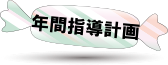(2) 年間指導計画における学級活動内容(2)の位置付け方
ア 学級活動の時数配分
内容(1)と(2)の配分については基準はありません。
本研究では、次のようなことに留意して、以下のような時数配分を提案します。(表1)
| ○ | 低学年では、学級生活や学校生活の適応ということが大きな目的ですので、他の学年に比べて内容(2)の時間の割合を多くする。 | |
| ○ | 中学年では、低学年での学校生活への適応に関する学びが充実してきている段階と捉え、学級を楽しくするための自発的、自治的な態度を育成していく内容に重点を置くことから、学級活動内容(1)の時間を多くする。 | |
| ○ | 高学年は、学級全体としてまとまりをもち、自治的活動を十分に行う中で、集団としての結び付きの大切さを感じたり、児童それぞれに集団の中での自己の在り方を考えたりする段階です。そこで、学級活動内容(1)の時間を中学年より更に多くする。 |
表1 小学校における各内容の時数配分例
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容(1) | 17時間 |
18時間 |
21時間 |
21時間 |
25時間 |
25時間 |
| 内容(2) | 17時間 |
17時間 |
14時間 |
14時間 |
10時間 |
10時間 |
| 特別活動は、各学年ごとに年間35時間と定められています。その時間内で、学級活動の各内容項目について時間を配分します。その際、内容(1)、(2)、(3)それぞれの活動内容は各々独立していると考えるべきものではありません。 |
|
|||||||||||||||||
| 生徒の実態や取り上げる題材に応じて、内容間の関連や統合を図ることも考えながら、計画的に配分する必要があります。 | 表2 中学校における各内容の時数配分例
|
||||||||||||||||
イ 題材を位置付けるときの留意点
・ |
1学期(2、3学期)のめあてを考えよう(2)−ア | |
| ・ | 夏(冬)休みの計画を立てよう(2)−イ | |
・ |
かぜの予防をしよう(2)−カ |
・ |
夏(冬)休みの計画を立てよう(2)−キ | |
・ |
望ましい食習慣を身に付けよう(2)−ケ |
【小学校の例】
| ・ |
男女仲良く協力して生活しよう(2)−ウ ・・・運動会の前 |  |
|
・ |
図書館の本をたくさん読もう(2)−オ ・・・読書月間、図書館祭りなど | ||
| ・ | 虫歯になりにくい食生活を考えよう(2)−カ ・・・虫歯予防週間 |
・ |
仲良く協力して練習に取り組もう(2)−エ ・・・体育大会、合唱コンクール | ||
・ |
一人暮らしのお年寄りに喜んでもらう年賀状を送ろう(2)−カ ・・・ボランティア活動 |
「小中接続期の時期区分とねらい及び題材例」
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続前期 | 小学校第6学年9月 〜小学校卒業 |
小学校卒業へ向けて学習と生活を充実させ、中学校への不安を取り除き、期待をもたせる。 | 「一年間の自分をふり返り、中学校に向けてがんばることを考えよう」 小学校で頑張ってきたことを生かしたり、中学校生活に向けて、まだ自立しきれていないところを振り返ったりし、中学校進学に向けて希望や目標をもって頑張ることができるようにする。 |
||||
| 接続中期 | 中学校入学 〜ゴールデンウイーク明け |
中学校での学級、学年の生活に慣れさせ、 小学校の最高学年と しての経験を引き出し 、自主的・実践的な態度を醸成する。 | 「自分を知る、友だちを知る」 中学校生活を意欲をもって気持ちよくスタートできるように学級で話し合い、お互い励まし合ったり協力し合ったりしながら、めあてを実現させていくようにする。 |
||||
| 接続後期 | 中学校第1学年 ゴールデンウィーク明け 〜10月中旬 |
中学校での新しい生活や新しい仲間の中で、 次第に自分らしさを表現できるようにする。 | 「気持ちを言葉で表そう」 中学校の生活にも慣れ、教師も生徒も緊張が解け始めたころがトラブルが起こりやすい時期でもある。そこで、お互いの気持ちを考えることができる題材で自分たちの生活を振り返らせることにより、新しい仲間の中で、自分らしさをきちんと表現できるようにする。 |
| 不登校や暴力行為が中1の夏休み以降に一気に増える問題を、いわゆる『中1ギャップ』と呼んでいます。小学校と中学校の学習や生活に大きなギャップがあることが原因だと考えられています。この問題の対応について、特別活動は大きな役割を果たすことができます。最も効果が期待できるのは、小学校の出口と中学校の入り口の指導について、中1ギャップの対応を意識して意図的、計画的に行うことです。 |
| 小1プロブレムや中1ギャップへの対応は、新しい生活や集団への適応の指導が中心になります。学習指導要領において学級活動の(2)については『日常の生活や学習への適応及び健康安全』(小学校)『適応と成長及び健康安全』(中学校)と示されているとおり、このような問題に直接働きかける役割を担っています。 |

そこで、接続前期、接続中期、接続後期のねらいを踏まえ、次のように研究を進めました。
| (イ) 年間指導計画に位置付けた例 | ||
|
年間指導計画に位置付けた例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2012 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |