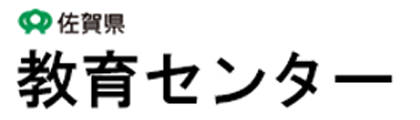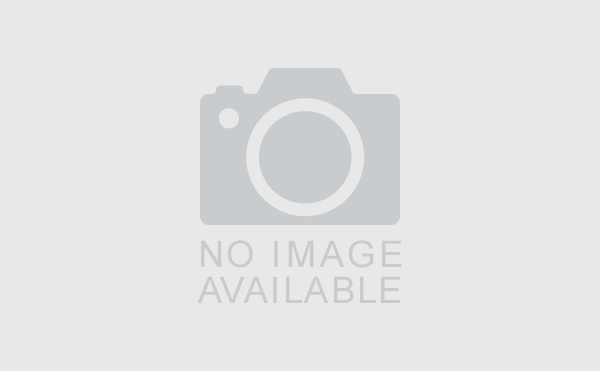LDについて
| ●基本的には全般的な知的発達に遅れはありません。 | |
| LD児は、知能検査などの結果から知的発達の遅れは見られません。ですから、学習指導上の配慮は必要ですが、基本的に通常の学級で学習をします。 |
|
| ●聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力のうち、特定の能力の習得に著しい困難があります。 | |
| LD児には、個人内の能力にアンバランスがあります。例えば、「計算問題は得意だが、文章題や図形問題は苦手」、「話して表現することは上手だが、ひらがなを読んだり書いたりすることがとてもむずかしい」などです。 | |
| ●原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されています。 | |
| LD児は、見たり聞いたりした情報を受け止め、整理し、関係づけ、表出する過程の情報処理をつかさどる中枢神経系のごく一部が、適切に働いていないのではないかと考えられています。 | |
| ●視覚・聴覚の障害や知的障害、情緒障害、環境の要因は直接の原因ではありません。 | |
| LD児の学習時における様子は、視覚・聴覚障害、知的障害、情緒障害のある子どもに似ていることがあります。しかし、それらは直接の原因ではありません。また、家庭や学校を含む生活環境、しつけや指導の様子も、直接の原因にはなりません。ただし、LDのことをよく分からずに不適切なかかわりを持つことによって、二次的な問題を引き起こすことがあります。 | |
子どもたちへの支援
| 工夫の視点 | 工夫の方法 | |
| 指示の出し方の工夫 | ○話し手に注目させる ○短い言葉で伝える |
一度に伝えることはひとつにして、タイミングのよい声かけを工夫しましょう。 |
| 指導内容の工夫 | ○指導内容を細かく分ける (スモールステップ) |
その時間の学習のスケジュールやめあてをメモにして、はじめる前に子どもにわたしておくなど、見通しが持ちやすくなるようにしましょう。 |
| 課題の工夫 | ○できる課題に取り組ませる ○励まし、自信をもたせる |
失敗した経験を積み重ねやすい子どもたちです。できる課題に取り組み、できた経験や満足できる経験を積めるようにしましょう。 |
| 板書の工夫 | ○文字量を減らす ○色や大きさを考える |
文字と文字、行と行の間のスペースの空け方や、色使いの工夫でずいぶん見やすい板書になります。また板書をノートに書き写すまでのちょっとの間でも内容を覚えておくことが難しい子の場合、早く消してしまうと写せなくなるので、消すタイミングにも注意しましょう。 |
| 書くときの工夫 | ○大きいマス目を使う ○問題数を少なくする |
書くことそのものが苦手な子は、書くスペースが狭いだけで勉強がおっくうになるものです。できるだけ書くことの負担を減らし、勉強に意識を向けやすいようにしましょう。 |
| 座席と教室環境の工夫 | ○指導者の近くにする ○掲示物をシンプルにする ○気が散る原因を減らす |
聞くことが難しい子には窓の外の音が邪魔になることがあるので、窓から離れて、またモデルとなる子がいたほうがいい場合は、最前列よりも、前から2~3列目にしてみましょう。 |
| 指導形態の工夫 | ○TTを効果的に活用する ○個別の学習時間を設ける |
担任だけが指導に当たるのではなく、チームを組んで支援にあたるなど、学校全体でこのような子どもたちにかかわる体制作りをするようにしましょう。 |
| 係活動の工夫 | ○活動内容を分かりやすくする ○毎日活動のある係にする |
その子にとってやりがいがあり、みんなに感謝される係や、その子の興味が生かせる係を選びましょう。 |
| 宿題の工夫 | ○子どもに応じて調整する | 宿題の量を調節したり(漢字100字→50字)、その子が取り組みやすい別の宿題に変えたりして、ひとりでも家庭での学習に取り組めるような工夫をしましょう。 |
LDの子どもたち
| 子どもたちの様子 |
対応のヒント |
| 聞き間違いが多い |
・みんなが静かになってから話す |
| 内容を分かりやすく筋道を立てて話すことが苦手 | ・ゆとりを持って、ゆっくり聞く ・「それは○○ということだよね」と丁寧に確認する ・話したいことを絵や箇条書きにして見せる |
| 形を写すことや地図を描くことがむずかしい | ・書きたい図だけを拡大する ・重なった図形には、あらかじめ色をつけてやる ・トレーシングペーパーを使う |
| 文中の言葉や行を抜かしたり繰り返して読んでしまう | ・拡大コピーしたものや、行間を広くしたプリントを用意する ・読んでいる行だけが見えるように、他の行をかくす ・読み取りたいキーワードや語句のまとまりにマーカーで印を付ける |
| 順番を待つのがむずかしい | ・「順番を守ります」と約束し、声に出して言わせる ・順番カードを作って、全員に持たせる ・めあてカードを作って、守れたらシールを貼るなどする |
| 学用品をよくなくす | ・机の中に区切りを付けたトレイを置く ・持ち物にはっきりと名前を書く ・持ち物に片付ける場所を書いてみる ・いつも使うものをリストにして持たせる |
| 相手の気持ちや立場を理解するのが苦手 | ・「○○さんは、□□と言いたかったんだよ」と具体的に説明する ・場面に合う言い方を、具体的に説明する |