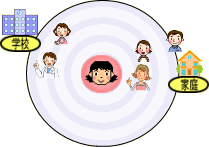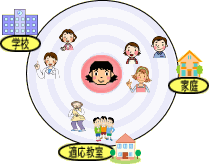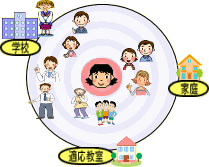ここでは、3つのポイント((ポイント1)「子どもの今」をとらえよう、(ポイント2)「子どもの今」につきあおう、(ポイント3)支援者の持ち味を生かそう)を生かした支援を考えていきます。
具体的には、以下のような手立てを事例を通して示していきたいと思います。
○(Point1)「子どもの対人関係と行動の状態チェック表」を使った子どもの状態把握 ○(Point2)心のエネルギーを貯える活動の実施 ○(Point3)連携した支援のための個別支援シートの活用 |
以下、A子(中学3年生)の事例を通して、3つのポイントを生かした支援を考えてみます。
【事例の概要】
小学6年生の6月から、友人関係のトラブルがきっかけとなり不登校になる。
中学校への入学を契機に、登校するようになるが、5月中旬から欠席が目立ち始め、6月には全く登校しなくなった。
中1の10月から、本人の希望で、適応教室へ通級し始めた。
その後、学校(担任)、保護者、適応教室指導員の3者を中心として連携が図られた。
A子は、支援者それぞれに見守られながら、心のエネルギーを貯えていった。そして、しだいに学校へ登校することもできるようになり、希望する高校に合格し、中学校を卒業した。
ここで、A子の回復過程を「心のエネルギー曲線」を使って表すと、次のようになると考えられます。
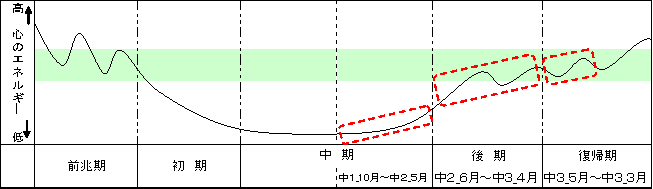 |
ここでは、上記で示された「中期」、「後期」、「復帰期」の3期におけるA子の行動や様子及び支援者のかかわり等を表で示します。