| 集団全体の仲間づくりとともに、本音を互いに伝え合う、対等な人間関係づくりを考えましょう。 ・仲間への関心を高めたり、助け合ったりできるような活動を増やしましょう。 ・係活動や行事などで、子ども同士がかかわる場面を多くつくりましょう。 ・信頼体験をねらいとした、構成的グループ・エンカウンターを取り入れてみましょう。 ・「3分間スピーチ」など、日常的に継続される活動において、 温かな雰囲気(人間関係)の中で本音を 伝え合う場面を工夫しましょう。 ・教師が日常的に、ルールの大切さについて話しましょう。 ・「心のノート」などの教材を活用してルールの大切さについて考える時間や、具体的な場面での対応に ついて話し合う時間を設けましょう。 ・「ありがとう」の声掛けを増やす取り組みを進めましょう。 ・道徳の時間などに、「感謝することの大切さ」について考える時間をもちましょう。 |
||||
 |
||||
| 友達同士の交流を深めていくような場の設定や、他者理解が進むような手立てを考えましょう。 ・日常の中で、協力して活動する場面を増やしましょう。 ・グループで取り組む活動場面を増やしましょう。 ・子どもが自分の気持ちを表現しやすい手立てや機会を工夫しましょう。 ・子ども同士が自分の気持ちや考えを素直に表現し合い、互いの大切さについて考える時間を もちましょう。 ・集団活動等において、あまり交流のない子ども同士の交流が深まるようなグループの編制を工夫しま しょう。 ・他者理解をねらいとした、構成的グループ・エンカウンターを取り入れてみましょう。 ・友達とのかかわり方(言葉の掛け方など)について、具体的な場面を設定し、示しましょう。 |
||||
 |
||||
| 自己肯定感(ありのままの自分でいいんだと思う気持ち)を高めるかかわりの工夫とともに、 集団における有用感(だれかの、また、何かの役に立っていると思う気持ち)や承認感(認められて いると思う気持ち)を高めるような手立てを考えましょう。 ・様々な場面をとらえ、子どものいいところや頑張り、できるようになったことを認める言葉掛けを しましょう。 ・他者とかかわる中で、自分のいいところに気付くような場面を設定しましょう。 ・集団活動の中で、個に応じた役割を設定しましょう。 ・係活動など、日常的な場面において、個々が活躍できる場面を増やしましょう。 ・自己理解を進めるために、子どもが自分を見つめる機会を設定しましょう。 ・自分の短所も、見方を変えると長所になるという「リフレーミング」の考えを生かしましょう。 |
||||
 |
||||
| 興味・関心を高め、理解を進める授業の工夫を行うとともに、発表したり質問したりしやすい 環境づくりを考えましょう。 ・ティームティーチングや少人数授業など、きめ細かな指導を行いましょう。 ・体験型学習など、子どもの興味・関心を引き出す授業の工夫をしましょう。 ・小集団の中で発表しやすい場面を設定するなど、個人の考えを積極的に伝える機会を増やし ましょう。 ・少人数のグループで、互いに教え合う時間を設定しましょう。 ・個々の勉強法や学習内容などについて、情報交換する機会を設定しましょう。 ・子どもの知的好奇心を促すような課題(選択課題など)への取り組み、家庭での自由学習、総合的な 学習の時間における探究活動などを計画しましょう。 ・小さな成長でも見取って評価するなど、子どもが成果を自覚できるような手立てを工夫しましょう。 |
||||
 |
||||
| 子どもとの信頼関係を深めるコミュニケーションのとり方について考え、日常の声掛けやかかわりを工夫しましょう。 ・やり遂げた仕事などに対して、どんな小さなことでも、感謝の言葉を掛けましょう。 ・指導的なかかわりだけでなく、子どもと一緒に活動する中で、教師自身の経験や考えを話す機会を つくりましょう。 ・休み時間に一緒に遊んだり、日常的にかかわったりと、子どもが気軽に話せる機会をつくりましょう。 ・日記などに、先生に対するメッセージ(先生からのきつい一言など)をテーマにして書かせてみましょう。 ・自分の言動について、子どもの立場に立って、意識して振り返る機会をもちましょう。 |
||||
 |
||||
| 支援案リンク集はこちら→ | 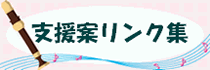 |
|||
| 支援案作成の手順はこちら→ | 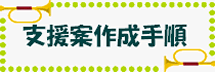 |
|||
| |
||||