私たちが、身のまわりにあるいろいろなものを見るときには、様々な視覚機能を働かせている。見たいものが「はっきり見えているか」ということだけでなく、その情報が「何であるか」を把握し、その情報に「どう反応したらよいのか」を考え、適切に行動することが「見る」という活動である。この「見る」活動を支えている視覚機能として、主に、「視力」「両眼の運動機能」「視覚情報処理機能」がある。これらの機能が効率よく働き合うことで「見る」活動が円滑に行われることになる。
そこで本研究では、「視力」「両眼の運動機能」「視覚情報処理機能」の3つの視覚機能をまとめて「見る力」とした(資料1)。
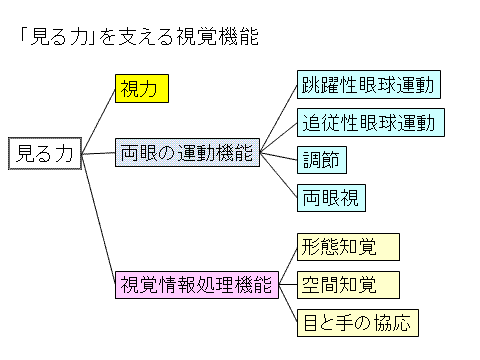 |
 |
資料1 「見る力」を支える視覚機能 |
|
| ア 視力 | |
「見る」ためには、まずは、「視力」が必要である。奥村(2010)は、「視力」を「注意して見分けようとする対象物を、どれだけ細かく見分けることができるかを表す単位」と述べている。この「視力」の測定法としては、眼科や保健室等での視力検査で用いられている「字づまり視標」(資料2)で測定されている。1.0や0.5といった値で「視力」が数値化されており、これは、「字づまり視標」に描かれている様々な大きさのランドルト環の隙間を識別できるかで評価されている。ただ、ここで評価される力は、ある一定の距離にある単純な形をどの程度小さいものまで識別できるかであり、「見る」活動で言えば、入り口の部分の力である。そのため、一般的に「視力」が低いと言われる近視、遠視、乱視がある場合は、眼鏡やコンタクトレンズ等を使って「視力」を補っている。
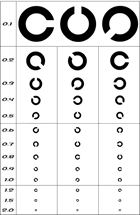 資料2 字づまり視標 |
||
 |
||
| イ 両眼の運動機能 |
見たいものを「視力」によって取り込む際には、そのものの方向に眼球を動かし、それがはっきりと映し出されるように、眼の中の水晶体というレンズの厚みを調節している。カメラを使って撮影をすることに例えるならば、写したい人やもの(被写体)を決め、その方向にカメラを向ける。カメラを向けた後、被写体の中で最も写したい場所をファインダーの中央に合わせ、シャッターを半押しする。すると、自動で焦点(フォーカス、ピント)を最適な状態に調節し、被写体が鮮明に撮影される。このようなことを瞬時に幾度となく行っている。さらに、右眼と左眼の両眼を使うことで立体感を感じることができるようになる。これらのような様々な機能が円滑に正常に行われることで、「視力」によって取り入れられた情報が「何であるか」を把握できるようになる。そこで、「両眼の運動機能」について、「跳躍性眼球運動」、「追従性眼球運動」、「調節」、「両眼視」別に詳しくまとめる。 |
両眼の運動機能により、見たいものをとらえることができ、脳の中に映像を映し出すことができたとしても、それが「何」であるかを判断しなければならない。そして、その映し出された映像が、どのような動きをしているのか、またそれに対してどう対応するのかを考えることになる。さらに、考えたことを実際の運動として表現することが必要になる。これらの働きが、「視覚情報処理機能」と呼ばれている。そこで、「視覚情報処理機能」について、「形態知覚」、「空間知覚」、「眼と手の協応」別に詳しくまとめる。
(ア) 形態知覚
「跳躍性眼球運動」や「追従性眼球運動」、「調節」さらに、「両眼視」が円滑に行われるようになって初めて、見たいものが鮮明な映像として脳の中に描かれる。そして、次に行われるのが、見たいものが「何であるか」を理解することである。この段階では、脳の中に描かれた映像は、様々な点や線、色等で表現されており、それを統合して何かの形を把握することになる。この働きは、「形態知覚」と呼ばれている。
(イ) 空間知覚
また、「形態知覚」と同時に、見たいものがどのように動いているのか、どのくらいの距離の場所にあるのか、他のものとどのような位置関係にあるのか等の空間的な位置関係を把握することも必要である。この働きは、「空間知覚」と呼ばれている。
(ウ) 眼と手の協応
例えば、テニスでボールを打つ動きで考えると、相手がサービスで打とうとするボールを「跳躍性眼球運動」により探し出し、そこに焦点を「調節」して合わせ、「形態知覚」により、ボールと認識し、「追従性眼球運動」により、ボールに合わせた焦点を持続させる。このときには、「両眼視」により、自分とボールとの距離感を「空間知覚」を使いながら把握し、向かってくるボールに合わせて、両眼の視線を内側に寄せてくる。そして最後に、打ち返すために最適な位置にボールが来たときに、「打つ」という動作が行われる。打ち返すためには、向かってくるボールと自分の位置関係を把握し、自分自身の体をその場所に動かしたり、ボールの軌道に合わせて、ラケットの振り方を修正したりする必要もある。この眼から入った情報に対して、手や体の動きで「どう反応するか」が求められてくる。この働きは、「眼と手の協応」と呼ばれている。
「眼と手の協応」は、運動としてあらわれてくる。生活や学習の中でのあらゆる活動において、手や指、その他の体の部位を正確に素早く動かさなければならない。運動の中でぎこちない動きをしたり、うまくやり遂げることができなかったりする児童生徒の姿を見て、その児童生徒の様子を「不器用」と表現することがあるが、これらは、これまでに述べてきた「視力」や「両眼の運動機能」、「視覚情報処理機能」が円滑に働いていないために起こっているものと考えられる。
(ア) 視力
まずは、視力が必要である。これは、眼科や学校等で行われる視力検査の数値で確かめることができる。ただ、そこで測定される視力は、5m以上の距離で測定される「遠見視力」であることが多い。視力検査で視力が1.0と評価されたとしても、教科書等を読む際に必要となる、30cmの距離で測定される「近見視力」の値が低ければ、文字を読むことに影響を及ぼしていると考えることができる。
(イ) 両眼の運動機能
「遠見視力」や「近見視力」の値が正常である、または、眼鏡等での矯正視力が日常生活に影響を及ぼさない程度であれば、「両眼の運動機能」における働きの不全が考えられる。教科書等を読み進めるためには、読むべき文字を探さなければならない。数多く示されている文字から読むために必要な文字を探し出すためには、まずは、「跳躍性眼球運動」と「調節」が必要となる。この2つの働きを瞬間的に何度も繰り返すことで、読むべき文字を探し出すことができる。しかし、「跳躍性眼球運動」の働きに弱さがあると、文字から文字へと視線を移動させることが困難になったり、動かしたい場所にきちんと動かせなかったりすることが考えられる。また、「調節」がすばやくできないと「跳躍性眼球運動」により、読みたい文字へ移動できたとしても焦点が合わずに、鮮明な映像としてとらえることができなくなる。さらに、これらの働きは、片眼それぞれ別々に行われているのではなく、両眼で1つの文字を同時にとらえている。この「両眼視」がうまくできない斜視のある場合にも、読むことのつまずきとして現れてくると考えられる。
また、「追従性眼球運動」により、しばらくの間、読みたい文字に、視線を固定することができるようになる。次の文字へ移動をする際には、「跳躍性眼球運動」よりも「追従性眼球運動」を多く使うことで、なめらかな視線の移動が可能となる。その際、「調節」の働きにより焦点も合わせながら、かつ「両眼視」で行うことが必要となる。
このように、「跳躍性眼球運動」や「追従性眼球運動」、「調節」、「両眼視」の働きの状態を把握することで、読み書きのつまずきの要因を知ることができる。
(ウ) 視覚情報処理機能
「視力」、「両眼の運動機能」により見たい文字が鮮明な映像として脳の中に映し出された後に行われるのが、その文字が「何であるか」を識別する作業である。そのときに映されている文字は、点だけで示されたり、無意味な線が交り合ったりした図形のようなものである。まずは、その点の位置や大きさ、向き、線の位置や長さ、交わり、向きなどを正確にとらえることが必要になる。次に、そのすべての関係性を把握し、全体としての形を作り上げる。そして、これまでに学び得た知識として記憶されている文字と照合し、その文字の発音や意味等を確認することとなる。これは、「形態知覚」の働きによって行われている。この「形態知覚」の働きに弱さがあると、文字の読みに影響を及ぼす。点や線の大小、長短、他の点や線との位置関係などを正確に把握することができないと、正しい字形にはならず、誤って字を理解し、違う発音をしてしまうことになる。ただし、「形態知覚」の働きに弱さがあることを確認するための前提としては、知識として文字の形や音声、意味等を正確に記憶しているかを知っておく必要がある。また、構音障害のような発音する際の口腔内の運動機能不全により、発音の誤り等がないことを確かめておかなければならない。
書くことがどのような手続きで行われているかを考えると、眼の前にある文字が「どのような形をしているか」を把握し、これまで身に付けた知識としての字形と照らし合わせながら、その文字が「どの文字なのか」を理解し、最後に、照らし合わせた字形と同じ形として表現する力が必要となる。この一連の働きが、円滑に行われることで自分の思いや考えを書き綴ることが可能となる。そこで、「見る力」を支える3つの視覚機能毎に、書くことのつまずきの要因を考える。
(ア) 視力
学校では、書くことの主な活動としては、「自発書字」、「視写」、「聴写」がある。「自発書字」としては、自分の考えや思いをそのまま文字として表すことであり、「視写」は、提示された見本を見ながら、それと同じような文字や図形として表すこと、「聴写」は、聞こえたことを文字や図形として表すことである。「視写」は苦手であるが、「自発書字」や「聴写」はできる場合については、「視力」に問題があることが考えらえる。その際には、適正な視力があるかを確かめなければならない。適正な視力はあるが、書くことに苦手さのある場合には、以下の「両眼の運動機能」や「視覚情報処理機能」の働きについて確かめることが必要となる。
(イ) 両眼の運動機能
視写をする際には、書きたい文字がどのような形をしているかを正確に理解するまでの過程は、前述の読むことと同じである。視写において必要となる働きとして、「跳躍性眼球運動」と「調節」がある。視写では、書きたい文字の見本とこれから書こうとしている場所を見比べる作業を頻繁に行わなければならないが、その際に、両方の間の視線の移動を素早く正確に行うためには、「跳躍性眼球運動」と「調節」が円滑に働くことが求められる。また、授業の中で新しい漢字を学ぶ際、教師が空書き(空中に文字を書くこと)をしたり、黒板に書いたりする様子を見ながら筆順を確認する時、教師の手元やチョークの先を見続けるためには、「追従性眼球運動」と「調節」が必要となる。この「追従性眼球運動」の働きに弱さがあると、すぐに視線がそれてしまい、見るべき場所を「跳躍性眼球運動」によって探し直さなければならなくなる。しかし、見るべき場所に視線が戻ったとしても、「追従性眼球運動」の働きに弱さがあるために、また視線がそれてしまう。これを、何度も何度も繰り返すこととなり、筆順を一連の流れとして理解できず、字の部分だけしかとらえることができないことになる。さらに、実際に文字を書くときには、「跳躍性眼球運動」により書き始めの場所を決めたり、「追従性眼球運動」により自分自身が動かしている鉛筆等の先に視線を保持し続けたりする働きも必要になるため、「跳躍性眼球運動」や「追従性眼球運動」の働きに弱さがあると、書くことに支障をきたすようになると考える。
また、これらの働きは、片眼でそれぞれに行われているのではなく、両眼を使って、それぞれの眼から入ってくる情報を均等に取り入れながら行うため、「両眼視」がきちんとできていることも必要になってくる。
(ウ) 視覚情報処理機能
文字を書くためには、書きたい文字を正確にとらえ、記憶することが必要になる。ここでは、まず、書きたい文字や覚えたい文字を「視力」や「両眼の運動機能」により脳の中に鮮明な映像として映し出し、映し出された点の位置や大きさ、向き、線の位置や長さ、交わり、向きなどを正確にとらえ、これらすべての関係性を把握し、全体としての形を作り上げる。このとき、「形態知覚」が必要であり、作り上げた形が記憶として残っていく。視写をする時には、「形態知覚」の働きに弱さがなければ、「形態知覚」により認識した形と記憶している形を瞬時に照合し、指先で鉛筆等を操作する。ただし、「形態知覚」の働きに弱さがあれば、誤って形を認識してしまい、見本として示された形とは異なる文字をあらわしてしまう。
実際に鉛筆で紙に文字をあらわそうとするときには、「空間知覚」や「眼と手の協応」の働きも必要になる。書きたいと思い描いている文字の1画目を書き、続いて2画目を書くときには、1画目との距離や長さ、交わり方等の空間的な位置関係を正確に判断しなければならない。そして、その判断したことを運動として手の動きで表現することになる。そのときには、手の動きがその向きでよいのか、長さはどうか、早さは適当か等についても、瞬間的な動きの中で判断し、調整を行うことが求められる。「空間知覚」の働きに弱さがある場合には、点や線の場所が正しくなかったり、長さが違ったり、交わり方がおかしくなったりしてしまい、字の形がいびつになってしまう。、また、「眼と手の協応」の働きに弱さがある場合には、自分が思い描いている形と照らし合わせながら確認し、もし違いあれば微調整をすることがうまくできずに、書きたいと思うものとは違う形になってしまうことがある。
また、書く際には、1本の指先だけの動きだけでなく、5本の指の動きや手首の動き、腕の動き、肩の動き等とも関係しており、書くことにかかわるそれぞれの体の部位の動きが連動して、書くことができるようになる。さらには、それを見ている頭が揺れ動くことなく静止した状態として保たれておくことも必要であり、体全体の姿勢の保持も必要となってくる。
例えば、書くことが苦手な児童生徒についてのアセスメントでは、内的な条件としては、その児童生徒の「視力はどうか」「眼が文字を追うことができているか」「形や空間をとらえることができているか」「鉛筆をスムーズに動かすことができているか」などの情報が必要になる。一方、外的な条件としては、児童生徒が書きやすい「文字の大きさの提示をしているか」「ノートのマス目の大きさは合っているか」「座席の位置は適当か」などの環境面を整理することが必要である。
そこで、本研究では、児童生徒の「見る力」の内的な条件のアセスメントを行い、児童生徒の「見る力」に合わせて、児童生徒が取り組むトレーニングを考えることとした。
「見る」ことは「理解する」こと 本田 和子・北出 勝也著 2003年 山洋社
| Copyright(C) 2011 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. 最終更新日:2011-03-30 |