| 技術・家庭科(家庭分野) | 〜課題選択学習を取り入れた食生活指導の工夫〜 | ||||||
| トップへ | 研究の概要 | 課題選択学習 | 食生活の調査 | 指導計画 | 授業の実践 | 研究の成果 | |
課題選択学習を取り入れた「献立作成の授業」の学習指導
| 1 題材 | 「朝食の献立を立てよう〜オムレツの調理を主菜として〜」 内容A(1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 題材について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝食の献立作成とした理由 生徒の食事調査の結果,朝食の摂食率は比較的良いが,食事の内容を見ると問題点が多かった。量が不足している,食品群の偏りが大きく5群だけを摂取しているなどである。そこで,栄養に関する学習を踏まえて,朝食の内容を見直し,自分で朝食を整えることのできる力を付けさせたいと考えた。最終的には,考えた献立で朝食を作って家族に食べてもらうことを目指した。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「オムレツの調理」を主菜とした理由 事前の生徒の調理に対する意識調査では,「肉料理」に並び「オムレツ」を学習したい,作れるようになりたいという関心が高かった。卵の調理は小学校でも取り扱われなくなったが,卵の調理について学習することは,その調理の多様性や経済性から考えても意義がある。さらに,朝食では取り入れやすいメニューであり,試しの調理実習(第1回の調理)では一人一人の技能の評価も可能となる。初めての献立学習であるが,主菜をオムレツとして1食分の献立を作成することで,献立作成が容易に進むと考えた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 献立学習について〜まず「1食分」から〜 献立作成は栄養や調理,食品選択などに関する学習が基礎となることから,食事作りの経験の少ない生徒にとっては難しい学習内容であるが,工夫が生かせる内容でもある。実習ごとに,実習した調理品を取り入れて1食分の献立作成を位置付け,繰り返し学習することでその定着が図れると考える。また,献立作成の際には,配膳図を描くことにより,いろどりや食品の概量,正しい配膳を視覚的に把握させていきたい。 |
【生徒が考えた献立例】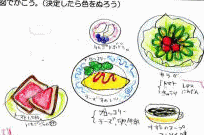 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 本時の選択課題の設定・提示について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒の能力,生活実態を考慮し,下の3つを設定し,生徒に1つを選択させるようにした。本時の課題①②は学習方法を意識し,課題③は内容も意識した発展的な課題である。
課題②は,本時の目標「栄養のバランスよく献立を立てる」には,どのようにすればよいかを考えさせその方法として提示する。既習事項の6つの食品群についておおむね理解している生徒は,副菜や飲み物を考える際に2群や3・4群から食品を考えていくことになる。 課題①は,6つの食品群について理解が不十分で,課題②では困難な生徒に配慮したものである。食品のいろどり(5色:白,赤,緑,黄,黒)を考えて献立を立てると,見た目もよく,自然にバランスが良くなる方法として提示する。5色の色を満たすように食品を選べばよいことから,抵抗感が少なく献立作成ができると考える。献立作成後,食品群が満たされたかどうかを確認させる。 課題③は,①②の発展的な課題として提示する。生徒の食事調査や事前の学習ではカルシウム不足傾向の強い生徒が見られた。このような生徒に対し,特にカルシウムを気を付けてとろうとする態度を養うには,有効な手立てと考える。栄養バランスを満たした上で,カルシウムの給源となる食品の調理を考えていくので難易度は高くなる。 難易度から見れば,①②③の順であるが,生徒の意思を大切にして主体的に課題を選ばせ,課題選択の理由を明記させることで課題意識をもたせ,意欲的に取り組めるようにしていく。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 学習指導計画(全6時間)と題材の評価規準
*調理ではペアを組み,オムレツときゅうり切りの相互評価ができるようにする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 本時の授業展開 (2.5時間計画)
6 学習シート・資料の紹介
7 授業を終えて
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 研究の概要へ戻る
研究の概要へ戻る ![]() その他の授業展開案は「研究の概要」にて紹介しています。
その他の授業展開案は「研究の概要」にて紹介しています。