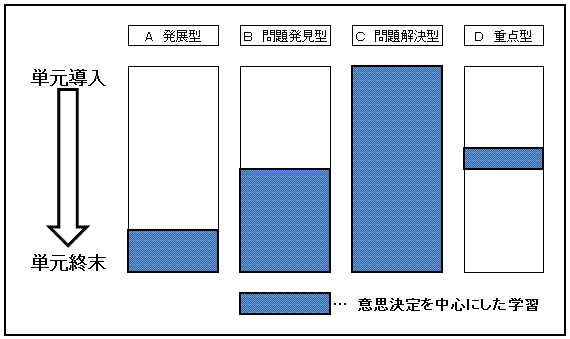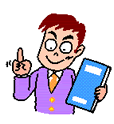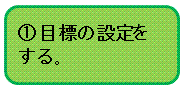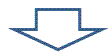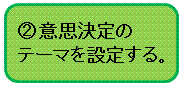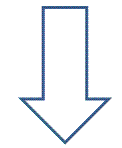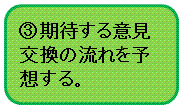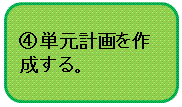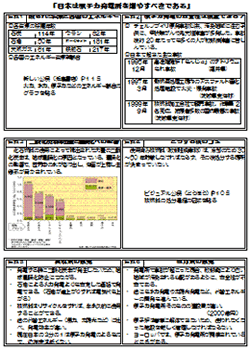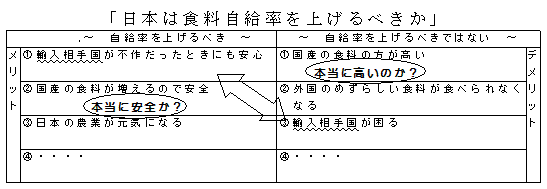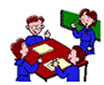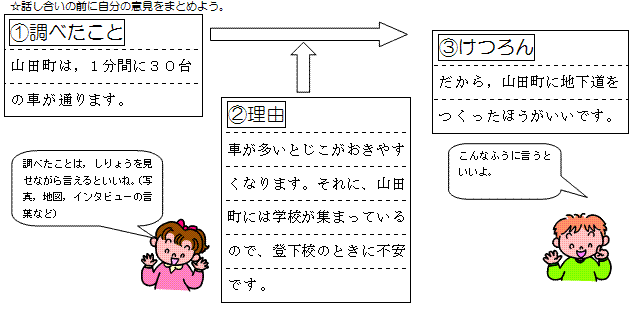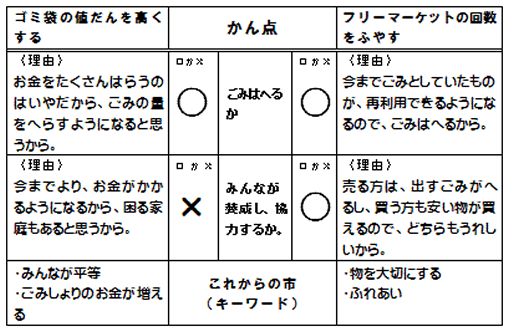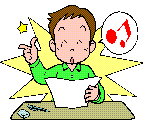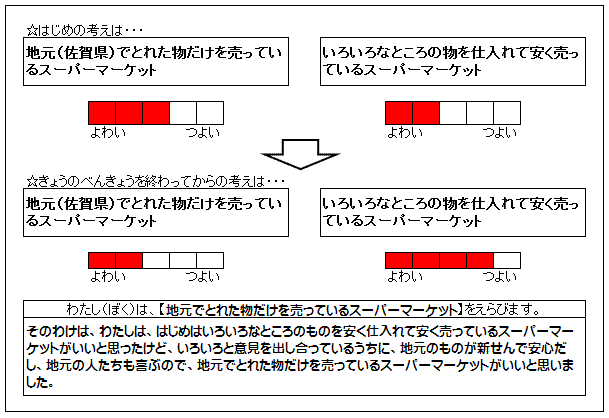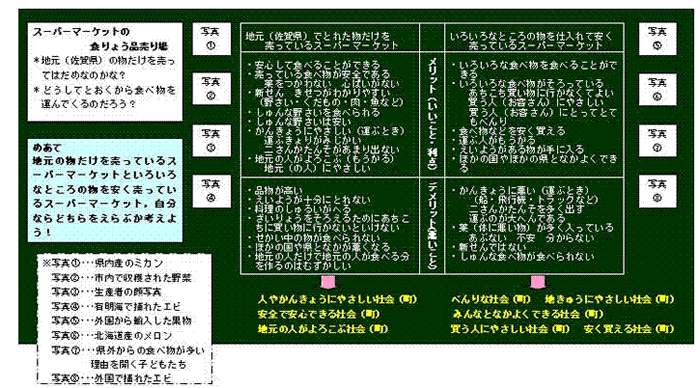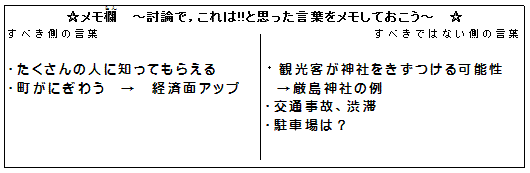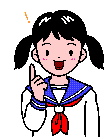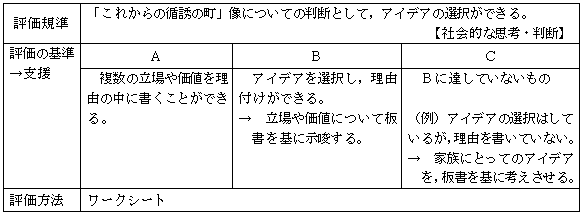○ 意思決定型の学習の単元における取り入れ方の違いによる分類 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「意思決定型の学習をしてみたいけど、単元の進め方が分からない」「意思決定型の学習は時間がかかり、難しそう」「習得すべき学習内容はどうするの?」「歴史学習ではどうすればいいの?」など、授業改善の必要性は感じているものの、具体的にどうすればいいのか分からなかったり、難しいと思い込んでしまったりしている先生方は少なくないようです。 そこで、まずは、意思決定型の学習での指導過程について、児童生徒の発達の段階や単元の内容を考えながら、図1のように、4つに分類することにしました。 図1 意思決定型の学習の4分類
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○意思決定型の学習を取り入れた単元づくりのポイント
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意思決定型の学習を取り入れた単元のテーマ例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の表にある意思決定のテーマ例については、選択した意思決定型の学習の取り入れ方の類型A~Dに合わせて、また、学年の発達の段階に応じて変更をする必要があります。
例えば、歴史学習では小学校、中学校で類似した学習が展開されます。江戸幕府の開国の学習では、意思決定のテーマはどちらも開国の是非となります。しかし、児童生徒の発達の段階を踏まえると、当然、学習内容に違いがでてきますし、取り扱う資料や学習内容が違うので、児童生徒の発言や論述内容の質も変わってきます。 小学校であれば、「あなたが~だったら」というように、当時の将軍や老中の体験を追体験するという学習内容が考えられます。中学校であれば、開国することはどのような意味や価値をもったのかについて、現在から見た歴史の評価を行うこともできます。 このように、当時の時代背景に焦点を当て「日本は開国すべきか(D:重点型)」とする場合と、その前後の時代背景まで考慮し「日本は開国すべきだったのか(A:発展型)」とする場合では、テーマを変更する必要があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会的な見方や考え方を深めさせるためには、資料活用や意見交換の場面における指導の工夫をし、児童生徒が明確な根拠を基に、学習問題に対する自分なりの考えをもったり、他者との意見交換などを通して判断したりしていくことが必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①資料活用をさせる上での工夫
(ア) 指導のポイント 新学習指導要領では社会科の授業時数が増えました。しかしながら、それでも意思決定型学習を取り入れた |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
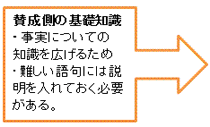 |
資料1 配付資料例(中学校3年生) → 実際の配布資料へ |
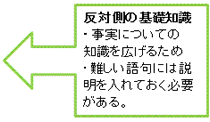 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
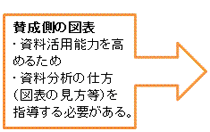 |
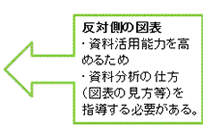 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
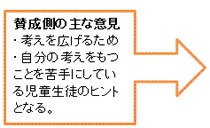 |
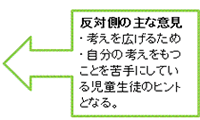 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
②多面的・多角的に考えさせるための工夫 (ア) 指導のポイント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料2 ワークシート記入例(小学校5年生 「日本は食料自給率を上げるべきか」)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
③論理的な考えに高めるための工夫 意思決定型学習を取り入れた授業に取り組んでみたけれども、児童生徒の意見の質を高めることに苦慮した (イ)
ワークシート作成のポイント
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料3 ワークシート記入例(小学校4年生 「○○地区交通事故0作戦を考えよう」 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
④自分の考えを再構成させるための工夫 (ア) 指導のポイント 中央教育審議会答申(平成20年1月)の小学校社会科についての「改善の具体的事項」の中にも、お互いの考 (イ) ワークシート作成のポイント ワークシートの形式としては、資料4のように、○と×を付けさせる方法がありますが、他にも優先順位を付けさ すえう方法と意見交換をしながら学級としての考えをまとめていくような方法も考えられます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料5 ワークシート記入例
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⑤意見交換場面における工夫
社会的な見方や考え方を深めさせるためには、意見交換場面を設定することも大切です。なぜなら、意見交 (ア) 指導のポイント 板書をどのようにまとめるかということは、大切なポイントの1つです。まずは、両方の立場がそれぞれどのよ この場面では、原則として、児童生徒の主体性を重んじることが大切ですが、意見交換の際、途中で、教師 資料6 板書例
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(イ) ワークシート作成のポイント 十分な目的意識をもたずに、意見交換に参加してしまう児童生徒は少なくありません。それでは、内容も深 資料7 ワークシート記入例(中学校1年生 「○○を世界文化遺産リストに推薦すべき?」)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本研究においては、児童生徒が社会の仕組みや制度だけではなく、「社会全体にとってよいことか」という社会的な価値を意識した見方や考え方を獲得させることに主眼をおいています。このように、社会的な価値を意識し、様々な立場や観点を踏まえながら社会的事象を見たり考えたりできるようになることを「深まり」ととらえ、目指す社会の在り方を考えさせることで、児童生徒の社会的な見方や考え方を深める指導の在り方を探ってきました。
近年、特に「指導と評価の一体化」ということが大切にされています。しかし、児童生徒の知識・理解の習得に比べ社会的な見方や考え方の変容や伸びは、測ることが難しいという問題があります。しかしながら、ぜひ育成したい大切な力であるからこそ、的確に評価を行い、その評価情報に基づいて、適切な指導をしていくことが重要となります。社会的な見方や考え方を評価するためには、できるだけ、具体的な評価規準と評価の基準を設定し、それらを見取っていくための方法を明らかにしておく必要があります。社会的な見方や考え方は質的なものであり、見えにくいことを考えると、それらを児童生徒の考えとして、発言や記述などの形で表現させ、それを見ていくことが有効であると考えます。 ここでは、評価の手順とポイントについて述べたいと思います。 【手順】 ①学習指導要領を基に、評価規準と評価方法を決める。 評価規準は、子どもにつけたい力(目標)を示すもので、質的なものといわれます。4観点の中の何を、どの 社会的な見方や考え方の評価については、社会的な思考・判断の観点で、児童生徒が意思決定した理由 ②評価の基準を設定する。 評価の基準は、評価規準で示したつけたい力(目標)がどの程度達成されたか判断するための目安となるも 本研究においては、評価の基準をA・B・Cの3つに設定していますが、A・Bの2つで設定する場合もありま 【評価規準と評価の基準の例】 単元名 「循誘公民館の利用者がふえるアイデアを考えよう」(小学校3年生) ③児童生徒の記述内容や発言を基に、評価する。 実際に、評価する際には、児童生徒の記述内容や発言を基に、その状況を見取っていくことになります。意思 決定場面においては、それぞれの児童がどのような考えなのか(どのような立場を選択しているのか)が一目で 【ポイント】 評価の基準に基づいて、形成的な評価を行うことが基本です。加えて、社会的な見方や考え方の深まりを見て |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
視点1 書かれている内容に、社会的事象にかかわる立場が増えているか。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2009 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日: 2010-03-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||