| TOP | 研究の概要 | 授業実践 | 研究のまとめ | |
|
|
|
||||||||||||
| 研究の概要 |
| ◆ | 研究テーマ |
| 確かな読みの力をはぐくむ国語科指導の在り方 | |
| −思考する場としての書く活動を通して− |
| ◆ | 研究のテーマ設定に当たって |
| 今日の国語科では「読むこと」の学習指導が大きな課題とされています。平成18年度佐賀県小・中学校学習状況調査においては、「読むこと」の領域の県全体通過率が、全国通過率をやや上回ったものの、これからは教材の内容を理解する力だけではなく、自分の考えや感想をもちながら主体的に読む力を付けることが課題とされています。また、平成17年度全国高等学校教育課程実施状況調査においても文章全体の展開や内容を的確に読み取ることができない生徒が一定数存在することが指摘され、佐賀県においても、平成15年度佐賀県高等学校学習状況調査で現代文の内容理解に関する設問の県全体の通過率の低さが課題としてあげられています。 そこで、本研究では、「目的を持って文章を読み、読み取った情報から自分の考えを構築する力」を確かな読みの力とし、思考する場としての書く活動と連動させることで、効果的に確かな読みの力をはぐくむことができるような学習指導の展開を探りたいと考えました。具体的には、中学校第2・3学年の「読むこと」の指導内容である「文章を読んで人間、社会、自然などについて考え、自分の意見をもつこと」と高等学校現代文の指導内容である「様々な文章を読むことを通して、人間、社会、自然などについて自分の考えを深めたり発展させたりすること」との連続性を意識しながら研究を進めました。 |
| ◆ | 「確かな読みの力」についての理論研究 |
| この「確かな読みの力」は単独で成り立つものではなく、様々な「国語力」によって支えられ、はぐくまれるものであると考えます。 理論研究では、井上尚美の「文章読解能力」の「基礎学力」についての考え方を基に、「確かな読みの力」を分析し、内容を検討しました。そして、分析の中で見えてきた、それぞれの側面を段階的に指導することでより効果的に「確かな読みの力」を身に付けさせることができると考えました。 |
| ◎ 「確かな読みの力」の関係図 |
| 「確かな読みの力」の実践的側面 (1) 論理的思考力 (2) 分析力 (3) 解釈力 (4) 批判・評価力 |
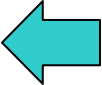 |
||||||||
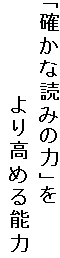 |
|||||||||
| 「確かな読みの力」の運用的側面 (1) 文章の内容を、随時解釈しながら読み取る能力 (2) 文章の内容を、展開を予測しながら読み取る能力 |
|||||||||
| 「確かな読みの力」の基礎的側面 (1) 文脈における語句の意味・働きを理解する力 (2) 文構造における関係性を理解する力 (3) 文章における関係性を理解する力 |
|||||||||
| 「確かな読みの力」を支える日本語の知識・技能 (1) 日本語に関する基礎的知識 (2) 日本語に関する基礎的運用能力 |
|||||||||
| ◆ | 「確かな読みの力」を支える「書く」活動 |
| 自分の考えを構築する | 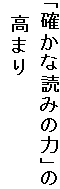 |
||||
| 書く活動 | 習得した知識・技能を活用し、 思考する場 |
||||
| 目的をもって文章を読む | |||||
| 書く活動 | 思考に必要な知識・技能の 習得の動機付け |
||||
| 本研究では、思考する場としての書く活動と連動させることで、効果的に確かな読みの力をはぐくむことができるような学習指導の展開を探ることとしました。読み書き指導の有効性、特に「読むこと」の力を付ける際「書く活動」が有効であるというのはよく言われることです。本研究においては、「確かな読みの力」を「目的をもって文章を読み、読み取った情報から自分の考えを構築する力」ととらえています。「自分の考えを構築する」際には、当然「書く活動」が必要になってくると思われますが、本研究では、中学校・高等学校のそれぞれの実践において、「文章読解」の段階においても「思考する場としての書く活動の場」を設定し、「目的をもって文章を読む」という姿勢の育成につなげていきたいと考えました。 |
| ◆ | 「確かな読みの力」の実践的側面を意識した授業 |
| 中学校での実践 | 高等学校での実践 | |||||||||
| 「分析の基礎的能力の育成 「批判的精神」の育成 |
「分析の実践的能力の育成 「評価力」の育成 |
|||||||||
| 比較的内容読解が簡単な文章で 「分析」の基礎的なスキルと一般的な概念の育成 |
難解な文章読解のためのスキルとして使えるような「分析」の実践力の習得 | |||||||||
| 本研究では、「確かな読みの力」の実践的側面における「分析力」「批判・評価力」の育成という目標を、中学校・高等学校の共通の目標として設定し、それぞれの校種で実践を行いました。 中学校では「分析」の考え方の習得と「批判的精神」の育成を目指し、高等学校では「分析」の実践的能力の育成と自己との対話を通した「評価力」の育成を目指しています。具体的には、中学校段階では比較的内容読解が簡単で身近な話題を扱っている新聞記事を利用することで基礎的なスキルと一般的な概念の習得を目指し、高等学校段階では難解な文章の読解のためのスキルとして使えるような実践力の習得と自己の考えを他者の考えとの比較を通して深めていくことを目指しました。 「書く」活動として中学校では、教科書にある説明的文章の分析を、語彙表現、叙述表現にとどまらず、隠された筆者の意図までを対象としました。具体的には、マトリクスに書き込んでいく作業をさせました。さらに、筆者の主張を取り入れ、その手法を用いて教科書以外の文章の分析を行い、筆者の主張の確かさを確認させました。最後に、自分が情報に接する際の視点を書くことで意識化させました。このような学習過程を通して、ともすれば受動的になりがちな「読むこと」の学習が、読みの成果を生かせる能動的な学習へと深めることができると考えました。高等学校では、一問一答式の発問をできるだけさけて、それぞれの意味段落毎に読解のポイントを提示し、それらについて思考する場を授業中に意識的に設定しました。ワークシートに生徒それぞれが読み取った内容や自分の考えを書き込んでいくという作業をさせることで、生徒に思考を促していくという試みです。目的を意識した「書く活動」を行うことで思考が整理され、そのことが自分の考えを構築していく際にも役立つのではないかと考えました。 |
| ◆ | 研究のまとめ |
| 研究のまとめはこちらです。 |