| �P�@���Z���w�ȋ����̈ӎ��������� | |
| (1)�@�����̖ړI | |
| �@�{���̐��w�ȋ����̎w�����@�Ɋւ���ӎ��Ǝ��Ԃ�m�邽�߂ɁC���������w�Z�̐��w�ȋ�����ΏۂɃA���P�[�g���������{���܂����B �@�V����ے��X�^�[�g����R�N�ڂ��}���C���ɁC�w�K�������ʂ���ۑ�Ƃ��Ďw�E����Ă���u�}�`�̈�v�̎w���𒆐S�ɋ����̈ӎ����ǂ��Ȃ��Ă���̂��C�܂��C�w���̎��Ԃ͂ǂ�����c�����C����̋��Ȏw���ɂ����Ă����ʓI�Ȏw�����@���������C���H�����ł̎Q�l���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂����B |
|
| �i�Q�j�@�����Ώ� | |
| �@�@ ���������w�Z���w�ȋ����S���i�P�X�W���j | |
| �i�R�j�@�������� | |
| �@�@ �����P�V�N�P�O���Q�S���i���j�`�P�O���Q�W���i���j | |
| �i�S�j�@�������ʂ̊T�v | |
| ��������ʁ@�P�V3���i�W�V�D�S���j ����Ȓ������ځ@�ӎ���������p���i�o�c�e�j �i�A�j�w�����ɂ�������i�̈�j�y�т��̗v�� �i�C�j�w�����@�̉��P�Ɋւ���ӎ� �i�E�j�����̎w������ �i�G�j���k�̗���x���Ⴂ�̈�Ƃ��̗v�� �i�I�j�}�`�̈�̎w���̎��ԂƍH�v |
|
| ����Ȍ��� �i�A�|�P�j�@�w�����ɂ�������i�̈�j �@�w�����ɂ�������Ƃ��āC�ł������I�����ꂽ���ڂ́C���ʉȁC���w�ȓ��i�����w�Ȃ��܂ށj�Ƃ��Ɂu���ʐ}�`�v�ł���B���ʉȂł�66.9���C���w�ȓ��ł�49.0���̋������I�������B �@������̍����w�Z�ɂ����Ă��C�u���ʐ}�`�v�ɂ��Ďw��������ł���C���炩�̑K�v�ł���ƔF�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B �@���̎��ɑ�����������́C���ʉȂƐ��w�ȓ��ł͈قȂ�C���ʉȂł́C�u���v�����v�i32.3���j�C�u�_���ƏW���v�i29.0���j�C�u���Əؖ��v�i27.4���j�C���w�ȓ��ł́C�u���v�i38.8���j�C�u�_���ƏW���v�i26.5���j�C�u���Əؖ��v�E�u��ԃx�N�g���v�i�Ƃ���24.5���j�ł������B �@�Ȃ�, �u���v�����v�ɂ��ẮC�w�����ɂ�������Ƃ��ď�ʂɂ��Ă��邪�C�ł��w�����ɂ�������Ƃ��ĂƂ炦�Ă��鋳���͏��Ȃ��C���ގ��̂̏o�藦���Ⴂ���߁C����̎w���ł͂���قǃE�F�[�g���u����Ă��Ȃ��ƍl����B �@�����̌��ʂ��Q�l�ɁC�u���ʐ}�`�v�𒆐S�ɁC�_���E�ؖ��Ƃ������w��������ȕ���̎��Ɖ��P�̎��_���l���Ă������Ƃɂ����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���t�P�j |
|
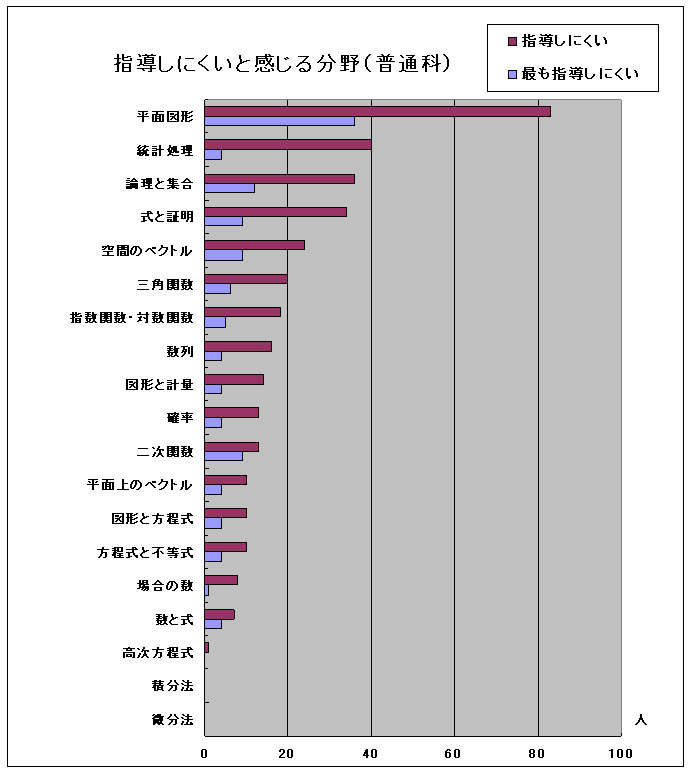 |
|
| �@�i�O���t�Q�j | |
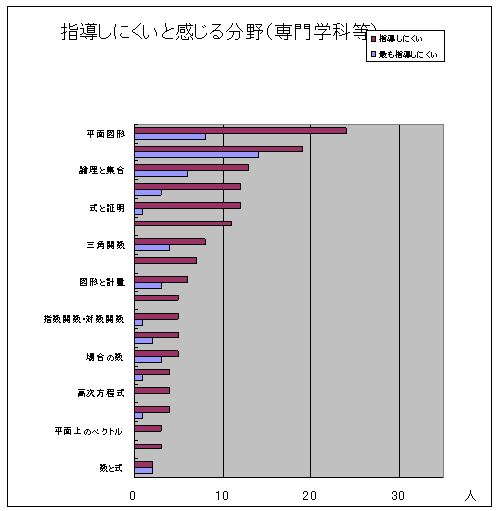 |
|
| �i�A�[�Q�j�@�w��������ȗv���ɂ��� | |
| �u���ʐ}�`�v���ł��w�����ɂ����Ɖ��������̉��C�u�����v���v���S�_���_�Ƃ���S�_�@�Ɋ��Z���ďW�v�����B �@���̌��ʁC���ʉȂł́C�i�`�Q�j�́u�����ɍ�������}���m�[�g�ɏ�������A��������l�����肷�邱�Ƃ����Ȃ��߁v���ł������C3.11�|�C���g�ł���C���w�ȓ��ł��C3.66�|�C���g�ƂقƂ�ǂ̋�������ȗ��R�̈�Ƃ��Ďx�����Ă���B �@���̎��ɑ��������̂́C���ʉȂł́C�i�`�R�j�u�_���I�Ȏv�l�́E�\���͂Ȃǂ��s�����Ă��邽�߁B�v�i3.08�|�C���g�j�C�i�`�V�j�u�w�����@�E�w���������ɂ��ĉ��P����]�n�����邽�߁B�v�i3.08�j�|�C���g�j�C�i�`�W�j�u���k���g���ǂ��炩�Ƃ������Ƃ��Ă��镪��ł��邽�߁B�v�i3.00�|�C���g�j�ł���B �@�܂����w�Ȃł́C�i�`�R�j�u�_���I�Ȏv�l�́E�\���͂Ȃǂ��s�����Ă��邽�߁B�v�i3.50�|�C���g�j�C�i�`�W�j�u���k���g���ǂ��炩�Ƃ������Ƃ��Ă��镪��ł��邽�߁B�v�i3.38�|�C���g�j�C�i�`�P�j�u��{�I�Ȓm����v�Z�͂Ȃǂ̊�b�w�͂��s�����Ă��邽�߁B�v�i3.13�|�C���g�j����ʂɂ��Ă���C���k�̋��ӎ����b�w�͂̕s���Ɍ���������ƍl���Ă���B �@�����������Ƃ���C���ꂼ��̊w�Z�E�w�Ȃ̉ۑ��c�����C�ӗ~�I�Ɋw�ԋ��ނ�w�����@�̉��P�Ɏ��g�ޕK�v������ƍl����B |
|
| ���I������ �i�`�P�j���k�Ɋ�{�I�Ȓm����v�Z�͂Ȃǂ̊�b�w�͂��s�����Ă��邽�߁B �i�`�Q�j���k�������ɍ�������}���m�[�g�ɏ�������A��������l�����肷�邱�Ƃ����Ȃ��߁B �i�`�R�j���k�ɘ_���I�Ȏv�l�́E�\���͂Ȃǂ��s�����Ă��邽�߁B �i�`�S�j���k�ɐV�����T�O��L���̒�`�ɑ����R�������邽�߁B �i�`�T�j�w�����Ԃ̌����ɔ����A�w�Z�ŏ\���w�����鎞�Ԃ�����Ȃ����߁B �i�`�U�j���̕���̋��ނ�����ɖ��͂�����e�ɉ��P����]�n�����邽�߁B �i�`�V�j���̕���̎w�����@�E�w���������ɂ��ĉ��P����]�n�����邽�߁B �i�`�W�j���k���g���ǂ��炩�Ƃ������Ƃ��Ă��镪��ł��邽�߁B �i�`�X�j���t���g���ǂ��炩�Ƃ������Ƃ��Ă��镪��ł��邽�߁B |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���t�R�j | |
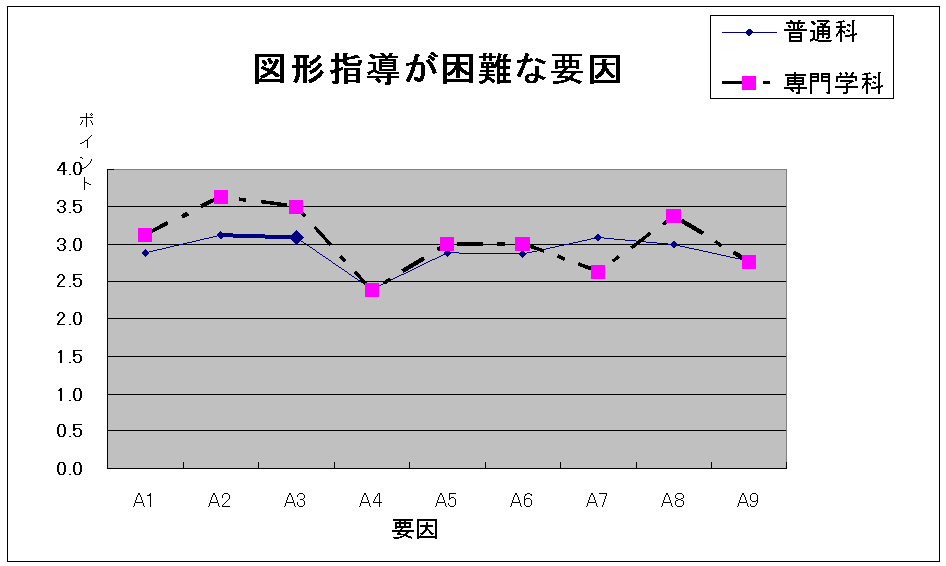 |
|
| �i�C�j�w�����@�̉��P�Ɋւ���ӎ��ɂ��� | |
| �@�@�u�}�`����v���w�����₷�����邽�߂̕���Ƃ��āC���ʉȁC���w�ȓ��Ƃ��ɁC�i�a�P�j�u���ȏ��E���W�̓��e�I���C���k�̎��Ԃ�i�H�ڕW�ɉ��������ފJ���Ɏ��g�ށv�i���ʉ�3.36�|�C���g�C���w�ȓ�3.38�|�C���g�j���ł������x�����B �@���Ɏx�������������̂́C���ʉȂł́C�i�a�R�j�u���w�Z�Ƃ̊Ԃňړ��������e�������߂Đ������C�P�����Ƃ̎w���v����������v�i3.28�|�C���g�j�C�i�a�Q�j�u�]�����̍쐬�Ɏ��g�ށB�v�i3.00�|�C���g�j�C�i�a�U�j�u��̓I�Ɋw�K�ɎQ���ł���悤�ȋ��ށE������H�v����v�i2.97�|�C���g�j�ł������B �@�܂��C���w�Ȃł́C�i�a�T�j�u�Љ�Ƃ̂������̒��Ő��w���w�ԈӖ���`���C�ӗ~�������o���悤�H�v����v�i2.88�|�C���g�j�C�i�a�Q�j�u�]�����̍쐬�Ɏ��g�ށv�C�i�a�U�j�u��̓I�Ɋw�K�ɎQ���ł���悤�ȋ��ށE������H�v����v�C�i�a�V�j�u���ޓ������L������A���S�̂Ńf�[�^�x�[�X�������肷��v�i�ȏ�R���ڂƂ�2.75�|�C���g�j�ł������B �@���̌��ʁC���ʉȂɂ��ẮC���k�̎��Ԃɉ��������ށE����̊J����i�߂�ƂƂ��ɁC�P�����Ƃ̎w���v�������������C�]�����̊J���Ɏ��g�ޕK�v������B�܂��C���w�Ȃɂ��ẮC�}�`����̎w���ɓ������āC�Љ�Ƃ̂������̒��Ő��w���w�ԈӖ���`���ӗ~�������o���w�����@���H�v������C��̓I�Ɋw�K�ɎQ���ł���悤�ȋ��ށE������J�����邱�Ƃ��K�v�ł���B |
|
| ���I������ �i�a�P�j���ȏ�����W�̓��e�I���C���k�̎��Ԃ�i�H�ڕW�ɉ��������ފJ���Ɏ��g�ށB �i�a�Q�j���k�̗���x��I�m�ɔc���ł���]�����̍쐬�Ɏ��g�ށB �i�a�R�j�w�K�w���v�̂̉����ɔ������w�Z�Ƃ̊Ԃňړ��������e�������߂Đ������C�P�����Ƃ̎w���v����������B �i�a�S�j�R���s���[�^���̋@������p���C�w�����@�̉��P�Ɏ��g�ށB �i�a�T�j���k�ɎЉ�Ƃ̂������̒��Ő��w���w�ԈӖ���`���C�ӗ~�������o���悤�H�v����B �i�a�U�j���k����̓I�Ɋw�K�ɎQ���ł���悤�ȋ��ށE������H�v����B �i�a�V�j���̐搶�Ƌ��ޓ������L������C���S�̂Ńf�[�^�x�[�X�������肷��B �i�a�W�j�������Ɓi���J���Ɓj��ϋɓI�ɍs���C���Ɨ͂����߂Ă����B �i�a�X�j�������������E�Z���O�̌��C�ɎQ������ȂǁC���Ԃ���茤�C���d�˂�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���t�S�j |
|
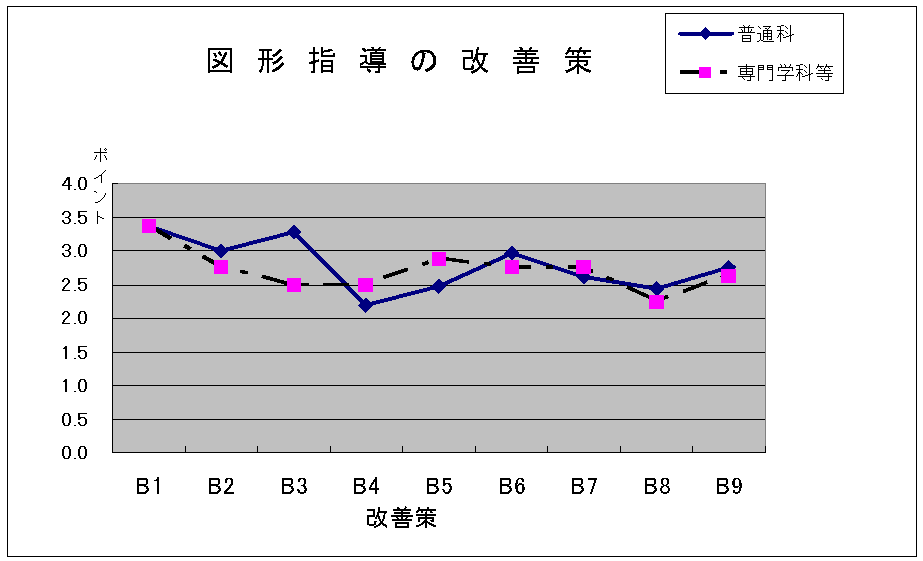 |
|
| �i�E�j�����̎w�����Ԃɂ��ā@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���t�T�j | |
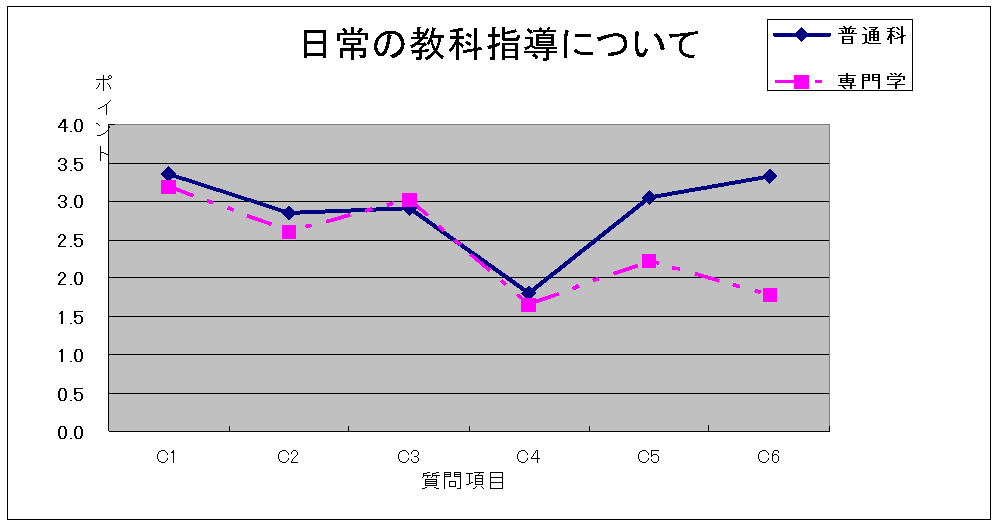 |
|
| �����⍀�ځ� �i�b�P�j���k�ɂ悭�w�����ė������m���߂���C�l�����������o�����������肷����Ƃ��s���Ă���B �i�b�Q�j�����̕��@�ʼnł������p�ӂ��Ďg���悤�ɐS�|���Ă���B �i�b�R�j�������ɂ�������ł́C���[�N�V�[�g���̕⏕���ނ��������Ď��Ƃ��s���Ă���B �i�b�S�j�R���s���[�^�����p������C�C���^�[�l�b�g��Ɍ��J����Ă���R���e���c�i���ށj�����p�����肵�Ď��Ƃ��s���Ă���B �i�b�T�j���Ƃ�������𒆐S�ɁC�ۑ���o���悤�ɂ��Ă���B �i�b�U�j�T���ۑ���o���悤�ɂ��Ă���B |
|
| �i�G�j���k�̗���x���Ⴂ�̈�Ƃ��̗v�� | |
| �@���k�̒蒅�������Ǝv������Ƃ��āC���w�������ł������I���������ڂ́C���ʉȂł́C�u����v�i51.6���j�ł���C���w�ȓ��ł́u�Q�����v�i67.3���j�ł���B �@���̎��ɑ�����������́C���ʉȂł́C�u�w�����E�ΐ����v�i39.5���j�C�u��ԃx�N�g���v�i36.3���j�C�u���ʐ}�`�v�Ɓu�O�p���v�i�Ƃ���29.8���j�������B �@�܂��C���w�ȓ��ł́C�u�}�`�ƌv�ʁv�i42.9���j�C�u�w�����E�ΐ����v�i32.7���j�C�u�O�p���v�i30.6���j�������B �@������̍��Z�ɂ����Ă��C�u����v�C�u�Q�����v���n�߁C���k�̗���x�����コ���邽�߁C���ꂼ��̉ۑ�ɉ������K�v�ł���ƔF�����Ă��邱�Ƃ������Ă���B �@�Ƃ�킯�C���ʉȂ̍��Z�ł́C���w�U�E�a�ɏW�����Ă���C�i�ق̉ۑ�ł���B |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���t�U�j | |
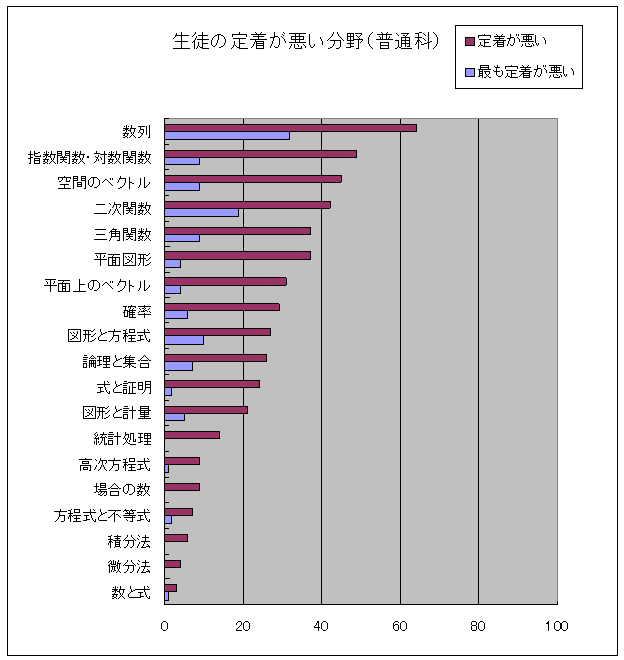 |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���t�V�j | |
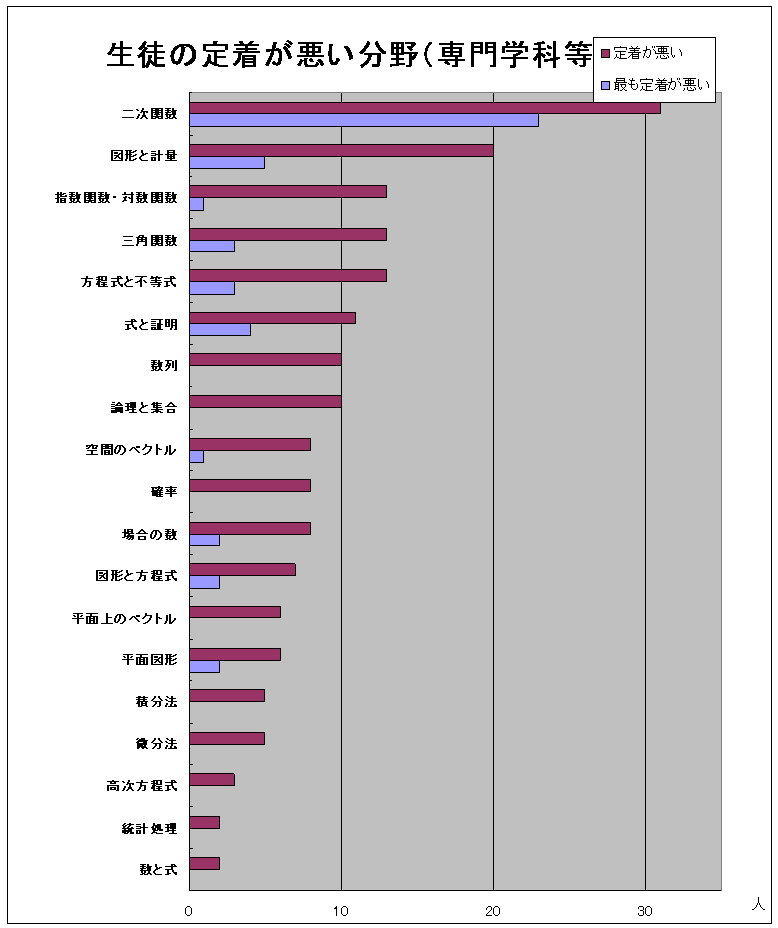 |
|
| �i�I�j�}�`�̈�̎w���̎��� | |
| �@���ʐ}�`�Ȃǂ̐}�`�̈�̎w���Ŏ��g��ł��鍀�ڂƂ��āC�����x�������ڂ́C���ʉȁC���w�ȂƂ��ɁC�d�T�u��{�I�ȊT�O��p��E�L���̈Ӗ��̗����Ȃǂɂ��āC���J�Ȏw�����s���Ă���v�ŁC���ꂼ��C���ʉ�2.97�|�C���g�C���w�ȓ�3.12�|�C���g�ł������B �@���̎��Ɏx���������������ڂ́C���ʉȂł́C�d�V�u���Ǝ��Ԑ��̊W���ŁC�u�`���S�̎w�����s���Ă���v�i2.92�|�C���g�j�C�d�R�u���[�N�V�[�g���̕⏕���ނ��������Ď��Ƃ��s���Ă���v�i2.66�|�C���g�j�C�d�U�u�����ɍ�������}���ł���悤���Ԃ��m�ۂ��Ă���v�i2.58�|�C���g�j�������B �@�܂��C���w�ȓ��ł́C�d�U�u�����ɍ�������}���ł���悤���Ԃ��m�ۂ��Ă���v�i2.79�|�C���g�j�C�d�R�u���[�N�V�[�g���̕⏕���ނ��������Ď��Ƃ��s���Ă���v�i2.76�|�C���g�j�C�d�V�u���Ǝ��Ԑ��̊W���ŁA�u�`���S�̎w�����s���Ă���v�i2.50�|�C���g�j�������B �@������̊w�Ȃ̍��Z�ɂ����Ă��C�}�`����ɂ��ẮC�����납��C���J�Ȏw����S�|���Ă���ƂƂ��ɁC�⏕���ނ���������ȂǁC���Ƃ̏�������������s���Ď��Ƃ�����Ă���B �@�������C���ʉȂ̍��Z�ł́C�u���Ǝ��Ԑ��̊W���ŁC�u�`���S�̎w�����s���Ă���v�Ƃ������������Ƃ������ł���C�w���v���w�����@�̌������Ɏ��g�ޕK�v������B |
|
| �i�d�P�j���K�����ɂ��āC���O�ɐ��k�̓��B�x�̊m�F���s���w���ɐ������Ă���B �i�d�Q�j���w�j�̓��e�������ꂽ��C�g�߂Ȏ��ۂƂ̂Ȃ�����ӎ�������w�����s�����肵�Ă���B �i�d�R�j���[�N�V�[�g���̕⏕���ނ��������Ď��Ƃ��s���Ă���B �i�d�S�j���w�Z�ɂ�����w�����e�Ƃ̊֘A�܂��C���ނI���Ďw�����Ă���B �i�d�T�j��{�I�ȊT�O��p��E�L���̈Ӗ��̗����Ȃǂɂ��āC���J�Ȏw�����s���Ă���B �i�d�U�j���k���g�������ɍ�������}���ł���悤���Ԃ��m�ۂ��Ă���B �i�d�V�j���Ǝ��Ԑ��̊W���ŁC�u�`���S�̎w�����s���Ă���B �i�d�W�j���k������}�`�̐�����������������C�ؖ��������肷��悤�Ȏw�����s���Ă���B �i�d�X�j�R���s���[�^�����p������C�C���^�[�l�b�g��Ɍ��J����Ă���R���e���c�i���ށj�����p�����肵�Ď��Ƃ��s���Ă���B �i�d�P�O�j���k����̓I�Ɋw�K�ɎQ���ł���悤�ȋ��ށE������H�v���Ă���B |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���t�W�j | |
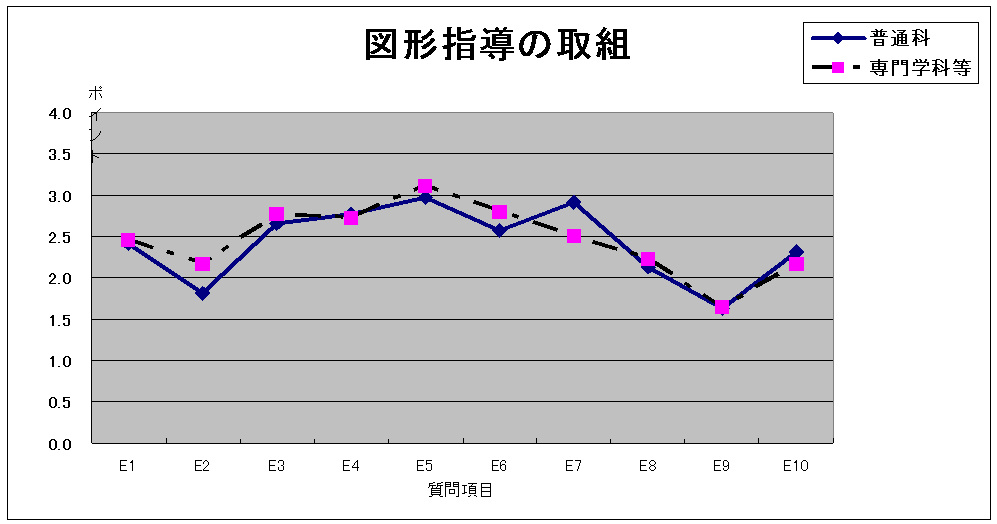 |
|