「生きて働く言語能力」の育成を目指した中学校国語科における学習評価の考え方
「生きて働く言語能力」の育成を目指した中学校国語科における学習評価の進め方
|
|||||||||||
| 学習指導要領の下での学習評価については、生徒の「生きる力」の育成をめざし、生徒の一人一人の資質や能力をより確かに育むようにするため、目標に照らしてその実現状況をみる評価(目標に準拠した評価)を確実に実施し、学習指導の改善に生かすことが重要です。併せて、学習指導要領に示す内容が確実に身に付いたかどうかの評価を行うことが求められています。 | |||||||||||
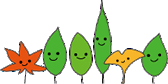
Copyright(C) 2012 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved.
