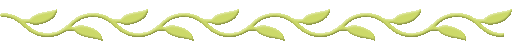
| 1 単元について | 2 単元の目標と評価規準 | 3 指導と評価の一体化 | 4 単元の指導計画 |
| 5 本時の展開 | ○ 学習指導案(PDF) | ○ 研究の実際TOPへ | ○ 3年生の実践へ |
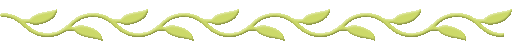
|
話し合いで考えを深め意見文を書いて発表しよう
~私たちの「佐賀県」~ |
| 「二つの意見から」(光村6上) |
(1) 意見文の特色
| ○ある事柄について自分の意見を述べて他者を動かそうとするものであり,意見とそれを生み出すもとになった理由から構成される ○相手意識,目的意識が明確な文種である |
(2) 意見文の学習上のねらいと指導上の留意点
① 意見文の基本的な構成について学ぶ
| ○教師作成の例文 | 意見文の基本的な構成要素(「問いかけ」「意見」「根拠となる事例(事実)」「まとめ(結論)」)が分かりやすい例文を提示する |
| ○練習学習 | 共通の題材「修学旅行の一番おすすめの見学地」で書き方を学ぶ場面を設ける |
② 相手を納得させることを意識した書き方について学ぶ
| ○教師作成の例文 | 2通りの例文(一つの立場から述べている意見文・異なる立場の考えに対する反論を入れた意見文)を比較させる |
| ○討論会の導入 | 自分と賛成の立場や異なる立場の友達と意見を交わして自分の意見のもとになった理由を再検討したり自分の考えとは異なる立場の考えについて考えたりすることで自分の立場からの主張だけでなく異なった立場の意見をも踏まえて納得させることができるように工夫する場面を設ける。 |
③ 自分たちが住む「佐賀県」について考える
| →生活を振り返り回りの人の存在やその思いに気付き今後の生き方につなげる |
【目標】
| ○佐賀についてテーマごとに調べたことをもとに自分の立場をはっきりさせて討論し深まった自分の意見を文章にまとめることができる。 |
【評価規準】
| ア | 国語への 関心・意欲・態度 |
○いろいろな角度から考え討論したり意見文を書いたりしようとしている。 |
| イ | 話す・聞く能力 | ○調べたことをもとに自分の立場や意図をはっきりさせながら討論会に参加している。 |
| ウ | 書く能力 | ○目的や意図に応じて取材,整理している。 ○自分の考えを明確に表現するために文章全体の組立ての効果を考えて書いている。 |
| エ | 言語についての知識・理解・技能 | ○文や文章にいろいろな構成があることについて理解し活用している。 |
(1) 単元の中に練習学習の時間を位置付ける
| ○共通の題材で意見文の「書き方」の指導ができる→意見文の構成と書き方のポイント |
| ○共通の題材で「討論会」における意見の取り入れ方についての指導ができる |
| ○個々のテーマで取り組む前に補充指導ができる |
(2) 意見文を書く過程において討論会を位置付ける
| ○討論会シートを活用することで取材・構成メモの簡素化を図ることができる |
| ○討論会で互いに意見や理由を述べさせる中で自分の考えが伝わるかどうかを実感させることができる |
| ○児童の評価意識(自己評価相互評価)を高めることができる |
(3) 叙述の過程においては,項目ごとに書き上げて(ミニ作文)いくようにする
| ○1時間ごと,1活動単位ごとの指導内容をより焦点化できる |
| ○1単位時間での指導や評価がしやすい |
| ○児童にとっては,各時間・各活動における学習目標の明確化につながる |
| 学 習 活 動 | 時間 | 指 導 上 の 留 意 点 | 資料等 |
| 学習課題をつかむ | 1 | ○2つの意見文を提示し「異なる立場の考えに対する反論を入れた意見文」のよさに気付かせる →例:説得力がある 等 ○意見文の生かし方について話し合わせる |
例文 |
| 評価について→ | 異なる立場の考えに対する反論を入れた意見文のよさに気付いているかどうかまたその理由についても述べることができているかどうかを授業中の話し合いの様子やノートの記述より見る | ||
| 練習学習をする ①討論会をする ②意見文を書く ③書いたものを読み合う |
3 | ○例文を参考に「書き方」を学ばせる ○「討論会シート」を工夫する →取材・構成に生かせるように ○書き方のよいところを見つけさせる →反論の書き出し 等 |
討論会シート1 ワークシート ワークシート(作品) |
| 評価について→ | 討論会シートへの記入状況やワークシート(「はじめ」と「終わり」を印刷し「なか」の部分だけを書き込むようにした原稿用紙)への叙述の様子を見る | ||
| 放 課 後 に 個 別 に 補 充 指 導 を す る | |||
| 佐賀県についての意見文を書く ①テーマを決め資料を集める ②意見文を部分ごとに書いていく ③テーマごとのミニ討論会をし反論の部分を書く ④意見文の残りの部分を書く ⑤書いたものを読み合う |
5 | ○例文の構成を参考に部分ごとに指導する ○テーマ別にミニ討論会をさせる ○討論会シートを活用させる →ミニ討論会でのメモ ○書き方のよいところを見つけさせる →相手を惹きつける表現の工夫 等 |
ミニ作文作品例 討論会シート(A児) 討論会シート(B児) |
| 評価について→ | 討論会シートへの記入状況やミニ作文用紙(項目ごとに書き分けるようにした原稿用紙)への叙述の様子を見る | ||
| 学習のまとめをする ①意見文を推敲する ②互いの意見文を読み話し合う ③意見文を生かす工夫を話し合う |
4 | ○全体の構成を見直させる →項目ごとに書いた作文の並べ変え 等 ○推敲の方法やポイントに気付かせる ○読んでもらうための工夫を話し合わせる →ポスターを描く感想カードを作る 等 |
ミニ作文全体(A児) ミニ作文全体(B児) 意見文(A児) 意見文(B児) |
| 評価について→ | 推敲については部分ごとに書き上げた作文を読み直している様子や修正箇所への書き込み相互評価の様子を見る 学習のまとめを補充指導や次の単元に生かすようにする |
||
| (1)本時の目標 | |
| ミニ討論会をし,自分とは異なる立場の意見を知り,それに対する反論を書くことができる。 | |
| 児童の学習のめあて |
| ミニ討論会をし,異なる立場の意見を生かして相手を納得させる反論を書こう。 |
| (2)本時の展開 |
| 学習活動 | 指導上の留意点 | 評価と指導 | ||||||||||||||||||||||
| 学習のめあてをつかむ。 テーマごとに賛成と反対に分かれミニ討論会をする。 自分とは異なる意見に対する反論の材料を見つける。 反論の部分を書く。 →ミニ作文(A児) →ミニ作文(B児) 本時の学習を振り返る。 |
討論会シートや前時に書いた文章を読ませ討論会で主張することを明らかにさせる。 ○ミニ討論会の目的が結論を導き出すことではなく多様なものの見方や考え方に気付くことを確認しておく。 ○討論会シートに相手の意見や気付きをメモさせる。 ○自分が伝えたい意見をはっきりさせる。 ○討論会シートの記述やメモ,討論会で感じたことや考えたことを生かして反論の材料を見つけさせる。 →A児の討論会シート →B児の討論会シート ○考えたことや感じたことも交えながら自分の意見を効果的に伝える工夫をさせる。 ○書き方のポイントや反論の部分の例文を掲示し参考にさせる。 ○振り返りカードに記入させ,次時の学習について知らせる。 |
|
||||||||||||||||||||||