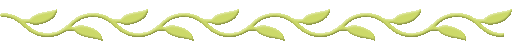
| 1 単元について | 2 単元の目標と評価規準 | 3 指導と評価の一体化 | 4 単元の指導計画 |
| 5 本時の展開 | ○ 学習指導案(PDF) | ○ 研究の実際TOPへ | ○ 6年生の実践へ |
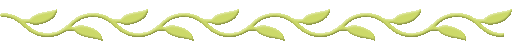
|
~「武雄のお気に入りの場所を紹介しよう」~
|
| 「紹介しよう『お気に入りの場所』」(東書3年上) |
(1) 「紹介の文章」の特色
| ○内容や用件を的確に他者に伝えるものであり,材料の整理や順序の工夫の学習に適している ○相手意識,目的意識が明確な文種である ○取材活動を通して,一人一人が「書く内容」をもつことができる ○低学年では生活文として扱われることが多い |
(2) 「紹介の文章」を学習する上でのねらいと指導上の留意点
① 段落の意味(内容のまとまり)について学ぶ
| ○イメージマップ | 取材の計画を立てさせる際に活用する 題材の整理やまとまりを考えさせる際に活用する |
| ○ミニ作文 | 取材した内容を項目ごとにミニ作文として書くことで内容のまとまりを意識させるとともに,作文の構成要素を一つ一つ確実に書き上げさせることができる |
② 文章構成の工夫について学ぶ
| ○教師作成の例文 | 2通りの例文(同じ場所を紹介しているが,紹介するものの順序が異なる2つの文)を比較させる |
| ○ミニ作文 | ミニ作文にすることで,出来上がりを具体的にイメージしながら文章の組立てを考えさせることができる |
③ 児童にとって必然性のある学習課題
| ○教師作成の例文 | 2通りの例文(施設の全体を紹介している文・その場所の一つ一つについて紹介している文)を比較させる |
| ○他校との交流 | 「他校の友達に武雄のよさを伝えよう」というテーマのもとに学習を進める →総合的な学習の時間との関連を図り,他校の友達へその場所のよさをうまく伝えるために,内容の並べ方を工夫するような場を設ける |
【目標】
| ○紹介したい場所のよさや楽しさ等が読み手に伝わるように,文章の構成を考えることができる。 |
| ○比喩や擬態語などの様子を表す言葉を使って,文章を書くことができる。 |
【評価規準】
| ア | 国語への 関心・意欲・態度 |
○紹介したい場所のよさや楽しさについて調べたり,相手に分かりやすい「紹介の文章」を書こうとしたりしている。 |
| イ | 書く能力 | ○自分の伝えたいことがよく分かるように,段落の並べ方を工夫して「紹介の文章」を書いている。 |
| ウ | 言語についての知識・理解・技能 | ○紹介したい場所のよさや楽しさを表現することばを工夫して文を書いている。 ○句読点を適切に打ち,段落のはじめなどの必要な箇所は改行して書いている。 |
(1) 学習モデル(例文)を作成し,児童に提示する
| ○単元を通して児童に身に付けさせたい能力や態度の具体化につながる。 →単元の指導目標,評価規準の明確化 |
| ○叙述や構成の指導過程における留意点を盛り込むことで,指導内容を具現化できる。 →各過程における評価の存り方ときめ細やかな指導に関する計画 |
| ○児童にとっては,学習モデル(例文)が示されることで,具体的な学習のゴールをイメージしやすい。また,自己評価・相互評価をする際の参考ともなり得る。 |
(2) 叙述の過程においては,項目ごとに書き上げて(ミニ作文)いくようにする
| ○1時間ごと,1活動単位ごとの指導内容をより焦点化できる |
| ○1単位時間での指導や評価がしやすい |
| ○児童にとっては,各時間・各活動における学習目標の明確化につながる |
| 学 習 活 動 | 時間 | 指 導 上 の 留 意 点 | 資料等 |
| 学習課題をつかむ ①「紹介の文章」の内容について学ぶ ②イメージマップをかく ③取材計画を立てる |
2 | ○2つの「紹介の文章」を提示する →それぞれの例文のよさを見つけさせる ○どちらのタイプを参考にして書くか考えさせる ○イメージマップを基に取材計画を立てさせる |
例文1 イメージマップ |
| 評価について→ | 授業中の話し合いの様子や,イメージマップの内容,自己評価表の記述内容などから,「紹介の文章」についての理解がどれくらいなのかや学習への関心・意欲の度合い,取材活動の見通しができているかどうかについて見る | ||
| 計 画 を も と に 取 材 に 出 か け る ( 総 合 的 な 学 習 の 時 間 と の 連 携 ) |
|||
| 「紹介の文章」を書く ①ミニ作文を書く ②文章の組立てを考える ③書き出しや結びの部分を考える |
7 | ○一項目を一枚のワークシートに書かせる →ワークには付箋紙で見出しを付けさせる ○2つの例文を提示する →同じ場所で紹介の順序が異なるもの ○実際に内容を読みながら組立てを考えさせる ○ミニ作文をつなげて書き上げさせる →段落をつなぐことば等を書き加えさせる |
ミニ作文作品例 丸山公園(A児) 水げん地公園(B児) |
| 評価について→ | ミニ作文用紙への叙述の様子や相手に分かりやすいような組立ての工夫(段落の並べ方の工夫)ができているかどうか,段落のつなげ方は適切かどうかについて見る | ||
| 学習のまとめをする ①作品の発表会をする ②単元の学習をふり返る |
1 | ○書き方のよいところを見つけさせる →紹介する場所のよさや様子 →相手を惹きつける表現の工夫 等 |
児童の作品 児童の感想 |
| 評価について→ | 作品のよさや工夫している点に気付くことができているかどうかを見る 学習のまとめを補充指導や次の単元に生かすようにする |
||
| (1)本時の目標 | |
| 紹介したい場所のよさがよく伝わるように,段落の並べ方を工夫することができる。 | |
| 児童の学習のめあて |
| 紹介したい場所のよさがよく伝わるように,段落の並べ方を工夫しよう。 |
| (2)本時の展開 |
| 学習活動 | 指導上の留意点 | 評価と指導 | ||||||||||||||||||
| 学習のめあてをつかむ。 例文2をもとに、文章構成を考える手順を知る。 自分の作文の組立て(段落の並べ方)を見直す。 本時の学習を振り返り,グループや全体で感想を述べ合う。 |
○例文が,どのような構成になっているか考えさせ,そのよさに気付かせる。(一次で提示した例文の段落を入れ替えて書き直したものを提示する) ○例文の書き手が,どのような手順で構成を考えたかを話し合わせることで,活動の見通しをもたせる。 ○3つの例文を比べさせ,書き手の意図や工夫に気付かせる。 ○例文の書き手の工夫を参考にして,ミニ作文をつなげるために必要なことを確認する。 ○並列に並べられる段落,順序を考えた方がいい段落を整理して,構成を考えるよう助言する。 ○決めた順序に沿って,前時までに書いたミニ作文を並べ,書き加えたり削除したりした方がいい箇所はないか考えさせる。 → 児童の変容 ○少人数で構想メモを見せ合う相互交流を行った後に,振り返りの活動にはいるようにする。→ 自己評価表 |
|
||||||||||||||||||