「児童生徒一人一人が居心地のよさを感じる学級集団づくり」について提案します! |
| 現在の位置: 2 研究の実際 (4) 対応策の検討 イ 対応策の立て方 | |||||
| イ 対応策の立て方 | |||||
| 具体的な対応策を立てていきましょう | |||||
実態把握のためのアンケート(「Q-U」や「がばいシート」の)実施後に、具体的な対応策を計画していきます。 |
|||||
| 対応策を立てる上で一番大事になることは、学級の状態をしっかり把握して継続できる活動を選ぶことです。 | |||||
| ① SGE、SST、GWTを取り入れた対応策 | |||||
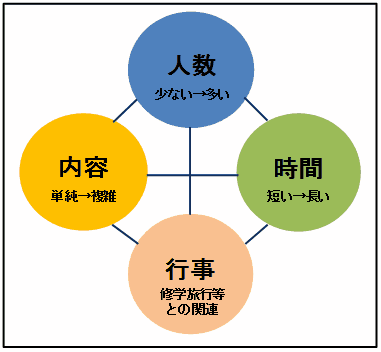 |
SGE、SST、GWTを取り入れた対応策を立てていくときには、人数・時間・内容・行事等を考慮する必要があります(図4-2)。学級の児童生徒の様子に応じて、内容やグルーピングを考えます。「まずは、ペアでできるものから」「短時間でできるものから」「非言語的な内容のものから」「行事前なのでグループで協力してできるものを」など、4つの要素を考えながら授業(SGE・SST・GWT)の順番や組合せを考えていきます。 |
||||
| 図4-2 SGE、SST、GWTを取り入れるときの視点 | |||||
| <SGE(構成的グループエンカウンター)とは> | |||||
| SGEは、2つの効果があります。1つ目は、「あたたかな人間関係をつくる」ことができます。児童生徒の人間関係が援助的になり、いじめや不登校などの問題を防止して、学級の支持的風土づくりや受容的な雰囲気の学級づくりに役立ちます。2つ目は「自己発見を促す」ことができます。児童生徒の自己理解や他者理解を促して、自尊感情を高めます。自分らしさに気付き、自分が大切な存在であるという感情を高める効果があります。 | |||||
| <SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは> | |||||
| ソーシャルスキルは、人付き合いを円滑に運ぶために必要な能力のことです。学習によって習得され、そのスキルを段階的に身に付けていきます。対人関係にかかわるルールの定着を図るときの、有効な手法でもあります。佐賀県教育センターでは、小・中・高等学校別の「12の基本スキル」の活動プログラムを提案しています。 | |||||
| <GWT(グループワークトレーニング)とは> | |||||
| GWTは、集団における自分の役割を学ぶことをねらいとしています。グループで課題を解決して、そのときのことを振り返ることで、友達と協力することの大切さやかかわり方について気付きを深めることができます。 | |||||
| 表4-1 SGE、SST、GWTを選ぶ視点 | |||||
実態把握と見立ての結果より |
||||
| 授業 | ○進め方・ねらい ◇教師が配慮すること |
授業内容(例) |
||
| ルールの確立が必要 | SGE |
○児童生徒が、互いが傷付くことのないコミュニケーションを目指して、基本的な聞く態度や話す態度の習得に焦点を当てます。また、誰でも安心して生活できる学級づくりを目指すために、集団のルールやマナー、許容的態度の習得にも焦点を当てます。 ◇教師はリーダーとして参加します。話すときはみんなに聞こえるように「大きな声ではっきりと話す」など、ルールを定着させる役割をします。 |
・質問ジャンケン ・他己紹介 ・二者択一 ・ビンゴ ・「?」と「!」 |
|
SST |
○児童生徒に、ソーシャルスキルを習得させることをねらいとします。学級の実態や発達の段階に応じて、「12の基本スキル」を相互に関連させながら取り組むことが望ましいです。 ◇教師は学級の実態を把握して、児童生徒が成功体験を繰り返すことができるようなスキルを選択する必要があります。 |
・「12の基本スキル」の展開案やワークシート等はこちら→(平成22・23年度プロジェクト研究) | ||
| リレーションの確立が必要 | SGE |
○児童生徒の活動では、楽しさを共有できるような内容を取り入れて、明るく自由な雰囲気をつくります。許容的な態度やさりげない励まし合い、集団への能動的参加など、肯定的なかかわりができることを目指します。 ◇教師が自己開示したり、一緒に楽しもうとする姿勢を見せたりします。 |
・サイコロトーキング ・カムオン ・アドジャン ・なんでもバスケット ・聖徳太子ゲーム |
|
GWT |
○児童生徒同士が、協力することのよさや友達のよさや自分のよさに気付くように仕組みます。内容やルールなどは児童生徒が理解できるように、丁寧に説明します。 ◇児童生徒の状況や目的に合わせて実施する活動を選ぶようにします。活動に慣れていないときは、ゲーム性が高く、ルールが簡単な内容のものから始めます。 |
・まちがいさがし(協力実習) ・お祭りにいこう(情報カード実習) |
||
| ※同じエクササイズでも教師のねらいやフィードバックの方法によって、ルールを重視したエクササイズになったり、リレーションを重視したエクササイズになったりします。 | ||||
| ② その他の対応策 | |||||||
| その他の対応策には、学校生活における児童生徒の様々な場面において、集団に対する対応策と個に対する対応策が考えられます。対応策の内容によって実施する期間は変わってきますが、継続できる内容を選択することが大切です。実践後は効果を検討して、学級の実態に応じて、修正等を加えていきます(表4-2)。(『Q-Uによる学級経営スーパーバイズ・ガイド』参考) | |||||||
| 表4-2 ルールやリレーションを重視した対応策の例 | |||||||
| (対応策の例) ルールを重視した対応策…【ル】 リレーションを重視した対応策…【リ】 | 【ル】 |
【リ】 |
| ① 学年の連携の仕方(TTや合同授業等、学級担任の役割の明確化) | ||
・4月の学級開きの際に、決めておかなければいけないルールや約束事(給食の準備の仕方、掃除の仕方など)づくりについてアイデアを出し合います。 |
○ |
|
| ・ルールや約束事については、学年の教師間で共通理解を図ります。 | ○ |
|
| ・学年内で支援を必要とする児童生徒への対応(教室以外の居場所の確保、支援する教師の確認等)を統一します。 | ○ |
|
| ・朝の会や帰りの会、授業などを参観し合い、教師間の指導のよいところを取り入れます。 | ○ |
○ |
| ② 保護者とのかかわりづくり | ||
| ・学級懇談会や学級通信などを利用して、児童生徒の様子(よいところ)を知らせたり、学級担任としての願いや学級経営方針を伝えたりします。 | ○ |
○ |
| ・児童生徒が欠席したときには電話を掛けて様子を尋ねます。できれば、最近の児童生徒の頑張りなどを短時間で伝えます。 | ○ |
|
| ・保護者と外部機関との共通理解や連携を図り、学校や家庭での対応の仕方を確認し合います。 | ○ |
|
| ③ 学級担任の対児童生徒へのリーダーシップの取り方のポイント | ||
| ・児童生徒に、「すぐに、まめに、さりげなく」声を掛けます。 | ○ |
|
| ・どんなことでも、できたらほめるという姿勢で児童生徒に接します。 | ○ |
○ |
| ・児童生徒のよい行動を見掛けたら、その場ですぐにほめます。 | ○ |
○ |
| ・日頃から、児童生徒の話を十分に聴くように心掛けます。 | ○ |
|
| ・必要最低限のルールや約束事を児童生徒と決めます。決めたら、双方で守るようにします。 | ○
|
|
| ④ 教科・領域での進め方のポイント | ||
| ・授業中の学習のルールを確認させます。 | ○ |
|
| ・指示や活動のルールを細かく具体的に示して、教師がモデリングを見せて取り組ませます。 | ○ |
|
| ・一斉指導の時間を減らして、ペア学習やグループ学習の時間を多く取り入れます。 | ○ |
○ |
| ・児童生徒の考えを認めて、称賛し自信をもたせます。 | ○ |
|
| ・ノートや学習プリント等に、教師からの温かいコメントを記入します。 | ○ |
|
| ⑤ 学級活動の展開のポイント(朝・帰りの会も含めて) | ||
| ・朝の読書タイムを取り入れて、学級担任も一緒に本を読みます。 | ○ |
|
| ・登校する児童生徒を教室で迎えるように心掛けて、挨拶と一言程度の会話を交わします。 | ○ |
|
| ・友達の「よいところ見付け」を行い、朝の会や帰りの会を利用してカードに書かせて、教室に掲示したり発表させたりします。 | ○ |
|
| ・朝の会などでショートエクササイズなど、みんなで楽しむことができる活動を取り入れます。 | ○ |
|
| ・毎週金曜日に、「今週のMVP」を生活班の中から一人選ぶ時間を設定します。 | ○ |
|
| ・学校行事などを利用して実行委員会を組織して、学級の自治的な力を育成します。 | ○ |
○ |
| ・「学級の中で困っていること」を無記名で書かせて児童生徒に提示し、学級で守ることができるルールを3つ決めます。 | ○ |
|
| ・ルールを見直して、短期間で達成することができそうな内容に取り組みます。 | ○ |
|
| ⑥ 給食・掃除時間の展開のポイント | ||
| ・グループで給食を食べるようにしたり、学級担任も曜日ごとにグループを変えたりして、児童生徒と一緒に給食を食べます。 | ○ |
|
| ・掃除当番を細かく分担して、誰がどこを掃除するのかを明確にして、役割への責任をもたせます。 | ○ |
|
| ・掃除の時間は担当場所の掃除の取り組み方を確認しながら、学級担任も一緒に掃除をします。 | ○ |
|
| ⑦ 時間外(休み時間・放課後)に必要な対応(個別面接・補習授業等) | ||
| ・学級全体で遊ぶ時間を設定し、全員が楽しむこができる遊びを企画させて、教師も参加します。 | ○ |
|
| ・気になる児童生徒については、随時個別に面談を実施します。 | ○ |
|
| ・教育相談週間を設けて、学級全ての児童生徒と面談をします。 | ○ |
|
| ⑧ 学級担任のサポートの在り方、作戦会議の計画 | ||
| ・気になる児童生徒には学級担任一人で対応するのではなく、学校としての支援体制をつくりって対応します。また、教師間で定期的に情報交換を行ったり、支援策について話し合ったりする時間を設けます。 | ○ | ○ |
| ・級外の教師は、学級担任の気付いていない学級のよさや学級担任の頑張りを学級担任に伝えます。 | ○ |
|
| ・学級で使ったプリント類や教具を、学年で共有します。 | ○ |
|
|
|
||||
|
||||