「児童生徒一人一人が居心地のよさを感じる学級集団づくり」について提案します! |
| 現在の位置: 2 研究の実際 (5) 対応策の実施 ウ 中学校(学年)における実践 (ア) 生徒理解 | |||||||||
| ウ 中学校(学年)における実践 | |||||||||
| 認められているという思いを高めることを目指した学年での取組 | |||||||||
| (ア) 生徒理解 | |||||||
| 1 本事例の学年の様子(3年生、6月上旬) | |||||||
本校は、各学年3〜4学級の中規模校です。 本学年は、入学時に友人間でのトラブルが発生したため、特に人間関係に配慮して学級編成を行っています。学年が上がるごとに徐々にトラブルも少なくなり、友人関係でトラブルを抱えていた生徒にも、学級の中で一緒に話をしたり活動したりする友人ができて、安心して過ごすことができるようになりました。教師の指示があれば、何事にも素直に取り組む生徒が多い学年ですが、進んで活動することには消極的な面が見られます。また、学年が変わった4月当初の緊張感が少しずつ低くくなり、当番活動が十分にできなかったり、移動教室の時間を守ることができなかったりする生徒が見られるようになっています。 生徒一人一人が居心地のよさを感じる学級集団づくりのために、生徒が友人や教師に認められているという思いを高めることを目指します。 |
|||||||
| 2 実践前のアンケート (「がばいシート」) 結果(5月下旬) | |||||||||
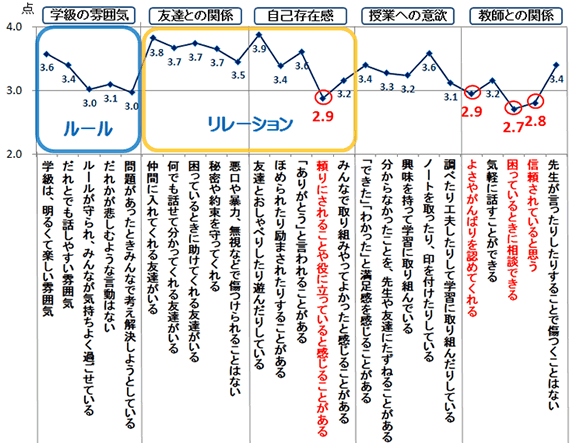 |
|||||||||
図5−ウ−1 実践前のアンケート結果(項目別・学年) |
|||||||||
| 図5−ウ−1のグラフは、「がばいシート」の全ての質問(25項目)について、学年で合計したものの平均値です。好ましい状態であるほど数値が高くなっています。(満点は4点) | |||||||||
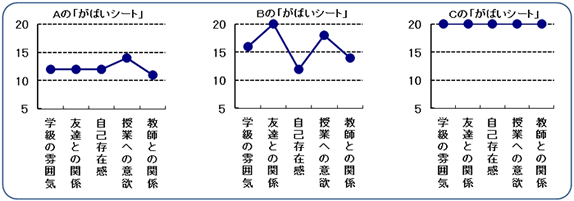 |
|||||||||
図5−ウ−2 実践前のアンケート結果(観点別・抽出した生徒) |
|||||||||
| 図5−ウ−2は、アンケート結果と学年の職員の日常観察を併せた結果、抽出した生徒のグラフです。縦軸の数値は、図5−ウ−1で示した質問項目への回答状況を、観点別に合計したものです。好ましい状態であるほど数値が高く、満点は各観点とも20点(5項目×4点)です。 | |||||||||
| 3 本事例の「学級把握シート」 | |||||||||
| 本事例の「学級把握シート」は、個人情報が含まれているためプライバシー保護の観点から省略します。 | |||||||||
| →「学級把握シート」についてはこちら | |||||||||
| 4 チームによる実態把握(研究委員、学級担任3名、副担任2名、学年主任、教育相談担当) | |||||||||
| 【集団について】 | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
学年がこのような状態になった要因として考えられること |
|||||||||
| ・3年生に進級してからの新しい人間関係は、教師と生徒との関係や同じ係などの役割での交流に基づくものであり、以前から仲のよかった友人以外との内面的な交流の場が少なかったために、友人関係が広がっていないのではないかと考えられる。 ・教師は、活動の見本を示して取り組み方を教えたり一緒に活動したりして、教師主導で学級や学年の活動を行う場面が多かった。また、リーダー以外の生徒は、リーダーや教師の指示を待って行動することが多いことから、生徒が友人や先生から認められているという思いを感じにくかったのではないかと考えられる。 |
|||||||||
| 【個人について】 |
|
|
||||||||
|
|
||||||||
抽出した生徒がこのような状態になった要因として考えられること |
|||||||||
| ・Aは、友人関係にトラブルを抱えているのではないかと考えられる。 ・Bは、学級での自己存在感を感じることができず、教師からの評価も低くなっていると思っているのではないかと考えられる。 ・Cは、アンケートに真剣に取り組む気持ちをもつことができなかったのではないかと考えられる。 |
|||||||||
|
|
||||
|
||||