「児童生徒一人一人が居心地のよさを感じる学級集団づくり」について提案します! |
| 現在の位置: サイトマップ ⇒ 2 研究の実際 ⇒ (5) 具体的な対応 ⇒ ア 小学校(中学年)における実践 | |||||||||
| ア 小学校(中学年)における実践 | |||||||||
| 学級全体にリレーションを広げる単学級での取組 | |||||||
| 対象:4年生35名 | |||||||
| 1 本事例の学級の様子 | |||||||
| 各学年1学級の小規模校である。地元の幼稚園や保育園からの入学が多い。 本学級の男子は明るく元気で、休み時間はほぼ全員で遊ぶことが多い。女子は学校生活において、決められたことを守り、落ち着いて生活しようとする児童が多く見られる。一方、男子の一部には意欲的に学校生活を送っているものの友達とのトラブルが多く見られたり、女子同士で仲の良いグループだけで過ごしがちになったりする傾向がある。今後、単学級で小学校生活の後半3年間を同じメンバーで過ごしていくに当たって、より一層、集団のまとまりや一体感、温かい雰囲気を育てることが課題だと考える。 |
|||||||
| 2 実践前のアンケート (「Q-U」) 結果(5月中旬) | |||||||
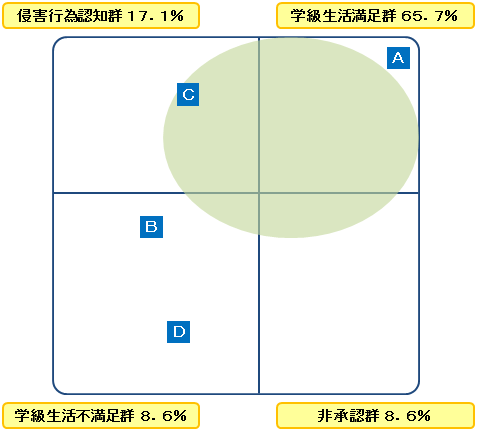 |
|||||||
| 3 実態把握 | |||||||
| (1) アンケート(「Q-U」)結果より 【集団について】 ・学級の65.7%の児童が学級生活満足群に位置しており、ルールとリレーションがある程度確立していると言える。 ・侵害行為認知群の割合が17.1%と4群の中で2番目に高く、安心して友達同士でかかわることができているとは言えない。 ・学級生活不満足群の児童は、低学年の頃とほぼ同じ位置にある。 【個人について】 ・Aは、学級生活満足群の一番右上に位置している。全ての質問項目で適応していると判断される回答である。 ・Bは、学級生活不満足群に位置している。学習や友達関係に関する意欲は高いが、被侵害得点が高く、嫌がらせを受けていると感じている。この傾向は、低学年の頃から続いている。 ・Cは、侵害行為認知群に位置している。承認得点は高いものの嫌なことを言われたり、されたりすることが「よくある」と答えている。低学年の頃は、学級生活満足群に位置していた。 ・Dは、学級生活不満足群に位置しているが、友達から嫌がらせを受けているとは感じていない。学習意欲や学級を肯定的に捉える質問の得点が低く、学校生活全般に関する意欲が低い。 |
(2) 担任の日常観察より 【集団について】 ・特定の児童に限らず、学級の誰かが活動中に失敗すると笑うことがあり、温かい雰囲気を感じられないことがある。 ・学習中の姿勢が悪く、人の話を聞くことが難しい。 ・男子に比べて、女子のまとまりが感じられない。 【個人について】 ・Aは、友達と進んでかかわることは少なく、休み時間は一人で図書館に行き、図鑑等の本を借りて、読書をして過ごすことが多い。教師の指示が通りにくく、行動が遅れることがある。 →アンケート結果と担任の日常観察が一致しない児童 ・Bは、休み時間は友達と一緒に外で遊んでいる。授業中は、積極的に発表する。Cとは低学年からトラブルになることが多く、担任に訴えてくることがあった。 → アンケート結果と担任の日常観察が一致しない児童 ・Cは、リーダー的存在でたくさんの友達を誘って遊ぶことが多い。運動能力が高く、友達からは認められているようだ。学習には積極的に参加し発言するが、理解するのに時間がかかり自信を失いかけているようだ。整理整頓に課題があり、担任が声を掛けることが多い。Bとトラブルがあっても担任に訴えることはない。 →学級で影響力の大きい児童 ・Dは、放課後に近所の友達と遊ぶことが多いが、学校では自分の気持ちを上手く表現することが苦手で、一人になることがある。 →態度や行動が気になる児童 |
![]()
| (3) 要因として考えられること 【集団について】 ・単学級であるため学級対抗での活動がなく、団結したり、協力したりする場面が少なく学級の一体感が得られにくかったことが考えられる。また、女子のまとまりのなさについては、単学級のため人間関係が固定化して、児童同士の交流がグループ内に留まっていることも考えられる。 ・侵害行為認知群の割合が高いことについては、友達の失敗を笑うことや話をじっくり聞くことができないことが原因として考えられる。また、友達とのかかわりにおけるルールが十分に確立されていないことも考えられる。 ・学級生活不満足群の児童は、単学級で人間関係が固定化しているために低学年の頃と同じ群に位置していると考えられる。 【個人について】 ・Aは、問題の意味が理解できていないことや評価を気にし過ぎていることが考えられるため、今後も観察が必要である。 ・Bは、不安傾向が強いことが考えられる。 ・Cは、学年が進むに連れ、人間関係の変化や学習面への不安が影響していることが考えられる。 ・Dは、承認得点が低いことや「クラスにいたくない」、「独りぼっちでいる」という回答から自己肯定感が低いことが考えられる。 |
| 4 対応策 |
| (1) 方針 |
| 【集団について】 「Q-U」の結果から、リレーションがグループ内に留まっていることが考えられるため、リレーションを学級全体に広げる取組を優先して行う。まず、協力して取り組むグループワークトレーニング(以下、GWT)を行い、生活班の友達にリレーションを広げていく。次に、構成的グループエンカウンター(以下、SGE)で生活班や学級全員で協力して取り組むエクササイズを取り入れて、学級全体にリレーションを広げていく。担任は全員に役割を与えて、学級全体で取り組み、達成感や一体感を味わうことができるような授業の展開や行事への参加の仕方を考える。 また、ルールの確立に向けた取組も行う。ソーシャルスキルトレーニング(以下、SGE)の授業を行い、上手な聴き方やあたたかい言葉かけ等のスキルを高め、友達とのかかわりにおけるルールを共有していきたい。 |
| 〈実践授業内容の選択理由〉 実践① GWT 「お誕生日おめでとう」 グループで協力してできる間違い探し「お誕生日おめでとう」を行う。間違い探しという簡単な活動で、一人ずつ交代で間違いを探しに行くため、作戦を立てたり、自分の考えを伝えたりするなど、コミュニケーションの場が考えられる。 実践② SST 「あいさつ名人になろう」 人とのかかわりの基本であるあいさつのスキルから取り組む。ソーシャルスキルトレーニングのアンケート及び集計ツール(佐賀県教育センター平成22・23年度プロジェクト小・中・高等学校教育相談研究委員会)を使って、あいさつのスキルに関しての実態調査を行ったところ、8割以上の児童が「誰にでも、自分から、笑顔であいさつしている」または「大体している」と答えている。このことから、あいさつのモデルになる児童が多く存在していると言える。また、練習の仕方が簡単で、初めてのソーシャルスキルトレーニングの授業としても適当であり、ソーシャルスキルトレーニングの授業の進め方に慣れることもねらいとする。 実践③ SST 「友達がうれしくなるような話の聴き方をしよう」 担任が問題と感じていることの1つに話を聴くことが難しいことがあった。「アンケート」からは「話をしている人を見て、うなずきながら、最後まで聴く」ことに対して児童の8割以上「している」「大体している」と答えているが、担任は5割以上ができていないと答え、児童と担任の聴くことに対してのギャップがある。このことから担任と児童、または児童同士の関係づくりの基本スキルの1つである「上手な聴き方」のスキルに取り組む。 実践④ SGE 「クリスマスツリー」 体育大会という学級全体で取り組む行事を終えたこの時期に、より一層学級のまとまりを高めるために、児童全員で1つのことに取り組むエクササイズが必要だと考えた。「クリスマスツリー」は、跳び箱の1段目に6、7人のグループ全員が体を密着させて乗るエクササイズである。高学年になる前に、男女関係なく体全体でコミュニケーションを図ることで、心理的な距離も縮まるのではないかと考える。また、学級全員で1枚のマットの上に乗るエクササイズも行うことで、学級全体の一体感を高めたい。 実践⑤ SST 「あたたかい言葉かけをしよう」 担任が問題と感じていることの1つに、友達の失敗を笑うことがあり、あたたかい雰囲気が感じられないという点があった。「アンケート」からは、「ほめる言葉や励ます言葉、心配する言葉をかける」ことは児童の8割以上が「している」「大体している」と答えている。このことから、あたたかい言葉かけについては理解しているものの、十分に適切な場でできていないのではないかと考える。ソーシャルスキルトレーニングの授業で「あたたかい言葉かけ」の場面を意図的に設定し、練習することで、実際の生活でより一層「あたたかい言葉かけ」ができるようにしたい。 |
| 【個人について】 ・Aに指示が伝わるように、座席を前に置く。また、全体へ指示した後、理解できていないようであれば、全体に気付かれないように、さりげなく個別に指示をする。友達とのかかわり方については、観察や他の職員との情報交換を心掛ける。 ・ Bと友達がトラブルになった場合は、その時の状況を本人や他の児童から聞き取り、今後どのような言動を取ればよいのかを伝える。また、休み時間や授業中のグループ活動の様子の観察を心掛ける。 ・ Cには、授業中の机間指導を心掛け、学習への積極的な姿勢やできたことを褒め自信をもたせる。友達とのかかわり方については観察を心掛け、よいかかわり方や発言があった場合は褒めるようにする。 ・ Dには授業中や休み時間に声を掛け、教師との信頼関係を築くようにする。 観察や他の職員との情報交換を心掛ける。 |
| (2) 具体的な対応 |
時期 |
|
ねらい |
展開 |
振り返りシート等 |
担任と
連携した取組 |
|
| 5月 | 第1回「Q-U」実施 第1回「Q-U」を受けての学級集団や個人の実態把握及び担任との事前打合せ 第1回「Q-U」の事例検討会 第1回「Q-U」を受けての実践計画作成 |
|||||
| 7月 実践① |
GWT 「お誕生日おめでとう」 (間違い探し) |
・グループで協力して間違い探しをすることで、互いに認め合う大切さに気付く。 | ・Aの様子を観察したり、他の職員との情報交換をしたりする。 ・BとCの様子を観察する。トラブルが起きた場合は双方から事情を聴き、適切な行動を一緒に考える。 ・Dには授業中や休み時間に声を掛け、教師との信頼関係を築く。 ・総合的な学習の時間の「お年寄り訪問」の活動で、全員に役割を設け、全員で取り組み、一体感をもてるような展開にする。 |
|||
| 9月 実践② |
SST 「あいさつ名人になろう」 |
・あいさつのポイントを理解する。 ・ソーシャルスキルトレーニングの学習の進め方に慣れる。 |
||||
| 9月 実践③ |
SST 「友達がうれしくなるような話のきき方をしよう」 |
・上手な聴き方の意義や大切さを理解し、基本的なかかわりのスキルを高める。 | ||||
| 10月 実践④ |
SGE 「クリスマスツリー」 |
・力を合わせると成功するという体験をすることで、仲間への信頼感や団結力を高める。 | ||||
| 10月 実践⑤ |
SST 「あたたかい言葉かけをしよう」 |
・あたたかい言葉かけの意義や大切さを理解し、リレーションを発展させるための共感的なスキルを高める。 | ||||
| 11月 | 第2回「Q-U」実施 第2回「Q-U」を受けての学級集団や個人の実態把握及び考察 |
|||||
| 5 実践後のアンケート (「Q-U」) 結果(11月中旬) |
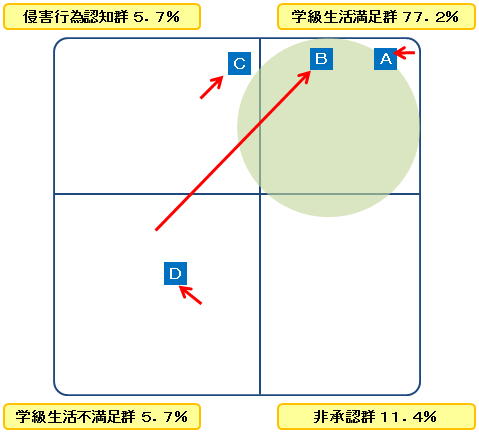 |
| 6 考察 |
| 【集団について】 ・「Q-U」のいごこちのよいクラスにするためのアンケートは、ルールに関する被侵害得点とリレーションに関する承認得点に大きく分けられるが、被侵害得点の平均が0.8ポイント、承認得点の平均が1.2ポイント改善されていた。このことからルールとリレーションの確立度が高まっていると言える。 ・「Q-U」のいごこちのよいクラスにするためのアンケートでは、学級生活満足群の割合が65.7%から77.2%に増加している。また、侵害行為認知群の割合が17.1%から5.7%に減少していることから、学級内のルールの確立が進み、嫌がらせを受けていると感じる被侵害得点が下がったと考える。ルールの確立に向けて、「あいさつ」「上手な聴き方」「あたたかい言葉かけ」のSSTの授業を行ったことで、友達とのかかわり方のスキルを共有し、ルールの確立を高めることにつながったと考える。(図1)担任の観察からも、授業中の話の聴き方がよくなったり、あたたかい言葉かけをする場面が見られたりして、トラブルや不安が少なくなってきたと感じられる。 |
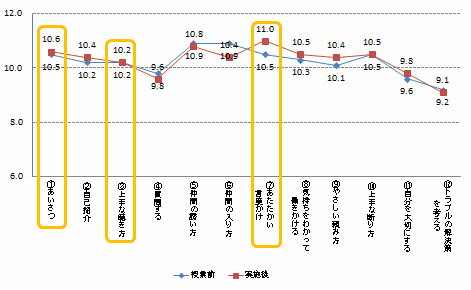 図1 ソーシャルスキルトレーニングの授業前と実施後の獲得状況の比較 (参考:平成22・23年度佐賀県教育センタープロジェクト研究 小・中・高等学校教育相談研究委員会) |
| ・リレーションの確立に向けて、協力する場面が必要なSGEやGWT、生活班で練習するSSTの授業を実践したことで、リレーションが学級全体へ広がってきていると考えられる。 ・「Q-U」のやる気のあるクラスをつくるためのアンケートでは、合計点が34点以上(36点満点)の児童が約半数を占め、1回目に比べ、男女共に平均点が上昇した(男子0.9ポイント、女子1.5ポイント)。ルールとリレーションの確立が、児童の学校生活意欲得点の変化にもつながっていると考えられる。 ・非承認群の割合が8.6%から11.8%と増加しており、1回目に学級生活満足群に位置していた児童3人が移行している。3人とも学習への取組において消極的だったり、落ち着きがなかったりして承認感を得られにくかったためだと考える。 ・やる気のあるクラスをつくるためのアンケートの友達関係と学級の雰囲気は0.5ポイント以上上昇していたが、学習への意欲は0.2ポイント下降していた。学年が上がるにつれ学習内容が難しくなってきたことが意欲にも影響していると考える。 |
| 【個人について】 〈Aについて〉 1回目の「Q-U」の結果では学級生活満足群に位置していたが、担任の日常観察と結果が一致せず、友達とのかかわりにおいて観察や他の職員との情報交換を心掛けた。周囲からは、Cが嫌がらせを受けていると思われる場面でも、C本人は何とも思わず、むしろ遊んでもらっていると感じていた。夏休みに、担任が通級指導教室の教師や保護者と連携を行い、2学期から通級指導教室で、Aが嫌なことをされたときに、どのような言動を取ればよいのかというスキル学習を行うことを確認した。授業では、GWTやSGEの活動を通して、友達と達成感や楽しさを共感できるようにした。2回目の結果では、「友達に嫌なことを言われる」という質問項目で、侵害得点が1つ増え、周囲と本人のかかわりにおける捉え方が徐々に一致しはじめてきたのではないかと思われる。 |
| 〈Bについて〉 学級生活不満足群から学級生活満足群に移行している。Cとのトラブルが減ったことが大きな原因だと考えられる。また、SSTによって友達とのかかわり方が共有されたことで、Cへのかかわり方が男子全体で共通にできはじめたことや、Cへの男子全体のかかわり方が少しずつ変わってきたことも原因と考えられる。 |
| 〈Cについて〉 同じ侵害行為認知群ではあるが、承認得点や侵害得点が少し改善された。SSTで「あたたかい言葉かけをしよう」の授業を行ったが、実際の生活場面でも「大丈夫よ」「ゆっくりしていいよ」等のあたたかい言葉を掛けて、友達を励ます場面が見られた。友達とのかかわり方のスキルが徐々に高まってきていると思われる。一方、昼休みに遊ぶ時は、友達に厳しい口調で自分の気持ちをぶつけており、数人の男子がその言葉を辛いと感じている。学習や生活面で友達関係の変化が見られてきたので、A本人が辛い思いをしないよう定期的に面談をしたり、友達への接し方で問題がある時には適切な言葉掛けを教えたりしていく必要がある。 |
| 〈Dについて〉 1回目同様、2回目の「Q-U」の結果でも学級生活不満足群に位置していた。SSTで学習したスキルを実際に使ったり、GWT、SGEをきっかけに友達関係が広がったりすることはなかったようだ。担任の声掛けで周りの友達はDに優しく接しているが、Dの印象には残っておらず、トラブルになった場面を強く覚えていることが担任との面談で分かった。友達とのかかわりや先生の声掛けを肯定的に受け止めることができないことが考えられる。今後も声掛けや観察を継続していく。また、保護者や他の職員との連携も必要である。 |
| →小学校中学年における実践の成果と課題はこちら |
|
|
||||
|
||||