|
授業づくりの考え方 〜ねらいの明確な授業を目指して〜
|
| |
新学習指導要領のねらいに対応し、生徒の実態に即した授業づくりを行うために、次の4点を考えています。具体的な実践を紹介しながら、明日の授業に役立つ提案をし、国語科授業の「あったらいいな!」を形にします。
|
(1) |
新学習指導要領の指導事項を意識した実態把握 |
| |
具体的な単元構想を行う基盤となるのは生徒のできるだけ詳細な実態把握であり、付けるべき力や育てたい言語能力に即して実態を把握する際の指標となるのは、新学習指導要領の指導事項です。単元を構想するためには、指導者は新学習指導要領の指導事項を意識した具体的な実態把握の方法をもっておく必要があります。
ここでは、実態把握の方法について提案します。 |
| |
〔実態把握の方法〕
|
| |
| アンケート |
学習する領域や文種に応じて、新学習指導
要領の指導事項に対応する項目でアンケート
を取ります。実態把握の手立てですが、内容を吟味すれば、これからの学習の内容を知らせる役割も果たすことができます。 |
| テストによる事前分析 |
○レディネステスト
※授業を行う前の時点で、これから行う学習内容に必要な力を生徒がどれくらい身に付けているのか把握するのに有効です。既に実施した定期テストや学力テスト等による分析と学習プリント等による分析が考えられます。身に付けさせたい力により着目したい場合には、学習プリントを事前に用い、その結果を分析する方法が考えられます。
※この時に大切なことは、その分析項目が新学習指導要領の指導事項に基づいていることです。 |
|
| 具体例はこちら! |
|
| (学習傾向が把握できます) |
| |
|
| (実態が把握できます) |
|
|
| |
★ここで把握するのは、目の前の生徒が現在の段階で、身に付けている力は何か、これから身に付けさせるべき力は何か、ということです。その目的に沿った実態把握の方法を選択することが大切です。 |
(2) |
学習内容の系統性を意識した指導のねらいの明確化と教材選択 |
| |
生徒に付けたい力が把握できたら、指導のねらいが明確になってきます。指導のねらいが明確になれば、必要な手立てやふさわしい教材が絞られてきます。そのようにして教材を選択すれば、より効果的な単元構想をすることができると考えます。また、そこで、より的確に生徒の力を伸ばすためには、既習の学習内容の活用を図ることと、次の学習内容への発展を意図した学習内容を位置付けることが必要になります。
ここでは、生徒の実態を踏まえ、学習内容の系統性を意識して指導のねらいの明確化を図ることについて提案します。
|
| |
〔単元の構想の進め方〕 |
| |
|
| |
詳しくはこちら 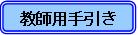 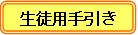 |
| |
★ここで明確にするのは、「目の前の生徒に、この授業でどのような力を付けたいか」ということです。そして生徒に確実に力を付けるためには、生徒と目標を共有し、生徒を主体的な学習者にするための学習活動を工夫することが必要となってきます。
★生徒と目標を共有し、生徒を主体的な学習者にするためには、指導のねらいが生徒にとっても学習のねらいとして共有されなければなりません。そのための手立てをもっておくことが必要です。 |
(3) |
言語活動の位置付け方の工夫と指導のポイント |
| |
生徒の実態を踏まえ、学習内容の系統性を意識した上で、指導のねらいが明確になったら、おのずと適切な学習活動が見えてきます。そのような学習活動において習得した知識や技能を、生徒の言語能力として定着させるために、活用を図る場として言語活動を位置付けます。
ここでは、習得した知識・技能の活用を図る場としての言語活動の位置付け方と位置付けた言語活動がより効果的に行われるための留意点について考え、提案します。
|
| |
〔言語活動の位置付け方〕 |
| |
|
| |
具体的な指導のポイントはこちら 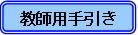 |
| |
★ここで留意するのは、言語活動が生徒の実態から導き出された指導のねらいを基盤として位置付けられていることです。また、位置付けた言語活動が効果的に行われるためには、指導のねらいとして具体化された知識・技能をどのように習得し、どのように伸ばすために位置付けたのかという流れと生徒の主体的な学習の流れををきちんと把握しなければなりません。
|
| |
〔位置付けた言語活動の例〕 |
| |
| 指導のねらい |
言語活動 |
目的や条件に応じて書くことができる。 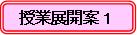 |
意見文を書いて新聞に投稿する。
【書くこと (2) イ】
|
構成や論理の展開を工夫して書くことができる。
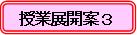 |
意見文を書いてコンクールに応募する。
【書くこと (2) イ】 |
論理の展開に即して文章を読むことができる。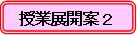 |
文章を読んで要旨をまとめ、内容について
自分の 意見を述べる
【読むこと (2) イ】 |
|
|
| |
★言語活動を位置付ける上で、思考力・判断力・表現力等を駆使し、伸ばすことができる活動であるか意識することも大切です。 |
(4) |
学習活動の振り返りと定着 |
| |
単元を通して、身に付けさせたい知識・技能を習得させ、効果に位置付けた言語活動の場においてそれらを活用させることで、思考力・判断力・表現力等の育成を図ることをねらっています。しかしながら、生徒自身が、自分にどのような知識・技能が身に付き、どのような思考力・判断力・表現力等が育ったのかということを自覚できなければ、その力が本当に定着したとはいえないと考えます。生徒にそれらを自覚させるためには、学習後の振り返りの活動を充実させることが必要と考えます。
ここでは、生徒が身に付けた知識・技能や育成が図られた思考力・判断力・表現力等を自覚することができるための効果的な方法について考え、提案します。 |
| |
〔振り返りの手立て〕 |
| |
| アンケート |
単元の初めに取ったアンケートと同じ項目で定着度を測ります。生徒にとっては身に付いた力についての認識を深める活動となります。 |
| 学習計画表 |
毎時間の振り返りと自己評価で力の定着を自覚します。教師にとっては形成的評価のよりどころとなります。 |
意見の交流
|
他者との交流で自分の意見を広げ、自分の考えをまとめることで身に付けた力の定着を図ります。 |
| テストや作品による分析 |
小テストや単元テストを行ったり、作品の分析をしたりすることを通して定着度を評価します。評価はフィードバックし、定着を図ります。 |
|
|
|