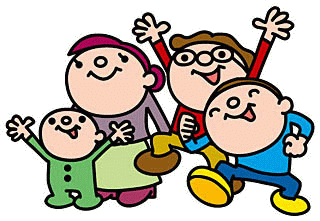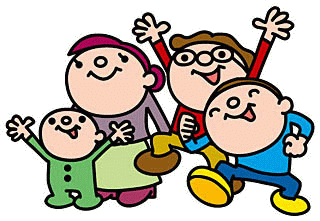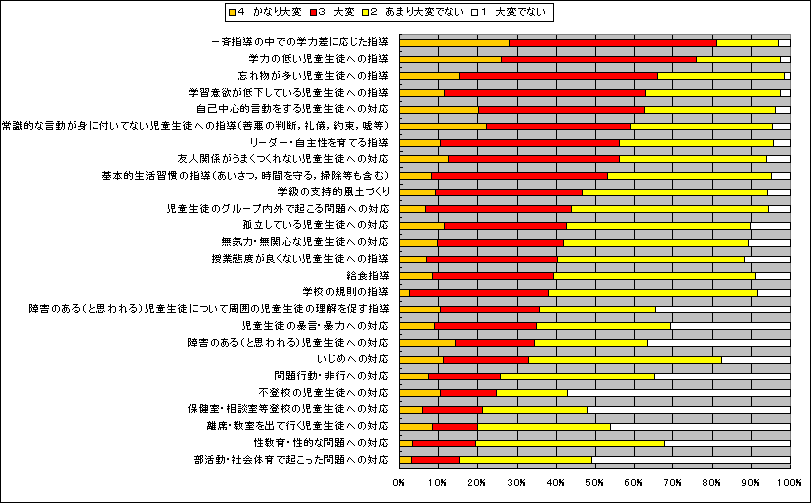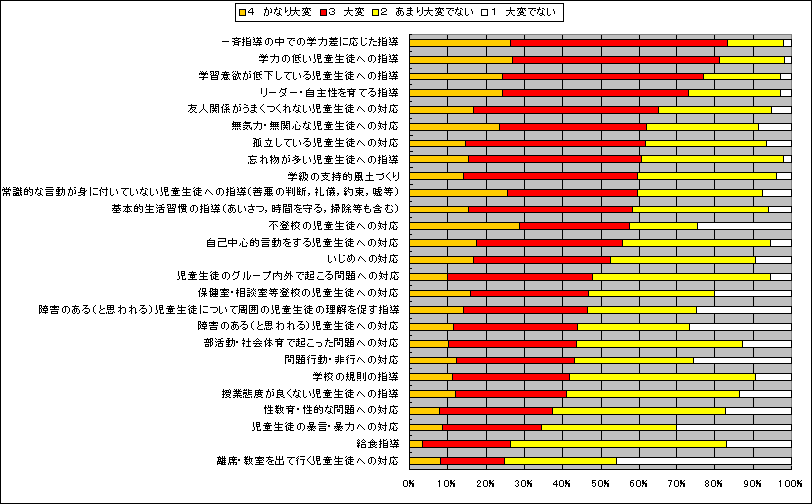| 指導上大変だと思うことのタイプ |
児童生徒への個別のかかわりが必要なこと
「保健室・相談室登校の児童生徒への対応」,「不登校の児童生徒への対応」,「部活動・社会体育で起こった問題への対応」,「問題行動・非行への対応」,「性教育・性的な問題への対応」「いじめへの対応」の6つが非常に関係が深いことが分かりました。これらは,学校や学級に足が向かない児童生徒への対応や教室外での対応についての大変さであり,その子が在籍するクラスやその家庭も含んで対応することが必要な場合もあるでしょう。
そこで,このことを【児童生徒への個別のかかわりが必要なこと】と名付けました。
これは,小学校の教員を対象にした調査の結果に見られたものです。 |
|
常識のある,規律正しい言動を促すための対応
「自己中心的言動をする児童生徒への対応」,「常識的な言動が身についていない児童生徒への指導」,「授業態度が良くない児童生徒への指導」,「基本的生活習慣の指導」,「学校の規則の指導」という5つの項目に高い関連性がありました。この5つは,生活面においても学習面においても決まりを守ることができなかったり,やるべきことができなかったりする児童生徒への対応ということができます。
そこで,このことを【常識のある,規律正しい言動を促すための対応】と名付けました。
中学校については,「児童生徒のグループ内外で起こる問題への対応」もこの5つに関係が深かったようです。 |
|
低学力・学力差への対応
「一斉指導の中での学力差に応じた指導」と「学力の低い児童生徒への指導」の2つの項目の間に強い関連性があるようです。この2つの項目は,調査3(指導上大変さを感じることについての調査)において,その指導に「大変だ」と回答した教師の数が最も多かったものです。
そこで,このことを【低学力・学力差への対応】と名付けました。
なお,小学校については「学習意欲が低下している児童生徒への指導」の項目もこの2つに関係が深かったようです。 |
|
友人づくりがうまく行かず孤立している児童生徒への対応
「孤立している児童生徒への対応」と「友人関係がうまくつくれない児童生徒への対応」の2つに強い関連があります。集団に自分から入ることを拒んでいる児童生徒や集団に入りたいのにうまく入ることができなかったり,入れてもらえなかったりする児童生徒の対応ということができます。
そこで,このことを【友人づくりがうまく行かず孤立している児童生徒への対応】と名付けました。 |
|
障害のある児童生徒やその周囲の児童生徒への対応
「障害のある(と思われる)児童生徒への対応」と「障害のある(と思われる)児童生徒について周囲の児童生徒の理解を促す指導」の2つに強い関連があります。
通常の学級にもLD,ADHD,高機能自閉症等の発達障害のある児童生徒をはじめ,知的な遅れや肢体不自由などいろいろなタイプの障害のある児童生徒が在籍している現状があります。このような児童生徒の個に応じた指導や,その周囲の児童生徒の理解を促す指導に対する大変さだと考えられます。
そこで,このことを【障害のある児童生徒やその周囲の児童生徒への対応】と名付けました。 |
|
不登校・教室外登校の生徒への対応
「不登校の児童生徒への対応」と「保健室・相談室等登校への対応」の2つに強い関連があります。これは,中学校の教員を対象にした調査の結果に見られたものです。
佐賀県でも小中学校合わせて約840人の不登校の児童生徒がいる(「平成17年度学校基本調査速報」より)という現実があり,このような児童生徒への対応や,登校していても教室に足を向けることの難しい児童生徒への対応の大変さだと考えられます。
そこで,このことを【不登校・教室外登校の生徒への対応】と名付けました。 |
|