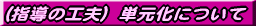○ねらいとする価値について
| 児童にとっての学級・学校とは,1日のうちの多くの時間を教師や友達と過ごす大切な場である。そして,授業をはじめ学校生活全体から学びとる社会性や豊かな心情は,将来へ向けての人格形成上の鍵となる重要な機能を果たしているといえるだろう。 上級生の仲間入りを果たすこの時期に,学級や学校の「よさ」に気付かせたり,そこに込められたたくさんの人々の思いに気付かせたりすることは,児童にとって自分の学校を「いい学校だなあ」「もっと大切にしたいなあ」という心情を育てる上で意義あることだと考え,本主題を設定した。 |
○児童の実態について
| 本学級の児童は,掃除を熱心に取り組んだり,元気よくあいさつをしたりすることができる。満足した学校生活をしている様子は,ほとんどの児童がアンケートで「学校はとても大切である」「学校は大切である」と答えていることからも分かる。
しかし,勉強の大切さや友達の大切さは意識しているものの,学校の「よさ」や「大切にしている人」について深く考えている児童は少ない。 そこで,この学習を通して,学校にかかわる「人」「もの」「伝統」には,それぞれ自分たちをよくしようとする共通の願いがあることに気付かせ,学校の一員であることの喜びを味わえる児童になってほしい。 |
○資料について
| 本単元は,3時間計画である。1時目では,学校の中にある「人」「もの」「伝統」という3つの視点からの写真を資料として活用する。それらを提示することで,それぞれがもつ「よさ」や,そこに込められた人々の思いに気付かせることができるであろう。また,資料となる写真が児童にとって身近なものであるため,生活へも広げやすいと考える。 2時目は,1時目終了から調べてきたことや本時で見付けた「よさ」を付箋紙に書かせ,校舎全景図・校内平面図に貼らせたものを資料とする。多くの児童の考えを1枚の図にまとめることで学校の中にある「よさ」やそこに込められた思いがいかに多いかということに気付かせることができるであろう。自分の意見や考えをワークシートに書き込むだけよりも,それを出し合い,図上に付箋紙が増えてくるのを視覚的にとらえさせることで,「自分たちの学校はよい学校だ」という思いをもたせることができるであろう。 3時目は,読み物資料(見えない名札 文溪堂)を使う。本資料は,公園で「仲間に入れてよ」と言ってきた他校の子どもと口論になり,やがて互いの学校の悪口を言い合う。それを見ていた卒業生にとがめられるという話である。実際に本校の近くにも,いくつかの学校があり,児童にとっては共感しやすい教材だと考える。この資料を使うことで,自分たちは学校の一員であるという所属意識を感じさせることができるであろう。 |
○指導の重点
| 本単元では,「三田川小の見えるよさ」→「三田川小の見えないよさ」→「三田川小の様々なよさと自分とのかかわり」という単元の構成をとる。 1時目では,学校の中にあるよさを「人」「もの」「伝統」の3つの視点から見付けさせていく。そして,「そのどれが一番すばらしいか」を考えさせていくことで,それぞれに込められた「学校をよくしたい」「子どもたちをよくしたい」という思いや願いに気付かせていく。 2時目では,本時までに調べてきた,学校の「よさ」や込められた「思い」を1枚の地図に書き込んでいく。さらに,学校を大切にしたいという思いをもった人は,学校の外にもたくさんいることを知り,その見えない思いにふれさせる。そこから,三田川小学校に込められた「学校を大切したい」という思いの多さに気付かせ,学校を大切にしようとする心情を育てる。 3時目では,みんなで完成させた「よさ」や「思い」の地図をもとに,「三田川小はいい学校だ」という思いをもたせたい。そこから,資料に入ることで,他の学校のよさにも気付かせるとともに,「自分は三田川小の大切な一員だ」という所属意識や自覚を育てたい。 |
3 単元のねらい
| 学校の中にある「よさ」や,そこに込められた「思い」を知ることで,「学校を大切にしたい」という心情を育てるとともに,その一員として行動することの大切さにも気付かせる。 |
4 指導計画