小学校国語科の授業びらきと年間を通した取り組み
国語科の授業びらきは、学級びらきの土台となるものです。主体的に学習に取り組む児童の姿を目標に、年間の見通しをもって継続的に取り組みを行いましょう。
授業びらきを行う際に気を付けておきたいポイントについて基本となるものを4つ示しています。
| ① 基本の約束 | ○ 明るく元気に「はい」と返事させる。 ○ 学習中の言葉遣いは敬体で話すようにさせる。 ○ 教科書やノートは決まった場所に置かせる。 ※利き手によっては、教科書とノートの位置を入れ替えた方が学習しやすい場合も あります。 |
| ② 話し方・聞き方 | ○ 聞き手の方を見ながら話させる。 ○ 話し手の方を見て聞かせる。 ○ 何を伝えたいのかを考えながら聞かせる。 ※始めのうちは、「からだごと…」や「目で聞く…」などと具体的な動きを教えるとよい でしょう。 |
| ③ 書き方 | ○ 丁寧に書かせる。 ※「丁寧な字」は児童の心構えによるものであり、誰もが達成できる書き方です。 ※先生自身の板書も丁寧な文字を書くように心掛けます。 |
| ④ 出会わせ方 | ○ 思わず学習したくなる出会いを考える。 ※いつも文字からの出会いではなく、挿絵やペープサート、クイズなど児童の意欲が 高まるような出会いを行う方法もあります。 |

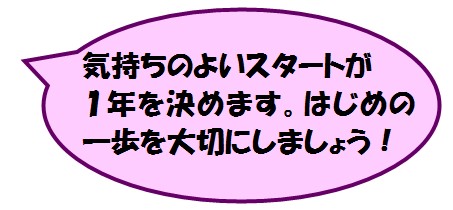
| 低学年 | 中学年 | 高学年 | |
| ひらがな表(1年生)・カタカナ表(2年生) | ローマ字表 | 古文・漢文 | |
| 既存の50音表を使います。学習したひらがな(カタカナ)を表中に書いたり貼ったりしながら、徐々にひらがな(カタカナ)表を完成させていくと児童の意欲も高まります。 |
ローマ字の学習は短期間で行われるため、定着しにくいものです。ローマ字表は年度当初から掲示して触れさせておくとよいでしょう。 | 教科書の教材に限らず、有名な古文や漢文を定期的に掲示することで、日本に伝わる伝統的な言語文化に触れさせておくとスムーズな学習が行えます。 | |
| ○ 言葉集め…ものの名前を表す言葉、動きを表す言葉、気持ちを表す言葉など、学習で触れた言葉や児童が日頃 使っている言葉を集めて、いつも見えるところに貼っておくとよいでしょう。 ○ 学習履歴…学習の中で学んだ大切なことは、「学習のあしあと」などの言葉を使って残しておくと、学習内容の確認 や振り返りに便利です。 |
|||
| ○ 漢字 | 漢字ノートについては、1年生:50字程度、2年生:84字程度、3・4年生:100~120字程度、5・6年生:120~150字程度が使いやすいようですが、児童の実態に応じて使い分けるとよいでしょう。 |
| ○ 音読 | ①正しく ②大きく ③はっきり を基本に、すらすら(間違えずに)などの視点も加えながら取り組ませるとよいでしょう。教科書教材を基本に音読に取り組ませますが、多くの文章に触れさせたい場合は、市販の音読用の資料や詩集など使ってもよいでしょう。高学年の場合は、古文や漢文の音読に挑戦させてみるのもよいでしょう。 【音読に役立つプリント】 |
| ○ 日記(作文) | 日記は連絡帳に書かせたり日記帳を準備して書かせたり、取り組み方はいろいろ考えられますが、児童の実態に応じて、3文日記など少ない分量から始めると比較的抵抗なく取り組むことができます。 【書き慣れることを目的としたプリント】 |
※以上の取り組みは一例です。自主学習と合わせて行ったり、毎日ではなく曜日を決めて行ったりするなど、児童の実態に応じて柔軟に取り入れ方を考えてみましょう。
※系統表はA4版で複数ページに分かれています。ダウンロードした後、A3版程度に拡大して貼り合わせてお使い下さい。
| 光村図書教材系統表【PDF】 | 東京書籍教材系統表【PDF】 |
 |
 |
| Copyright(C) 2011 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved. |
| 最終更新日:2011-03-30 |