自分自身の変化は見えにくいものです。しかし,第三者が,定期的に継続してかかわりながら,見取ったことをクライエントにフィードバックすることで,クライエント自身や周囲の変化を明らかにすることができます。(「この前できなかったことが今日はできてるね」といった声かけなど)
このようなかかわりは,先の見えない不安を抱えるクライエントにとって,解決に向かう足取りや,がんばっている自分の姿を確認できる大切な機会です。クライエントは小さな変化をいくつも積み重ねながら解決に向かっていきます。継続してかかわることは,その小さな変化を確認し,次の変化を促すために有効です。
うまくいったことの理由を探りましょう。
私たちは,子どもの失敗や過ち,つまり「うまくいかなかったこと」については,背景や原因を探り,動機や責任を追及し,どうあるべきかを教え諭そうと努めます。しかし,「うまくいったこと」の理由を改めて考えることはあまりないのではないでしょうか。
あることがうまくいったときの,具体的な状況を尋ねることは,次の成功へのヒントとなります。また,このことは,不安を抱え,自信をなくしているクライエントに安心感や希望を与えることにつながるようです。クライエントの多くは,成功体験について語り始めると,表情が明るくなり,声にも力が入るようになります。失敗体験の理由より,成功体験の理由の方が,解決策の構築に有効なようです。
![]() 事例に見るかかわり方のポイント
事例に見るかかわり方のポイント
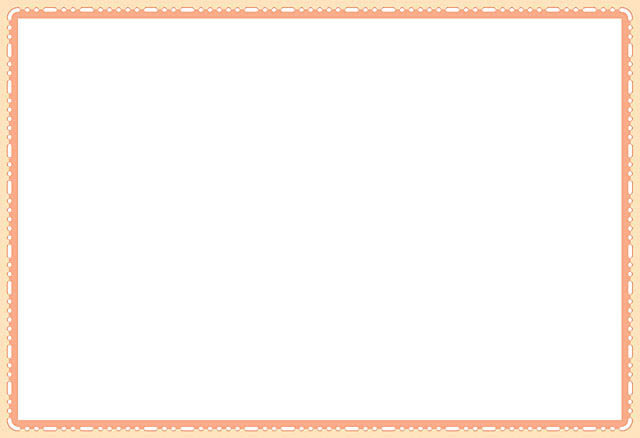
ここでは,ブリーフセラピーの技法を生かした相談事例を通して見えてきた,かかわり方のポイントを挙げています。これらを念頭に置いた子どもとのかかわりは,よりよい学校内カウンセリングにつながると考えられます。(「クライエント」は,子どもや保護者と考えてください。)
目標を設定し,解決イメージを膨らませましょう。
クライエントは,「学校へ行けるようになる。」「規則正しい生活ができるようになる。」などといった,長期的で大きく,漠然とした目標を掲げがちです。しかも,そのために,どのようなことが必要かという,具体的なビジョンを持ち合わせていないことが多いようです。「朝7時半に起きる。」「先生がうちに来たとき,玄関まで出てみる。」など,具体的で短期的,ちょっとがんばればできそうな目標を,クライエントと共に考え,設定することを大切にしたいものです。クライエントは,目標設定の過程で,解決へのイメージを膨らませていくようです。目標達成への取り組みが始まったら,折に触れ,称賛するのはもちろん,達成できなくても,目標を決めたことや取り組もうとしたことを認め,クライエントの自尊感情を高めたいものです。
今の自分の状態を把握させましょう。
不安や悩みが大きいと,自分自身の状態や周囲の状況を,冷静に把握するのが難しくなってしまうことが多いようです。そのため,自分がひどくだめな人間に思えたり,周囲の人から受け入れてもらっていないと感じたりしがちです。このような状況に置かれているクライエントにとっては,スケーリングクエスチョンなどで,自分を客観的に見ることが重要だと思われます。このことは,不安や悩みを自分自身から「離す」ことになり,クライエントは楽になるようです。自分の状態や変化,自分が置かれている状況などについて,少し離れて客観的に見るところから,解決への一歩が始まるケースは少なくありません。
クライエントへのちょっとした言葉かけで,自分のよさに気付かせることや,自分を再確認させることができます。そのためには,当たり前のことでも,今できていることを言葉で返してやることが大切です。(「保健室で過ごすことができたね。」「今日は昨日より長い時間,席に着いてるね。」など)
子どもの中に,リソース(資源)を見い出しましょう。
クライエント自身が困っていることや嫌だと思っていることは,見方を変えれば,いいところ,優れたところになり得ます。それが,解決策構築への資源となることもあります。(「学校に行きたいけど行けない→学校に行きたいという気持ちをもっている。」,「友達が自分をどう思ってるか気になる。気にする自分が嫌になる→周りの人の様子に気を配ることができる。」など)このようなことに,自分で気付くことも大切ですが,第三者(教師など)から,言ってもらうのは,クライエントにとって心地よいこと,また,自分自身のことを再確認できて嬉しいことのようです。
継続したかかわりで,変化を明らかにしましょう。
| カウンセリング的な簡単な受容や傾聴がベース |
| T: | ○○ちゃんの作品壊したの?今どんな気持ち? |
| C: | とても嫌な気持ち。 |
| T: | そうか。嫌な気持ちね。その嫌な気持ちを変える方法を考えようよ。あなたにできることは何かな? |
| ↑まず、受容 | |
| C: | ごめんって言う…でもね |
| T: | そうなんだ。悪口言われたんだ。じゃ,○○ちゃんに,何かしてほしいことがある? |
| ↑まず、受容 | |
| T: | ○○ちゃんにも,ごめんって言ってほしい。 |
こうして,「なぜ?」「どうして?」は重なり続け,やりとりは平行線のまま,子どもの困ったことの解決策は構築されませんでした。では,「なぜ?」「どうして?」から離れた,こんなやりとりだと,どうでしょう…
| T: | どうして○○ちゃんの作品壊したの? |
| C: | だって,先に○○ちゃんが,ぼくの作品の悪口言ったもん! |
| T: | なんで悪口言われたからって作品壊すのかなあ。あなたの作品が壊されたわけじゃないでしょ。 |
| C: | だって,くやしかったもん! |
| T: | くやしいからって,作品壊しちゃだめでしょ。なぜお友達の作品壊しちゃだめかわかる? |
| C: | …お友達が一生懸命作ったから… |
| T: | そのとおりよ。ちゃんとわかってるんじゃない。わかってんのに,どうして○○君の作品壊したの? |
| C: | だって,先に○○ちゃんが,ぼくの作品の悪口言ったもん! |
「なぜ?」「どうして?」からやりとりを始めると,さらに,「それはなぜ?」「どうしてそうしたの?」と,「WHY…?」が続くことが多いようです。そして,次第に子どもを追いつめていくことにつながりかねません。たとえば…
「なぜ?」「どうして?」から離れてみましょう。