| 商業教育と「ビジネス基礎」における商業の学習ガイダンス | |||||||||||||||
| 1.商業教育を取り巻く環境 | |||||||||||||||
| 商業教育を取り巻く環境はここ数年において大きく変化してきている。全学科に占める生徒数の割合(Excelファイル)を見ると分かるが,全学科における商業科の生徒数の割合はここ数年減少傾向にある。 これは,従来の商業に関する学科が,総合学科や情報科等に再編,統合されたためであるが,商業教育の規模が縮小傾向にあるという事実には変わりはない。この現実を直視して,今後の商業教育をより一層魅力あるものにするための創意・工夫が求められている。 ※(全学科に占める商業科生徒数の推移  |
|||||||||||||||
| 2.「ビジネス基礎」のねらい | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 学習指導要領にも示されている通り,「ビジネス基礎」のねらいは, | |||||||||||||||
| ①商業の各分野の教育において基本的な知識と技術 | |||||||||||||||
| ②ビジネスに対する望ましい心構えや理念 | |||||||||||||||
| ③ビジネスの現場で行われているさまざまな活動を合理的かつ主体的に実行できる能力と態度 | |||||||||||||||
| を身に付けさせることにより,経済社会の発展に寄与する人材を育成するための第一歩となるための科目である。 したがって,この科目の教育いかんで将来ビジネスにかかわる人材としての生徒の資質が決定されるほど重要な科目であるとの認識が必要である。 |
|||||||||||||||
| 3.「ビジネス基礎」の内容構成と学習指導形態 | |||||||||||||||
| 新学習指導要領の新設科目として導入された「ビジネス基礎」は,実教出版の教科書においては,表1 よって,この科目を指導するためには,この科目の目標をよく理解すると共に,学習内容の把握と学習指導法の研究開発に努め生徒が興味・関心をもって授業に参加できるよう配慮する必要がある。指導に当たっては,担当者会を開いて何点か担当者間の共通理解を踏まえた上で授業を実施していったが,今までの指導を振り返ると,さまざまな問題や課題が出てきた。そこで,こういった問題や課題の解決への糸口を見つけるために本校で実施してきた指導内容を振り返り,考察してみた。 |
|||||||||||||||
| 4.「ビジネス基礎」の指導における問題点とその考察 | |||||||||||||||
(1)「第1章 商業の学習ガイダンス」の指導や学習の動機付けがうまくできない 「ビジネス基礎」の担当者のアンケートから,「第1章 学習ガイダンス」の指導や学習の動機付けがうまくできないとの声があった。これについては,各学校の担当者間で,どういった資料,教材を使って何をガイダンスするのかを明確に意思統一をしておく必要がある。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| (2)興味・関心をもたせるための指導が難しい 第2章~第4章の各単元におけるビジネスに対して,興味・関心をもたせるための指導をどのようにすればよいのか。平板な教科書の内容の羅列だけでは,ビジネスに関して,生徒の興味・関心を沸き立たせることは難しい。ビジネスに関する興味・関心が薄れていけば,当然「ビジネス基礎」に対する学習意欲も喪失していくものと思われる。また,最近では全国的に,学力低下と共に学ぶ意欲の低下が話題に取り上げられ教育界で大変危惧されている。学ぼうとする意欲,学び続けようとする気持ちそれ自体が衰退すれば学力の維持も向上も覚束ないということになる。 |
|||||||||||||||
| ①そこで,学ぶ意欲を沸き立たせるためには,興味・関心をもたせるための指導が必要不可欠となる。そのために,最近のビジネス事情等のどういう点に触れさせていけば,生徒が興味・関心を抱いてくれるのか?新聞切り抜きなどのレポートの提出を事あるごとに取り上げ,学校内外で行われているビジネスに関心をもたせるようにするのも一つの方法である。また,資格取得のメリットを訴えることも学習の大きな動機付けとなる。 | |||||||||||||||
| ②教科書の内容(ボリューム)が薄いため,それを補足するための資料集が必要である。統計資料や,実際企業が行っている活動などのデータが不足している。生徒の興味・関心を沸き立たせるための経済に関するトピックスを毎時間の授業で準備しておく必要がある。具体的な企業名や商品名等の身近な話題を取り上げるのも一つの方法である。しかし,この科目の特徴やねらいとして商業教科のガイダンス的要素をはらんでいるため,従来の流通経済のような指導とは根本的に異なり,たくさんの内容を取り扱いすぎないよう注意しなければならない。 | |||||||||||||||
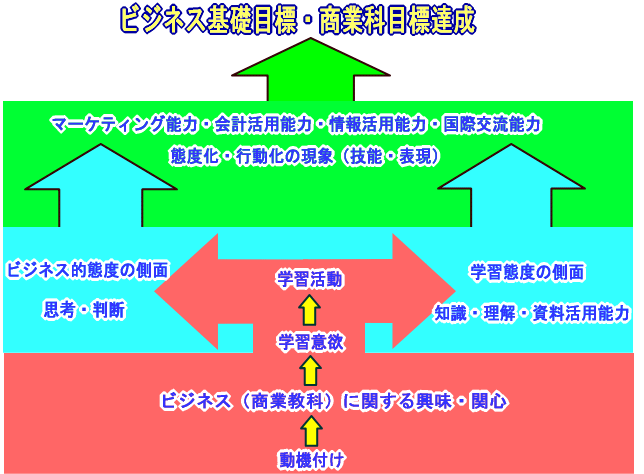 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3)現代のビジネスの動向を伝えるための工夫 (単元ごとに学習指導形態を考慮する必要性がある) ①現場実習の必要性 現代のビジネスの動向をリアルに感じ,興味・関心をもたせるための現場実習や,各業界のビジネスマンの講話などを学校行事の中でどのように取り入れていくべきか。 ②ビデオ教材や新聞記事のスクラップ等の活用 |
|||||||||||||||
| (4)教科書を超える範囲の内容をどこまで教えるのかの共通理解 従来の「流通経済」の教科書と比較すれば,「ビジネス基礎」の中味は浅薄なものとなっているので,各単元の学習内容(各項目)についてどこまで教えるのかの線引きが必要である。 特に2年次の「商品と流通」「商業技術」,3年次の「マーケティング」等の流通ビジネス分野における一貫した指導計画の策定が必要とされる。 |
|||||||||||||||
| (5)第5章 外国人とのコミュニケーションの指導方法 ・担当者の苦手意識の克服 ・英語科とのかねあいや連携 ・ALTとのTT |
|||||||||||||||
| (6)年間を通して一貫した指導の工夫 従来の「流通経済」では内容が体系付けられていたが,「ビジネス基礎」では,内容をかいつまんでいくような指導に陥りやすいので年間を通して一貫した指導を意識した取組が必要である。 |
|||||||||||||||
| (7)公民科との兼ね合い 現在中学校社会科の「公民」で使用されている教科書には,以下のような経済や企業に関する事柄が取り上げられている。よって担当者としてはある程度生徒がどういったことを学習してきているのかを踏まえた上で既知のものから未知のものへ指導していかなければならない。 |
|||||||||||||||