内容のまとまりごとの評価規準
○発想や構想の能力
ものの見方・感じ方を深め、感性や創造力を働かせて用途や機能、使用する者の気持ちなどを考え、豊かに発想し構想する基礎的能力を身に付け、形や色彩、材料などなどの構成を工夫し、美しく豊かな表現の構想をする。 |
| (第1学年の(2)「デザインや工芸などに表現する活動」の評価規準) |
 
|
|
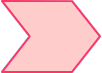 |

○発想や構想の能力
自然物の形の美しさを再発見するとともに、意図に合った構図や配色を工夫して、創造的な表現の構想をする。 |
|
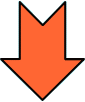 |

○発想や構想の能力
・スケッチから単純化や強調を考
え、自分なりの新しい形を構想
することができる。
・ラフスッケチにおいて、構成美
の要素を生かしながらバランス
よく全体の画面構成をすること
ができる。
・色相・明度・彩度のグラデーシ
ョンや色の感情の特性を考え
て、自分のイメージに合う配色
をすることができる。 |
|
|
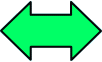 |
【「中等教育資料」 H15.8
文部科学省 村上尚徳教科調査官】より
「美術への関心・意欲・態度」
授業の中でどのように生徒に美術に対する関心や意欲を高めていくのかをよく考え、生徒を引きつけるような導入、作業が進むにつれ制作活動に熱中していくような展開の工夫、また、意欲がわかない生徒へはどのような手だてを講じるかなどを、事前によく検討しておくことが大切である。 |
「発想や構想の能力」
授業の中で「アイデアが思い浮かばない」「何をかいていいのかわからない」という発言が時々聞かれる。これは、題材が生徒にとって難しすぎたり、発想が深まるような言葉かけや資料の提示などが十分になされていなかったりするなど、指導計画に問題があることが多い。
多様なイメージが膨らむような幅のある題材を設定し、構想を練りながら描いたりつくったりできるように指導計画を吟味していくことが大切である。 |
「創造的な技能」
制作活動が単なる製作の技術を獲得するための場にならないように、生徒が創意工夫し自分の表現方法を生かして製作していけるような題材設定をすることが大切である。
また、ねらいに応じて基礎的な技能を指導していくことも必要である。 |
「鑑賞の能力」
生徒が作品などのよさや美しさを感じ取れるような場の設定や見方が深まるような適切な助言、お互いの表現意図を理解し合うために自分の作品について語り合えるような鑑賞の活動を指導計画の中に明確に位置付けておくことが大切である。 |
|
![]()