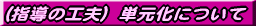○ねらいとする価値について
| 生きているものは一つとして同じではない。それゆえに命はかけがえのないものである。しかし,テレビなどで日々伝えられるのは,そのかけがえのない命が簡単に傷つけられたり奪われたりしている事件である。命を受け継いだはずの親子の間でさえ,殺人や虐待の事件が後を絶たない。 このような実態が,情報化の中で日々報道される一方,TVゲームやパソコンなどの普及により,子どもの中にも生死についての意識が希薄になり,他者への優しさの欠如や生命への軽視が問題になっている。また,少子化や核家族化,自然環境の消失などにより,兄弟姉妹や祖父母,動植物や昆虫との触れ合いの機会が減少し,日常生活の中で生命の美しさやはかなさに直接触れる機会も少なくなってきた。 生命が大切であるという認識は,だれでももってはいるが,それを実感としてとらえる機会が少なくなるなど子どもを取り巻く環境も大きく変わってきた。 私は子どもたちに,今,生きていることのすばらしさ,自分がかけがえのない存在であること,そして同様に,命あるものすべてが,かけがえのない存在として生きていることを伝えたいと思い,本単元を設定した。 |
○児童の実態について
| 本学級の児童は,大変明るく活発である。休み時間になると,教室や廊下や運動場で友達としゃべったり,走り回ったりしている姿をよく見かける。しかし,時には人が混雑している階段を走り抜けたり,教室の机の間を肩車で歩いたりなど,一歩間違えば命の危機にかかわるようなことを平気でしている姿を目にすることがある。また,教室で飼っているメダカやだれかが持ってきてくれた花に対しても,最初のうちは興味をもって世話をするが,興味をなくすと餌をやらなくても花瓶の中で枯れていても無関心でいることがある。さらに,友達との会話や授業の中でも,生命を軽視した発言を耳にすることがある。 何にもまして命が大切であるということは知識として十分理解しているはずであるが,行動が伴っていないのが現状である。 高学年になり自己の生き方や在り方に目を向け始めるこの時期に,生きる喜びや死の重さを知り,自他の生命を大切にしようとする心情を育てることは意義のあることと考える。 |
○資料について
| 本単元は,3時間で構成する。まず1時目では,人間の科学的値段を示し,命の重さを考えるきっかけを与える。これは単に人間を科学的な成分で分けてその値段を足したもので,子どもたちは「3000円で買えるわけない!」と反論するであろう。十分に反論を引きだした後で,二つの新聞記事を読ませる。一つはいじめによる自殺の記事で,もう一つは事故で父親を亡くしたある子どもの作文である。この二つの記事を読むことで,命の尊さについて自分と重ねながら死について考えさせたい。 2時目は,まず1時目の感想やオープンエンドの課題の中から命がなくなることで悲しむ人の存在がいることに気付かせるような内容のものを紹介する。それにより,子ども意識を“命を支える人”へと向けさせていきたい。その後,資料「とらねことじいちゃん」を読み,ビデオ「さよならリキ」を視聴することで,じいちゃんや飼い主の命に寄せる思いの深さを感じ取らせたい。 3時目も,まず2時目の感想やオープンエンドの課題の中から,特に命を支えてくれてる人としてお母さんを取り上げて紹介し,資料への導入を図る。その後,資料「この命のかがやきを」を読んで,精一杯娘の命を支えたお母さんと,その思いに必死でこたえようとする娘の姿を通して,生きていることのすばらしさ,命の尊さを味わわせたい。 |
○指導の重点
| 本単元の指導にあたっては,まず,資料における様々な「死」を通して「命」について考えさせる。次に「動物の命」→「人間の命」という順序で,「死」の周りにある「悲しむ人の存在」「命を支える人の存在」そして,「自分の命を支えてくれる人・大切に思ってくれる人の存在」に気付かせていく。このような学習により,多くの人の「命」についての思いを知ることで,生きていることのすばらしさ,命の尊さを考えさせていきたい。 子ども一人一人の生命尊重への思いや意識の芽生えや高まりを見ていくために,本単元では『ワークシート』や『ふりかえりカード』を準備して考えや思いを書かせていく。また,それぞれの授業をオープンエンドにして課題を与えたり,自学などで考える場を設定することで,授業と授業の間の子どもの様子も見ることができるようにする。そこで見付けた子どもの「よさ」を 子どもに返していくことで,子どもたち同士の分かち合いや子どもたち全体の生命尊重に対する意識を高めていきたい。 |
3 単元のねらい
| 『人間の科学的値段』や新聞記事,また生命尊重に関する資料やビデオに触れることで,命の大切さやそれを支える人の存在に気付かせ,自他の生命を大切にしようとする心情を育てる。 |
4 指導計画