| (1)基本的な「探究のプロセス」を身に付けさせましょう |
|
理科学習における基本的な探究のプロセスは次のようになります。 |
|
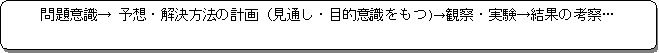 |
|
|
|
ここの「探究のプロセス」の各段階において,科学的な思考が必要となります。例えば,問題意識をもつ段階では,新しい事象と既有経験の類似点,相違点などから問題を見いだしたり,見通し・目的意識をもつ段階では要因を見付ける力や要因を関連付ける力を使って予想を立てたりします。結果の考察の段階では,結果を総合化したり,論理的に思考したりしながら原理・法則性を理解していきます。この「探究のプロセス」を理科授業で繰り返していくことで,子どもたちは,各段階でどのような思考をすればよいかを学び,問題解決の方法も身に付けていくことにつながっていきます。特に,小学校の高学年においては,中学校理科への橋渡しとして,ぜひとも意識して指導していきたいところです。
ただし,領域や内容によっては,このプロセスを柔軟に取り入れていくことが必要なのは言うまでもありません。
|
| (2)「見通しや目的意識」をもたせよう |
|
探究のプロセスにおいて,見通しや目的意識をもたせることは,問題解決の原動力となり,学ぶ必然性や主体的な学習を生むことにつながる重要な段階だと言えます。
観察・実験の見通しや目的意識をもたせるには,原因の予想とその予想を確かめる観察・実験の計画・検討,観察・実験結果の予想を行わせるとよいでしょう。つまり,子どもに観察・実験を行わせる前に「何を調べるために行うのか」「どのような方法で調べるのか」「結果はどうなるのか」を考えさせることです。
しかし,考える時間を確保するだけで,一人一人に「見通しや目的意識」をもたせることはできません。関連のある生活経験や既習事項を想起させたり,考えるヒントとなる事象や素材を提示したりすることなどが有効です。また,子どもに既習事項がなく生活経験もほとんどない場合は問題となる事象を見せるだけでなく,実際に体験させてみるなど五感を使わせることも効果があります。さらに,小学校高学年からは,定性的な観察・実験に終わらせないよう,学年に応じた指導を行い,条件を制御した観察・実験になるようにしましょう。
このような活動を通して,子どもたちは,要因を見付ける力,要因を関連付ける力,創意工夫する力,条件(変数)を制御する力,変数を定量化する力,数量的にとらえる力,およその量を見積もる力,比較対照する力等を使った科学的な思考をしていくことになります。
|
| (3)自分の考えを自分のことばや絵・図などで表現させよう |
|
探究プロセスの各段階での考えを自分のことばや絵・図で説明させることで,様々な科学的な思考を行います。表現させる自分の考えの内容としては次のようなものが考えられます。ただし,小学校中学年の子どもは,「やってから考える」帰納的な思考を得意としますので,教師の適切な配慮が必要となってきます。 |
|
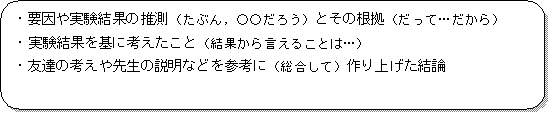
|
| (4)イメージをもたせよう |
|
子どもたちは目に見えないものを自分なりに想像し,概念を形成しながら学習しています。学習中,うまくイメージできないために理解が困難になってくる場合をよく見受けます。そのような場合,友達のイメージと比較させたり,教師がモデルを提示したりすることが必要です。また,領域・内容によっては五感を通した学習が困難なものがあります。人体の学習や天文の学習などのように観察・実験で得たデータだけでなく,図書やインターネットなどの資料も活用しながら進めていく学習もあります。このような内容は特に,モデルを使うことなどでイメージをもたせていく過程で科学的な思考をさせていくことが大事です。
|