●
|
テーマ設定に当たって
図画工作科の役割の1つに、子どもたちのものの見方や感じ方を深められるようにすることが挙げられる。授業の中で、単に素材や材料と出会うだけでなく、どのように加工していこうかなどの自分の思いや願いをもつことも重視されている。そこで、作品づくりの過程で、自分の身近な生活との関連性がないかを考えていくことで、作品へのこだわりや表現意欲を更に高めていきたいと考えている。
特に身近な素材のよさに着目するのは、子どもたちの感覚を揺さぶる上で大切であると考えるからである。図工の中での「素材」や「材料」の取り扱いを整理してみた(図1)。
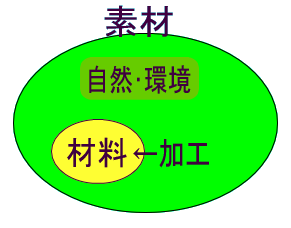 |
|
| (図1) |
|
|
・素材や材料のとらえ方について
材料を加工したものや自然・環境を含めて、素材として授業で扱われることが多い。素材・材料のよさを考えるには以下のような視点が考えられる。
| よさ(特徴)をとらえる視点 :色、形、可塑性、抵抗感、材質、強度、硬さ、軟らかさ、重量等 |
子どもたちにどのようなよさを見付けさせたいか、そのために、どのような題材、授業を考えるかが重要になる。その中で鑑賞の視点を設けることは大切である。だだし、題材や学年に応じて検討していく必要はある。見ただけでは分からない手触りや量感などを把握して活動することは、色彩や形態、材質に注目し、素材のよさを発見することにつながっていく。 |
身近な素材のもつよさを知ることにより、一層自分の体験と照らし合わせながら身近なものととらえることができ、素材や自分の作品への愛着心を育てることにもつながると考える。
以上のようなことから、身近な素材のよさを発見し、自分とのかかわりを求めていくことが重要であると考え、本テーマを設定した。 |
| ● |
研究の目標
身近な素材の特性を知り、自分とのかかわりを考えながら、身近な素材のよさに気付いて、造形表現を楽しむ児童の姿を目指す。 |
| ● |
研究の仮説
一題材の授業において、素材について考える時間と制作活動について自分とのかかわりを考える時間を設定すれば、身近な素材のもつ色彩や形態、材質に気付き、造形的な表現のおもしろさや不思議さ、美しさなどの意味や理由を考えることができるだろう。 |
|
《参考文献》
(1) 竹内 博 長町 充家 春日 明夫 村田 利裕 編 『アート教育を学ぶ人のために』 世界思想社 平成16年
(2) 濱田 浩 佐々木 達行 西村 徳行 編 『子どもの豊かさに培う共生・共創の学び
図画工作科』 東洋館出版社
平成17年 |
