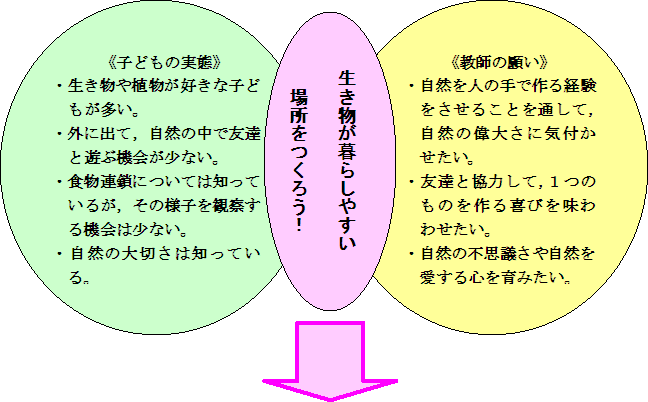| ○ |
田んぼで遊ぶ(過ごす)時間をできるだけ多くとることにより,子どもの興味・関心を高めたり,深めたりする。 |
|
|
| ○ |
この単元でどんな学びがあるのか,どんな力が身に付くのか,具体的に説明しておくことで,学習への意欲を高める。 |
|
|
|
|
| ○ |
子ども一人一人の興味・関心や意欲をみるために,ビオトープを中心に置いたウェビングをさせる。 |
|
|
| ○ |
学級で一つのウェビングに仕上げるときは,一人一人の意見を取り上げることができているか留意しておく。 |
|
|
| ○ |
課題を達成させるためにどのようなことに取り組むといいのか一人一人に考えさせるために,時間を十分確保する。 |
|
|
| ○ |
学習したことをどのような方法で人に伝えるかを意識させながら計画を立てさせる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○ |
学級で大きな一つの課題に向かって学習を進めていることを確認することで,どんな課題に対しても自分の課題として考えるように心掛けさせる。 |
|
|
| ○ |
ビオトープを作る場所については,学校に近い場所や水が確保しやすい場所など,あらかじめ子どもたちに設置条件を考えさせておく。 |
|
|
| ○ |
できるだけ生き物を死なせたり,植物を枯らせたりしないように,生き物や植物については,十分本やインターネット等を利用して調べさせておく。 |
|
|
| ○ |
ビオトープは完成させるまでの過程も大切であるが,それとともに完成した後のビオトープの維持についても十分な気配りが必要である。 |
|
|
| ○ |
教師による言葉掛けや地域の人の協力,学習環境の工夫などにより,ビオトープ作りを通して,自然環境についても考えさせる。 |
|
|
|
|
| ○ |
自分の計画に基づいて学習を進めているか,一人一人の状況を把握しておく。 |
|
|
| ○ |
活動を進めていく中で,気になるところについて意見を出し合ったり,よりよい方法を教え合ったりする。 |
|
|
|
|
| ○ |
招待する人の年齢や人数,説明する場所等を考えた上で,どのような説明の仕方がよいのか考えさせる。 |
| ○ |
リハーサルでは,説明の内容面からと説明の仕方など技術面から考えて,アドバイスをするように伝える。 |
|
|
| ○ |
子どもたちがそれぞれ学習してきたことを,ビオトープに来てくれた人や友達など,できるだけ多くの人に評価してもらうようにする。 |
|
|
|
|
|
|
| ○ |
単元を通して学んだことを,自分やグループの学習ファイルなどを参考にさせながらまとめさせることにより(凝縮ポートフォリオ作成),自分の学びを確認させるとともに自分の成長に気付かせる。 |
|
|
| ○ |
これまでの自分の学習の足跡をまとめたファイル(ポートフォリオ)を使って,子ども一人一人と対話をしながら評価を行う。その際,この単元で子どもが身に付けた力(身に付きつつある力)を認めてやるとともに,子ども(自分自身)が課題を達成することができたという達成感,満足感,成就感を味わわせるように賞賛する。 |