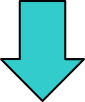|
|
●第2回ミニ学級会の計画,準備
・議題についての提案
・ミニ学級会までの仕事と分担
 |
| 計画委員会の話合いの様子 |
|
| 「第1回ミニ学級会で出た意見を整理しよう。」 |
「一番意見が多かった『ありがとう集会』がいいよ。がんばっている係にお礼を言いたいという人が多かったよ。」
|
| 「『ありがとう集会』に決めて,プログラムに係のことで知りたいことや係へのお願いを盛り込めば,みんなの考えが生かされるんじゃないかな。」 |
「だけど,仕事をしていない係があるということについては解決できないんじゃないかな?」
「このアンケートの結果をみんなに見せて決定しよう。」 |
|
| ● |
ミニ学級会の計画,準備を進めさせる。 |
| ・ |
アンケートを集計した結果を資料として教師がまとめておく。
準備した資料
・アンケート集計結果 |
| ※ |
計画委員会の経験のない子どもたちにとって,議題を1~2つにしぼることはなかなか難しい。教師の指導性を発揮して,活動をさせながらやり方を教えていくようにする。内容については,教師の意見で左右されることのないように配慮する。学級のみんなが納得のいく議題の決定のためには,どういう形でミニ学級会に提案した方がいいかを計画委員会の子どもと教師が一緒に考える。 |
|
|
|
|
| ●アンケート集計結果の説明 |
「係ががんばっているから,ありがとう集会がいいと思うよ。そして,クラスがもっと楽しくなると,係ももっと仕事をすると思うよ。」
「あまり仕事をしていない係もほめてもらうともっとがんばると思うから『ありがとう集会をしよう』がいいな。」
※みんなで理由を言い合いながら,「ありがとう集会を開こう」に決まった。
「出し物をしたいな。係のことを劇で紹介したい。」
「係にお礼を言うコーナーをつくりたいし,プレゼントもあったほうがいいなあ。」
※集会だからお菓子があった方がいいという意見をもっている子どもがいたが,反対意見が出て「持ってこない」に決まった。
※意見がたくさん出て,出し物をプログラムに入れること,他は,計画委員会が提案することに決まった。 |
| ● |
黒板に掲示する資料を準備させる。 |
| ● |
全員の納得した結論が得られるように進行を見守り,助言する。 |
| ● |
話合いのまとめをきちんとさせておく。 |
|
第2回ミニ学級会資料 |
|
●議題決めの話合いをする。
|
議題案 |
| ・ |
「係さん,ありがとう集会」を開こう |
| ・ |
係の発表会をしよう |
| ・ |
係活動をふり返ろう |
| ・ |
係を決め直そう |
|
| ●話合いのまとめをする。 |
|
|
|
|
| 作成した学級会計画 |
| 1 |
議題 |
|
「係さん,ありがとう集会を開こう」 |
| 2 |
提案理由 |
|
がんばっている係にお礼を言ったり,これからも係の仕事をもっとがんばろうという気持ちになったりするような集会をしたい |
| 3 |
柱 |
|
①係の出し物は,どんなものがいいか。 |
| ②集会の準備は,だれがどんなことをするか。 |
|
| ● |
学級会の準備を進めさせる。 |
| ・ |
第2回ミニ学級会で決まったことや出された意見を整理させる。 |
| ・ |
教師も一緒に議題・提案理由・柱をどうするかについて今までの話合いをもとにまとめ,話合いカードを作成し配布の準備をさせる。 |
| ・ |
学級活動コーナーへの書き込みをさせる。 |
| ※ |
出し物を入れたプログラムについては,朝の会などで全員に知らせておくようにアドバイスをする。 |
|
|
|
| 「他のクラスの人はありがとう集会をしたことがあるかな。聞いてみよう。」 |
| 「係が,なかよく仕事をするようにどんな出し物をしたらいいか,縦割りの上級生に聞いてみよう。」 |
|
| ● |
休み時間などを利用して進んで情報を集めるように声かけをする。 |
| ● |
話合いカードに目をとおし,アドバイスを書いたり個別に指導を行ったりする。 |
| ・ |
話合う内容,目的の理解が不十分な子どもや自分の考えを話合いカードに書けない子どもには教師が助言する。 |
|
|
|
●学級会の準備②
| ・ |
学級会の進行計画を立てる
時間配分・決議の仕方など |
| ・ |
話合いカードから意見を予想して板書計画を立てる
(意見を書いた短冊を作る) |
|
| 「柱1については,劇や紙芝居などという意見が多いね。」 |
| 「劇や紙芝居などでどんなことをするのかな。」 |
| 「中味についての話を深めたいね。」 |
| 「柱2は,『たくさん型』で決めていこう。」 |
|
| ● |
学級会の進め方マニュアルを参考に進め方を考えさせる。 |
| ● |
「出し物を係に任せて自由にする」ということでは,話合いが深まらない。劇や紙芝居などでどんな内容にしたらいいかについての話合いができるようにする。 |
|
 |
| ミニ話合いの風景 |
|
| 「○○さんに聞いてもらいたいな。」 |
| 「友だちは,どう考えているのかな?」 |
「早く,学級会で話し合いたいな。」
「今度の学級会では,発表しよう。」 |
|
|
| ※ |
発表に自信が持てない子どももいるので,仲のよい友だちとペアを作らせ,帰りの会で自分の意見を発表する練習をさせる。
発表に対して消極的になりがちな子どもに励ましや声かけを行う。
|
|
|
|
| 学 級 会 |
| 計画委員会(4名)の仕事分担 |
|
| 議長 |
1名 |
副議長
(めあて,よかったことの反省) |
1名 |
| 黒板書記 |
1名 |
| ノート書記(計時) |
1名 |
|
※ |
| 学級会の始めの「先生から」の際に,提案理由を補強する話をする。 |
| 司会や書記の子どもたちは経験が少ないので,意見を整理して進め方を助言する。教師の意見に左右されることもあるので話合いの内容には口を出さないで見守るようにする。 |
|
| ※ |