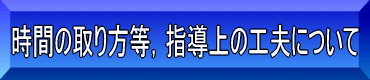 |
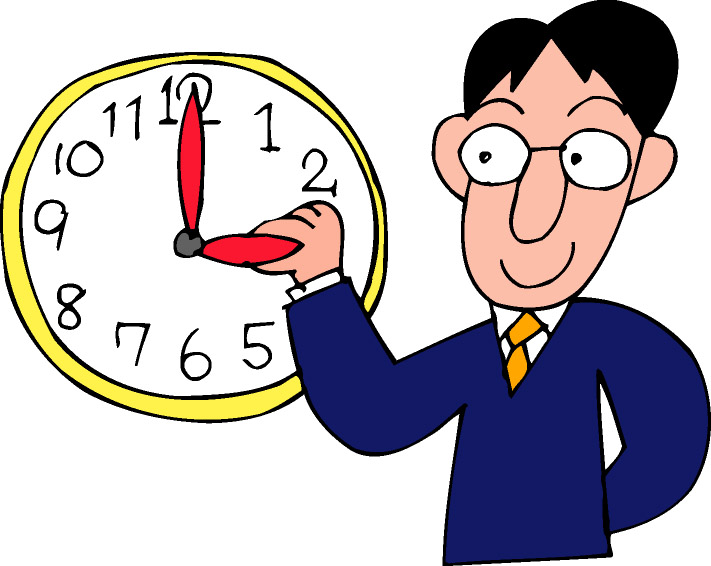 |
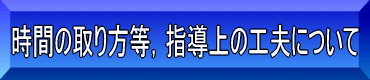 |
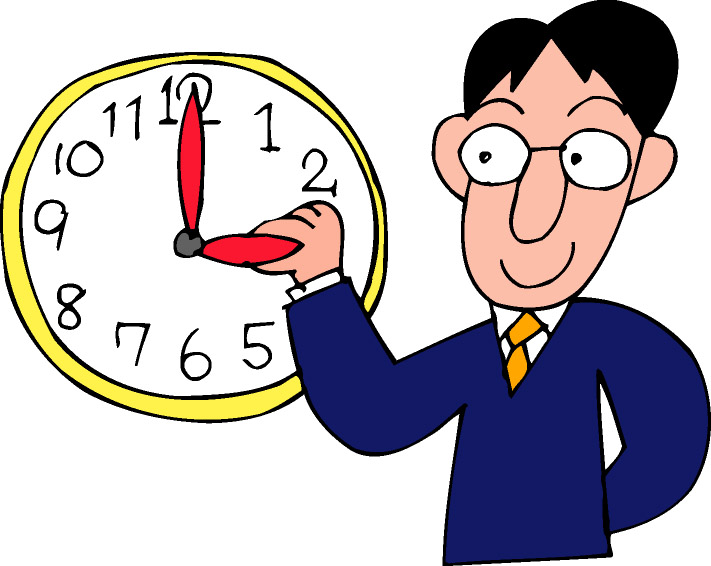 |
学級活動は年間35時間(1年生は34時間)以上,実施するようになっています。
そのうち内容(1)「学級や学校の生活の充実と向上に関すること」の中核をなす活動が「話合い活動」であり,次のような観点で繰り返して実施することが求められます。
しかし、事前指導に充てる時間がなかなか取れないといった理由から,話合い活動がなかなか計画的に実践できないという現実問題があります。
![]()
![]() 月1ペースで,確実に話合い活動に取り組もう!
月1ペースで,確実に話合い活動に取り組もう!
| 事前指導重視の話合い (学級会までの手順に慣れていないときや,話合いの手順をしっかりと身に付けさせたいとき) |
実践重視の話合い (実践までの準備に時間を要する集会のときなど) |
|
| 1週目 | 議題決定(昼休み・放課後など) 計画委員会(昼休み・放課後など) |
議題決定(昼休み・放課後など) 計画委員会(昼休み・放課後など) リサーチ(朝,帰りの会) |
| 2週目 | 計画委員会・リサーチ(朝,帰りの会) 話合い(授業) |
話合い(授業) 実践準備 |
| 3週目 | 実践準備(授業・昼休み・放課後など) 実践(授業) |
実践準備(授業・昼休み・放課後など) 実践(授業) |
| 4週目 | 時間が足りないときのゆとりの時間 | |
実践意欲をいかに持続させるかという点では問題がありますが,話合い活動の力を確実に高めることができます。慣れてくるとともに自主的にできるようになりますし,全員が司会の経験をするためにも,ぜひ1ヶ月に1回は話合い活動に取り組みましょう。
![]()
![]() 「ミニ学級会」を取り入れよう!
「ミニ学級会」を取り入れよう!
 |
学級の中には様々な問題が起こります。学級全体の問題で,児童に解決を図らせたい問題も必ず出てきます。解決を急ぐような問題については,柱を1本化し,日直に司会をさせるといった「ミニ学級会」に取り組むことで,児童の話合いの力や友達と折り合っていく力が高まり,その経験が話合いの効率化にもつながります。 |
![]()
![]() 話合いの資質を日常の指導で高めよう!
話合いの資質を日常の指導で高めよう!
「話す」「聞く」といった力は,学習においても日常生活においても基盤となるものです。以下のような指導を日常,継続していくことで話合いの資質が高まります。
| (1) あいさつや返事がきちんとできるようにする | 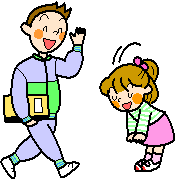 |
||
| ・ 朝のあいさつ,帰りのあいさつがきちんとできるようにする。 | |||
| ・ 名前を呼ばれたとき,用事を頼まれたときなどに,はっきりと返事ができる。 など | |||
| (2) 発言の仕方を指導する | |||
| ・ スピーチや解き方の説明といった活動を積極的に取り入れる。 | |||
| (3) 聞くときのきまりを指導する | |||
| ・ スピーチや解き方の説明といった活動を積極的に取り入れる。 | |||
| ・ 笑ったり,文句を言ったり,ひやかしたりしない。 |
|||
| ・ 静かに最後までしっかりと聞く。 など | |||
| (4) 何でも話せる場の設定をする | 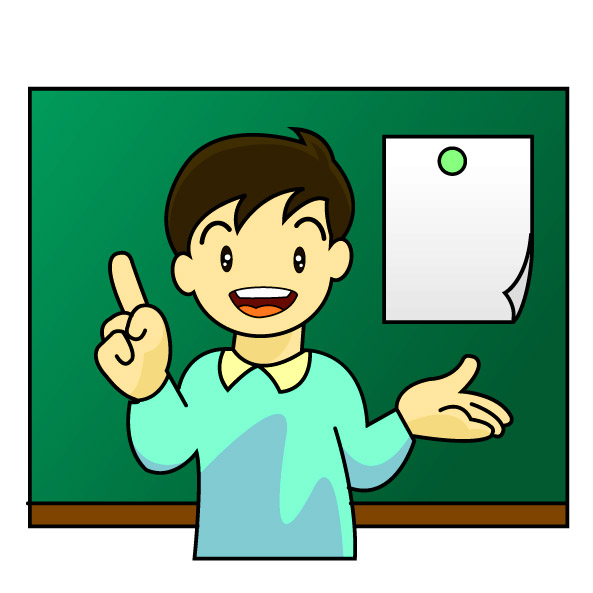 |
||
| ・ 1分間スピーチ(朝の会)。 | |||
| ・ 小グループでの話合い(バズ学習)。 | |||
| ・ よかったこと,うれしかったこと(帰りの会)。 など | |||
| (5) よりよい人間関係をつくる | |||
| ・ 個別の支援・指導と集団の指導。 |
|||
| ・ 人間関係をはぐくむ日ごろの取組。 | |||
![]()
![]() 話合い活動に役立つ教室環境を作ろう!
話合い活動に役立つ教室環境を作ろう!
学級活動コーナーや話合いを助ける掲示物があると,学級の雰囲気が高まりますし,話合いの指導に役立ちます。
何より一度作成すると,年間を通して使え,修正を加えると他の学年でも使えるというメリットがあります。1学期のうちに整備しておきたいものです。
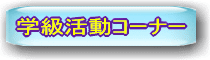 |
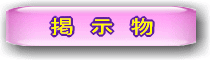 |
|
|
![]()
![]() 総合的な学習の時間との関連を図ろう!
総合的な学習の時間との関連を図ろう!
特別活動のねらいと総合的な学習の時間のねらいには「自ら課題を見付け,自ら課題を解決する力を身に付ける」という共通点があります。学級活動で培った資質や能力が総合的な学習の時間に生かされたり,その逆があったりと,両者は双方向的な関係にあると考えられます。
ただし,両者の相違点もあります。
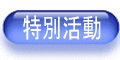 |
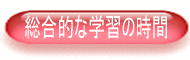 |
|
| 活動 | 集団による活動 | 個人の課題に基づく活動 |
| 課題 | 学級・学校生活の充実・向上に関する課題 | 地域や学校の特色に応じた課題 |
| 児童の興味・関心に基づく課題 | ||
| 情報・環境・福祉などの総合的な課題 | ||
| 解決方法 | 望ましい集団活動を通して | 問題解決的学習を通して |
| 体験的な学習を通して |