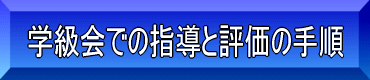
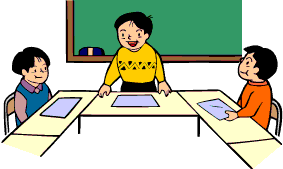
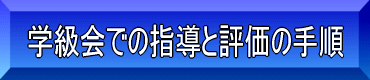
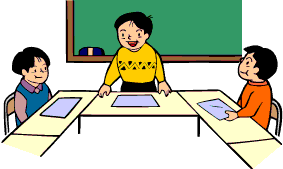
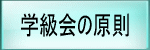 |
学級会は児童が自主的に進めていくものであり,児童の手に委ねなくてはなりません。ただし,次のような条件を満たしている必要があります。 |
|
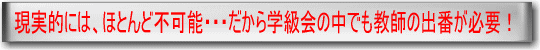
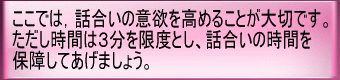
| 見守る姿勢を基本として,個別の支援を行う | 補助簿(座席表)を利用して,評価を行う | |
| いい意見をもっていながら,発表できない児童へ・・・ 話合いに集中,協力できない児童へ・・・ 友達を中傷するような意見を出した児童へ・・・ 話合いの柱からそれた意見を繰り返す児童へ・・・ 司会が,どう進行していいか分からなくなったとき 黒板書記が意見の速さについていけないとき など・・・ |
本時の評価規準に基づいた評価 話し方や聞き方に対する評価 話合いを高める発言への評価 |
|
| 1時間で児童全員を評価しようとすると,教師の出番を見過ごしてしまいます。 話合いを繰り返すことと,児童の自己評価,相互評価をチェックすることで,一人一人の評価をしていきましょう。 |
||
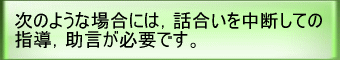
| 問題 | 解決への指導,助言 |
| 話合いが停滞したとき | 今,何を話し合っているのかを明確にしてやる。 賛成理由,反対理由を整理し,それぞれの意見のいいところと問題点を明確にしてやる。 出された意見の中から賛成理由のあったものをいったん絞り込んで話合いを深めさせる。 2つの意見を合わせたり,提案理由に近い意見はどれなのかといった話合いの方向付けをしてやる。 前の発表に関連した意見を出すように助言をする。 小グループや近くの人と相談する時間を設ける。 |
| 話合いの柱から脱線したとき | |
| いろんな意見が出て,混乱したとき | |
| 児童が決める範疇外の意見が出たとき | 意見が出た時点でなぜ,決められないのかを明確に伝え,方向修正をする。 |
| 実践不可能なことが決まりそうになったとき | 明らかに実践不可能な場合は,早めに方向修正をする。そうでない場合は,ルール等の工夫で実践を目指す。 |
|
・ 話合い中のよりよい発言を取り上げ,賞賛する。
・ 観察係の評価を補足する。
・ 態度面等,成長の見られる児童を賞賛する。
・ 司会団に対してねぎらいの言葉をかける。
・ 話合いの中で課題となったことが次回のめあてとなるよう,意識付けをする。
・ 実践に向けての意欲付けや今後の見通しをもたせる。
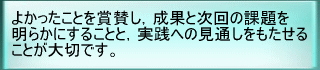 |
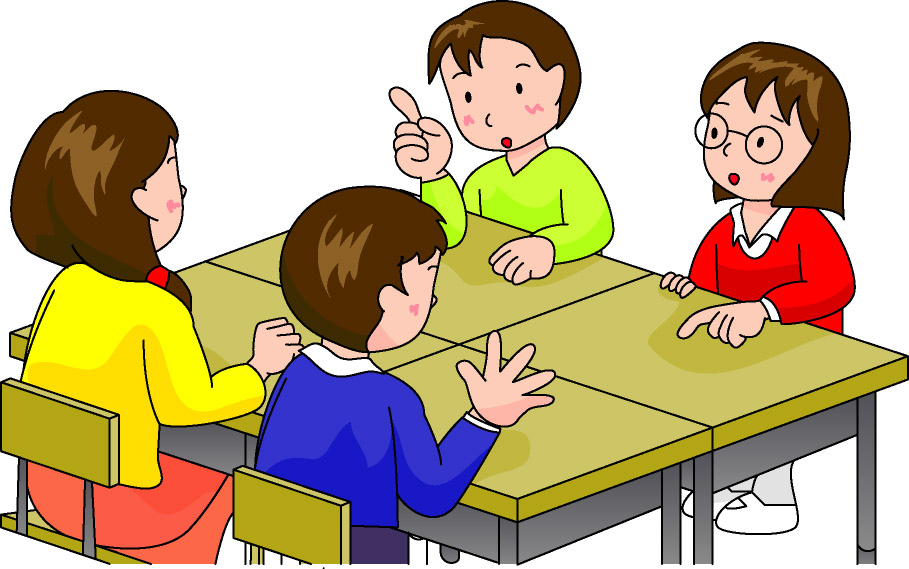 |