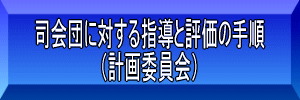 |
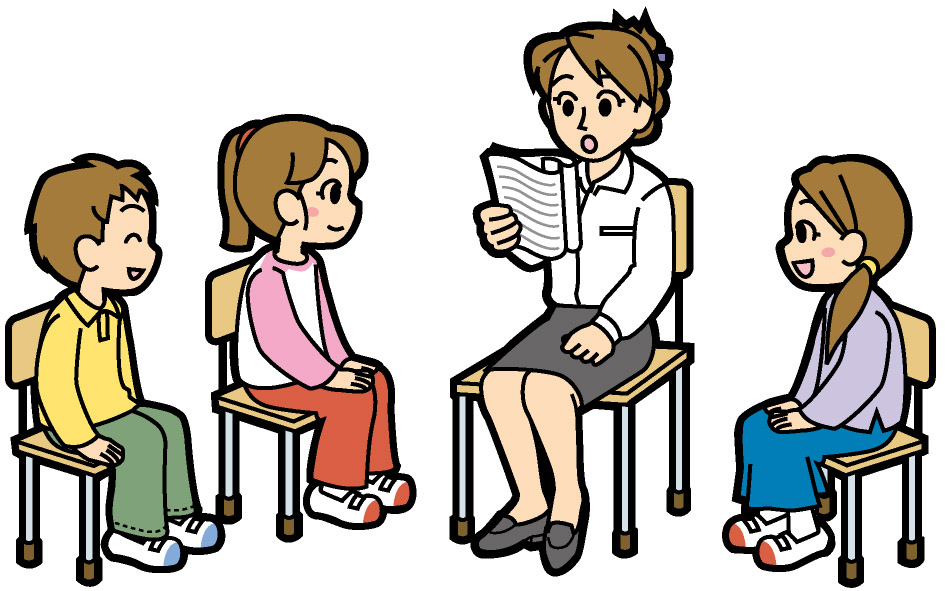 |
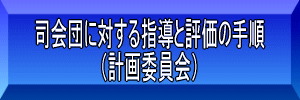 |
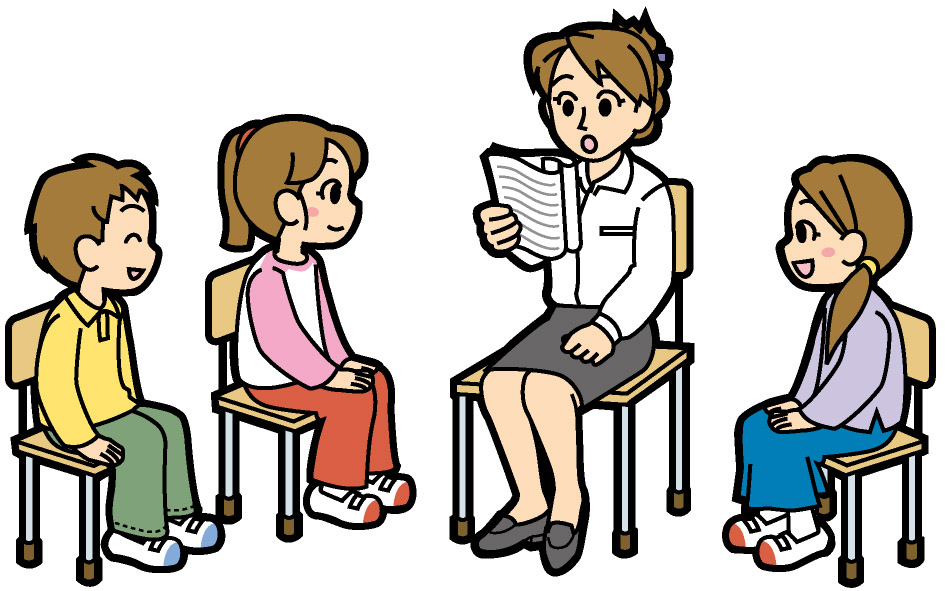 |
| 議題を決定する | ||
| 議題箱に入った問題の処理の仕方を検討する | ||
| 議案書(話合いカード)を作成する | ||
| 司会団の役割分担をする | ||
| 学級活動コーナーに議題や提案理由を提示する | ||
| 学級会進行の確認をする |
|
|
||||||||||||
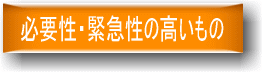 |
| ・「ありがとうカード」等,議題を出した児童に渡し,次への意欲につなげる。 ・議題を出した児童が納得するような処理を検討する。 |
||||||
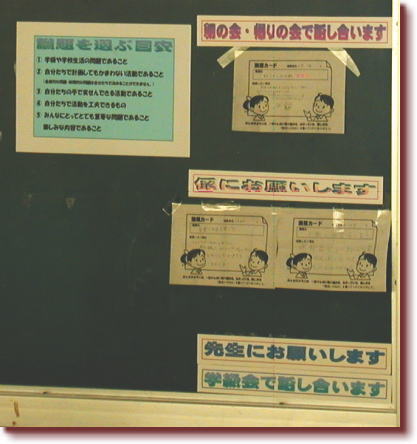 |
|
|||||
| 実践が見えるような議題,意欲が高まるような議題を工夫させる。 (○○しよう ○○を決めよう ○○を作ろう など) |
||
| なぜ,この議題について話し合うのか,その必要性が伝わるような提案理由を考えさせる。 | ||
次のような視点で,話合いのめあてを決めさせる。
|
||
時間内で話合いが終わるように,柱立てを焦点化する。
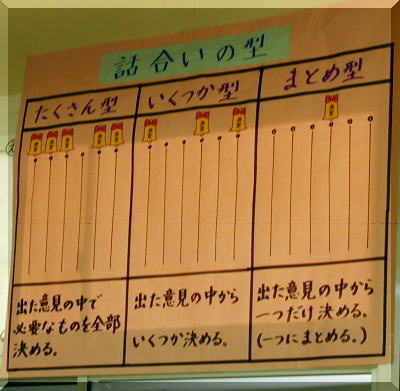 話合いの柱の型 |
|
|
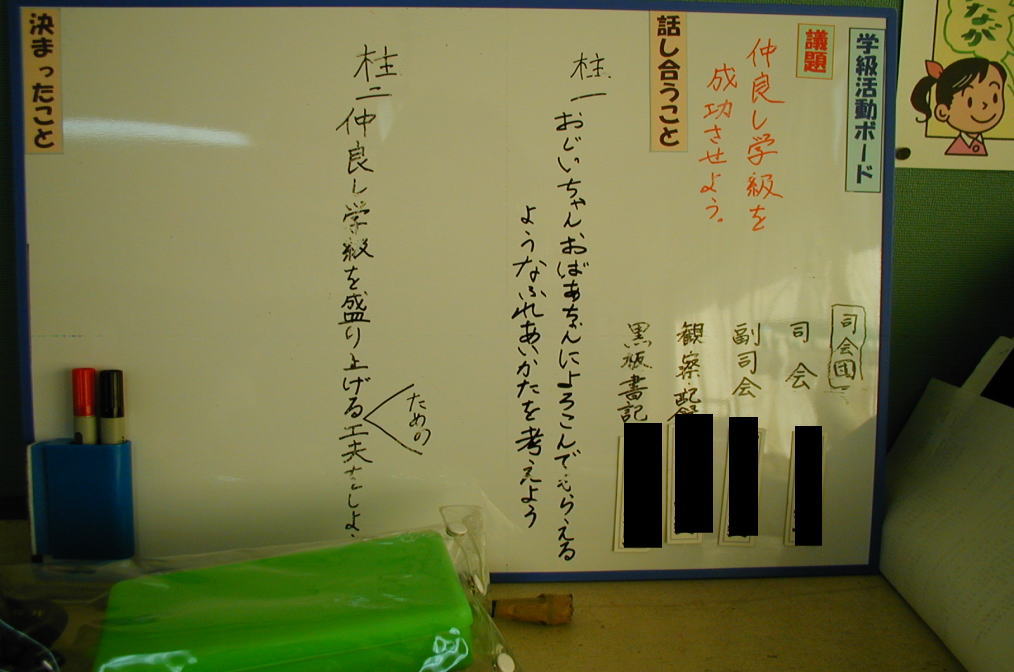 |
|
| 学級活動ボード(話合い活動のお知らせ) |
 |
||
|
||
|
||
|
||
| 学級会提案ボード |