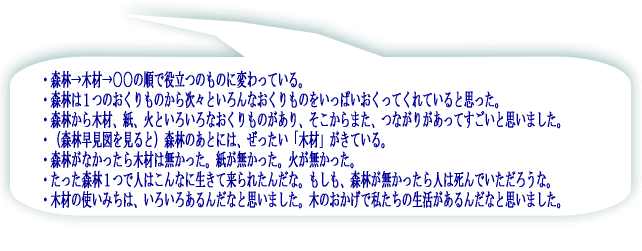| �ߒ� |
�w�K���� |
���w���@�@�@�@���]�� |
| �s�P |
�s�Q |
| ���� |
�P�@�O���܂ł̊w�K��z�N���A�{���̂߂��Ă����B |
���{���̊w�K�����Ɉӗ~�ƌ��ʂ����������邽�߂ɁA�u�X�ё����}�v�Â���ɍv�������u�ǂ݁v�┭�����������������Ȃ���Љ��B |
������܂ł̊w�K�łł����u�X�ё����}�v���v���W�F�N�^�[�Œ���B |
| �����Ɖ́u��������́v�̂Ȃ��肪�悭������悤�ȁu�X�ё����}�v�����낤�B |
|
| �W�J |
�Q�@���Ɖ́u��������́v�̊֘A��������悤�ɑ����}������B
|
(1)
|
���́u��������́v�̎��������B |
|
(2)
|
�́u��������́v�̎�������� |
�y���Ƃ̗l�q�@�z
�@

�y���Ƃ̗l�q�A�z |
�����O�ɔ����o�����Ă������u��������́v�\�����A�ڂɌ����鐶���i�ƖڂɌ����Ȃ����̓�����̖����Ƃ��ĕ\������Ă�����̑S�����m�F�ł���悤�ɂ���B
��������������J�[�h�����ɓ\���Đ���������A�tⳎ��̑�����������肷�邱�ƂŁA����Ƃ��̓����A����Ƃ��Ă����Ă�����̊T�O�����Ƃ炦����悤�ɂ���B
���@�����ޕʂ�����Ȃ����肵�Ȃ�����ׂĂ���B
�y�]���K���E�F�����@���[�N�V�[�g�z |
�`�@����������Ɉʒu�t���闝�R�m�ɂ��Ȃ�����ׂĂ���B
|
| �a�@�c�̌��̂Ȃ�����l���ĕ��ׂĂ���B |
| ���@��ʊT�O�̌����ɑI��A�⒇�ԂɂȂ�����܂Ƃ߂��肷��悤�ɑ����B |
|
�������̃J�[�h��\�邱�ƂŁA���̓����⎆���i���ȗ�����Ă��邱�ƂɋC�t����悤�ɂ���B�܂��A�u�Y��܂��v�̈ʒu��₤���ƂŁA�X�тƉ̊Ԃɂ���ׂ��u�X�сv����u�v�̊Ԃɂ���ׂ��L�q�̏ȗ��ɋC�t�����Ă����B
|
���S�̂ő����}���m�F����ۂ́A�K�v�ɉ����āA�������ɂȂ�A����̈ʒu���ɑ��鎿���������A��r�����邽�߂ɈႤ����̈ʒu�t�������������}���o�����肷��B |
�R�@���������X�ё����}�����ċC�t�������Ƃ�v�������Ƃ������A���\����.

| �y���҂��鎖��̒���_�z |
�E����̐��̑���
�E����̎�ނ̑���
�E����̂Ȃ���̒���
�E�؍ށA���A�̂R�̎���
�@�̈Ⴂ�� |
�y���Ƃ̗l�q�B�z
|
���u�؍ނ���ł������̎���v�u�؍ނ���ł����Y��܂�����o��ɂ���Ăł�������v�ɉ����A���O�Ɋw�K�����u�؍ނ̎���v�����A��r�����邱�ƂŁA�X�тɋ߂����Ⴉ�牓������ւƏ����悭�������Ă���M�҂̈Ӑ}��ǂݎ���悤�ɂ���B
| ���@����̂������̓����₻��ɑ��鎩���̍l����\�����Ă���B�y�]���K���C�F���[�N�V�[�g�@�����z |
| �`�@�M�҂̎���̈Ӑ}�₻�̌��ʂɂ��ď�������b�����肵�Ă���B |
| �a�@����̂������̓����ɂ��ď�������b�����肵�Ă���B |
| ���@���̑����}����ɁA����̐����ށA����̈Ⴂ�� ���ڂ�����B |
|
�������}�̎��o�I�ȗ����̏�������Ȃ���A�X�т��玖�Ⴊ�����Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�t�����A�Ȃ����̂悤�ɏ������̂��M�҂̈Ӑ}��T���悤�ɂ���B
|
������̓����ɋC�t�����邽�߂ɁA�K�v�ɉ����s.�@�P�̔���ɑ��A�������ɂȂ�A����̂������ɂ��Ă̔���������B |
|
| �I�� |
�S�@����̊w�K�����ʂ��B |
���{�_�㔼�́u�ʂ̂�������́v�������}�Ɉʒu�t���Ă������Ƃ��m�F����B |
���u�ʂ́v�̈Ӗ����ӎ������邽�߂ɁA�������ɂȂ��Ď��₷��B |